夏休みの宿題や調べ学習で、「レポートを提出してください」と言われて、何から手をつけていいか分からず困っていませんか?特に、パソコンではなく手書きでレポートを作成するとなると、どうすれば見やすく、分かりやすく書けるのか悩んでしまいますよね。
この記事では、そんな中学生のみなさんのために、手書きでのレポートの書き方を、テーマの決め方から、情報の集め方、きれいなまとめ方、そして提出前の最終チェックまで、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事を読めば、先生や友達に「すごい!」と言われるようなレポートが、きっと書けるようになります。初めてレポートを書く人も、もっと上手に書きたい人も、ぜひ参考にしてください。
中学生のためのレポート書き方【準備編】〜何から始める?〜

レポート作成は、いきなり書き始めるのではなく、しっかりとした準備から始まります。準備をきちんと行うことで、その後の作業がスムーズに進み、質の高いレポートを仕上げることができます。ここでは、レポート作成の第一歩となる「テーマ決め」「道具の準備」「スケジュール管理」の3つのポイントについて、詳しく解説していきます。
まずはテーマ(主題)を決めよう
レポート作成で最も大切ともいえるのが、テーマ(主題)決めです。テーマとは、そのレポートで何を調べて何について書くかという中心的な課題のことです。 面白そう、読んでみたいと人が関心を持つようなテーマが良いでしょう。 テーマを決める際は、まず自分が興味・関心を持てることから考えるのがおすすめです。 例えば、好きな歴史上の人物、気になる社会問題、普段の生活で「なぜ?」と疑問に思ったことなど、どんなことでも構いません。 興味のあるテーマなら、調べるのも楽しくなり、より深い内容のレポートになります。
テーマが大きすぎると調べるのが大変になるため、具体的なテーマに絞り込むことが大切です。 例えば、「環境問題」という大きなテーマではなく、「身近なリサイクル活動について」や「地域のゴミ問題とその対策」のように、具体的で調べやすい範囲に絞ると、レポートがまとめやすくなります。 教科書で習った内容から発展させてみるのも良い方法です。
必要な道具をそろえよう
手書きでレポートを作成するためには、適切な道具をそろえることが大切です。まず、レポート用紙はA4サイズが一般的です。 無地のものよりも、罫線(けいせん)が入っている方が文字をまっすぐ書きやすいのでおすすめです。
筆記用具は、HBかBの濃い鉛筆やシャープペンシル、または黒のボールペンを準備しましょう。 文字を丁寧に、はっきりと書くことが読みやすさにつながります。 もし間違えてもきれいに消せるように、よく消える消しゴムも用意しておくと安心です。 また、図やグラフを描くために、定規やコンパス、色鉛筆やカラーペンもあると便利です。写真や資料を貼り付ける場合は、のりやテープも忘れずに準備しましょう。 これらの道具を事前にそろえておくことで、作業を中断することなく、集中してレポート作成に取り組めます。
スケジュールを立てて計画的に進めよう
レポート作成は、思った以上に時間がかかることがあります。提出日直前になって慌てないように、まずは全体のスケジュールを立てましょう。初めにレポートの提出日を確認し、そこから逆算して計画を立てます。
スケジュールは、大きく分けて以下のステップで考えると分かりやすいです。
・ ステップ2:集めた情報の整理とレポート構成の決定(例:次の2日間)
・ ステップ3:下書きの作成(例:次の3日間)
・ ステップ4:清書と図表の作成(例:次の2日間)
・ ステップ5:最終チェックと修正(例:最後の1日)
このように、各ステップにどれくらいの時間をかけるかを具体的に決めておくことで、計画的に作業を進めることができます。無理のないスケジュールを立て、余裕を持って取り組むことが、質の高いレポートを完成させるためのポイントです。
分かりやすいレポートの構成とは?〜手書きでも伝わる組み立て方〜

レポートは、ただ調べたことを書き並べるだけでは、読んだ人に内容がうまく伝わりません。分かりやすいレポートには、決まった「型」があります。この型に沿って書くことで、内容が整理され、論理的な文章になります。ここでは、手書きレポートでも伝わる基本の構成について解説します。
レポートの基本構成「序論・本論・結論」
レポートの最も基本的な構成は、「序論(じょろん)」「本論(ほんろん)」「結論(けつろん)」の3つの部分から成り立っています。 これは、どんなテーマのレポートでも共通する組み立て方です。
・ 序論:「はじめに」の部分です。このレポートが何について書かれているのか、なぜこのテーマを選んだのかを紹介します。
・ 本論:「調べた内容」の部分です。集めた情報やデータを使って、テーマについて詳しく説明します。レポートの中心となる最も重要な部分です。
・ 結論:「まとめ」の部分です。本論で述べた内容を要約し、分かったことや自分の考えを述べます。
この3つの構成を意識することで、話の流れがスムーズになり、読み手はレポートの内容を理解しやすくなります。
序論(はじめに)の書き方:何を、なぜ調べるのか
序論は、レポートの導入部分であり、読み手が最初に読む大切なパートです。 ここでは、主に3つのことを書きます。
一つ目は、「研究のテーマ」です。 このレポートが何について調べているのかを明確に示します。 二つ目は、「研究の動機や目的」です。 なぜこのテーマに興味を持ったのか、そのきっかけとなった体験や疑問を書きます。 例えば、「ニュースで食品ロスの問題を知り、自分たちの家庭ではどれくらいの食品ロスが出ているのか気になったから」のように、具体的なきっかけを書くと、読み手の興味を引きやすくなります。
三つ目は、「このレポートで何を明らかにしたいのか」です。 レポート全体を通して、自分が何を調べ、何を伝えたいのかというゴールを示します。 序論を読むだけで、レポート全体の概要が分かるように書くのが理想です。
本論(調べた内容)の書き方:情報を整理して分かりやすく
本論は、レポートの中心部分で、最も多くの文字数を割く場所です。 ここでは、序論で立てた問いに対して、集めた情報やデータを使って具体的に説明していきます。
ただ情報を並べるのではなく、いくつかの章や節に分けて整理することが大切です。 例えば、「日本の食品ロスの現状」「家庭でできる食品ロス削減の工夫」「学校給食での取り組み」のように、テーマに沿っていくつかの小見出しを立てると、構成が分かりやすくなります。
各章では、本やインターネットで調べた事実やデータを正確に記述します。 その際、図やグラフ、表などを効果的に使うと、文字だけの説明よりも格段に分かりやすくなります。 例えば、アンケート結果を円グラフで示したり、数値の変化を折れ線グラフで示したりすると、視覚的に理解しやすくなります。 自分の意見や考えを書く場合は、「このデータから〇〇ということが考えられる」のように、事実と意見を区別して書くことが重要です。
結論(まとめ)の書き方:分かったことや感想
結論は、レポートの締めくくりの部分です。 ここでは、本論で述べてきた内容を簡潔にまとめ、レポート全体を通して何が分かったのかを明確に示します。 本論で書いたことをだらだらと繰り返すのではなく、要点を絞って記述することが大切です。
まず、研究の結果から導き出された結論を述べます。 序論で提示した問いに対する「答え」をここで示す形になります。次に、研究を通しての感想や、新たに生まれた疑問、そして今後の課題などを書きます。 例えば、「今回の調査で家庭での食品ロスを減らす工夫は分かったが、今後は地域全体で取り組む方法についても調べてみたい」というように、次に繋がる視点を示すと、より深みのあるレポートになります。 結論は、レポート全体のまとめとして、自分の学びや成長が伝わるように書きましょう。
【中学生向け】手書きレポートの書き方と見やすくするコツ
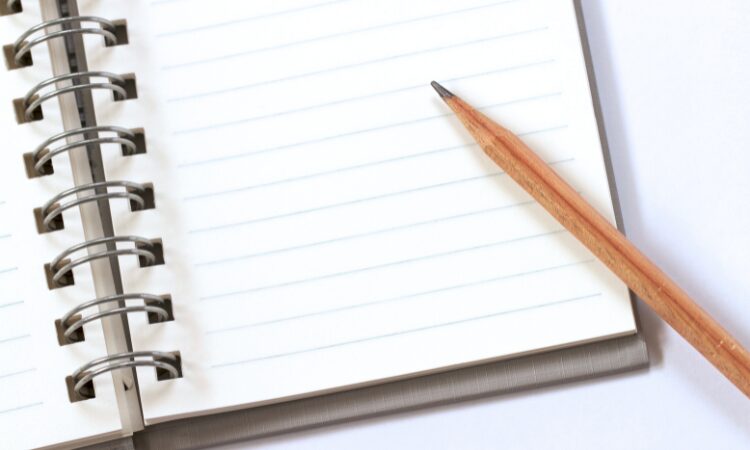
手書きのレポートは、パソコンで作るレポートとは違い、書く人の個性や丁寧さが見えやすいという特徴があります。だからこそ、少しの工夫で、ぐっと見やすく、評価の高いレポートに仕上げることができます。ここでは、中学生のみなさんがすぐに実践できる、手書きレポートをきれいに見せるコツを紹介します。
読みやすい文字で丁寧に書く
手書きレポートで最も大切なのは、読みやすい文字で丁寧に書くことです。 字の上手い下手は関係ありません。一字一字、心を込めて書くことを意識しましょう。文字の大きさや形をそろえると、全体的に整った印象になります。 また、文字と文字の間や、行と行の間を少し広めにとると、ゆったりとして読みやすくなります。
ぎっしり詰めて書くよりも、適度な余白を意識することが、見やすいレポートへの第一歩です。 筆記用具は、HB以上の濃い鉛筆やシャープペンシル、または黒のボールペンがおすすめです。 薄い文字は読みにくいので、しっかりとした筆圧で書くようにしましょう。
図やグラフ、写真を使って分かりやすく
レポートの内容をより分かりやすく伝えるためには、図やグラフ、写真を活用するのが非常に効果的です。 例えば、アンケートの結果を円グラフにしたり、数値の移り変わりを折れ線グラフにしたりすると、文字だけで説明するよりも、一目で内容を理解してもらえます。 グラフや図を手書きする際は、必ず定規を使って線を引き、丁寧に描きましょう。色鉛筆などを使って分かりやすく色分けするのも良い方法です。
観察記録や現地調査のレポートであれば、写真を撮って貼り付けるのもおすすめです。 写真を貼る際は、のりでしっかりと貼り付け、写真の下には「(図1)〇〇の様子」といったように、何の写真なのかを説明するキャプション(説明文)を必ず入れましょう。 こうした視覚的な要素を取り入れることで、レポートが華やかになり、読み手の理解を助けることができます。
見出しや箇条書きを活用する
長い文章が続くと、読み手はどこが重要なのか分かりにくくなってしまいます。そこで活用したいのが、見出しと箇条書きです。本論部分をいくつかのパートに分ける際に、「1. 〇〇について」「2. △△の原因」のように見出しをつけると、話の区切りが明確になり、内容が整理されて見えます。 見出しの文字を少し大きくしたり、アンダーラインを引いたりして、本文と区別がつくように工夫しましょう。
また、いくつかの項目を並べて説明したい場合には、箇条書きを使うと非常に便利です。「・」「1. 2. 3.」などの記号を使って情報を整理することで、文章がすっきりと見やすくなります。例えば、「問題点」や「解決策」などをリストアップする際に活用すると、要点が伝わりやすくなります。
間違えたときの修正方法
手書きのレポートでは、書き間違いはつきものです。間違えたときに、どう修正するかでレポートの印象が大きく変わります。ぐちゃぐちゃに塗りつぶしてしまうと、見た目が汚くなってしまいます。
間違えた箇所を修正する際は、定規を使って二重線を引いて消すのが基本的なルールです。 その上で、消した箇所の上や横の余白に正しい文字を書き込みます。修正テープや修正液を使っても良い場合がありますが、学校の先生によっては使用を認めていないこともあるので、事前に確認しておくと安心です。もし修正箇所が多くなってしまった場合は、面倒でも新しい用紙に書き直す方が、最終的にきれいなレポートに仕上がります。 丁寧に修正することで、作成者の誠実な態度も伝わります。
レポートの書き方で差がつく!情報の集め方とまとめ方

優れたレポートを作成するためには、その土台となる「情報」が非常に重要です。信頼できる情報を効率的に集め、それを分かりやすく整理する能力は、レポートの質を大きく左右します。ここでは、レポート作成に役立つ情報の探し方と、集めた情報を効果的にまとめるためのメモの取り方について解説します。
本や新聞で信頼できる情報を探す
レポートに書く内容は、正確で信頼できる情報に基づいている必要があります。そのために最も適した情報源の一つが、本や新聞です。学校の図書館や地域の公共図書館には、さまざまなテーマに関する本がそろっています。 図書館の司書さんに相談すれば、テーマに合った本を探す手伝いをしてもらえます。
本は、専門家によって書かれ、内容がチェックされているため、インターネットの情報よりも信頼性が高い場合が多いです。また、新聞は、最新の出来事や社会問題について知るのに役立ちます。特に、社説や解説記事は、物事を多角的に見る視点を養うのに役立つでしょう。調べ学習の際は、まずは図書館に足を運び、関連する本や新聞記事を探してみることから始めるのがおすすめです。
インターネットで情報を探すときの注意点
インターネットは、手軽に膨大な情報を得られる便利なツールです。 しかし、インターネット上の情報には、不正確なものや個人の意見に過ぎないものも多く含まれているため、注意が必要です。
インターネットで情報を探す際は、その情報の発信元がどこなのかを必ず確認しましょう。官公庁(〇〇省など)や、大学・研究機関、信頼できる報道機関のウェブサイトが出している情報は、信頼性が高いと言えます。 個人のブログや匿名の掲示板、誰でも編集できるタイプのオンライン百科事典などの情報は、参考程度にとどめ、鵜呑みにしないようにしましょう。また、複数のサイトを見比べて、同じ内容が書かれているかを確認することも、情報の信頼性を判断する上で重要です。
集めた情報を整理するメモの取り方
本やインターネットで集めた情報を、ただノートに書き写すだけでは、後でレポートにまとめるのが大変です。情報を効率的に整理するために、メモの取り方を工夫しましょう。
情報をメモする際は、後で参考文献として記載できるように、必ず出典を記録しておくことが重要です。 本の場合は「書名、著者名、出版社名、発行年、参考にしたページ」、ウェブサイトの場合は「サイト名、URL、アクセスした年月日」をメモしておきましょう。
メモを取る方法としては、情報をカードに書き出す「カード式」や、テーマに関連するキーワードを線で結んでいく「マインドマップ」などがあります。また、ノートに見開きで左ページに調べたこと(事実)、右ページにそれに対する自分の考えや疑問(意見)を書き分ける方法も、頭の中を整理するのに役立ちます。自分に合った方法で情報を整理し、レポートの構成を考えながらまとめていきましょう。
これで完璧!提出前の最終チェックリスト【手書き編】

時間をかけて一生懸命書いたレポートも、最後の詰めが甘いと評価が下がってしまうことがあります。提出する前には、必ず見直しを行い、完璧な状態で提出するように心がけましょう。ここでは、手書きレポートを提出する前に、最低限チェックしておきたい3つのポイントをリストアップしました。
誤字脱字はないか声に出して読む
レポートを書き終えたら、まずは誤字脱字がないか、文章がおかしくないかを確認しましょう。自分では完璧に書いたつもりでも、意外な間違いが隠れているものです。
チェックする際に効果的なのが、「声に出して読んでみる」ことです。黙読しているだけでは気づきにくい、文のリズムの悪さや、助詞(「てにをは」)の間違い、読点の打ち忘れなどを見つけやすくなります。また、一度時間を置いてから読み直したり、家族や友達に読んでもらって、分かりにくい部分がないか意見を聞いたりするのも良い方法です。客観的な視点を取り入れることで、より完成度の高いレポートになります。
表紙の書き方と全体の整え方
レポートの内容はもちろん大切ですが、見た目の第一印象も重要です。レポートの「顔」となる表紙をきちんと作成しましょう。
表紙には、一般的に以下の項目を記載します。
・ 提出日
・ 学校名、学年、組、氏名
これらの情報を、バランス良く配置します。タイトルは一番大きく、中央に書くと見栄えが良くなります。
また、全てのページにページ番号を振るのを忘れないようにしましょう。 通常は、ページの下部中央や右下に記載します。複数枚になる場合は、左上をホッチキスで1か所留めてまとめます。 クリップで留めたり、クリアファイルに入れたりせず、指示された形式で提出しましょう。 用紙にシワや汚れがないか、インクのかすれがないかなど、全体の清潔感も最後に確認します。
参考文献の書き忘れはないか確認しよう
レポート作成で参考にした本やウェブサイトがある場合は、その情報を「参考文献リスト」としてレポートの最後に必ず記載しなければなりません。 これは、レポートの信頼性を示すと同時に、情報を参考にさせてもらった著者への敬意を示すための大切なルールです。
参考文献の書き方には決まった形式があります。学校で特に指定がない場合は、以下のように記載するのが一般的です。
・ 本の場合:著者名『書名』出版社名、発行年
・ ウェブサイトの場合:サイト名、URL、アクセスした年月日
参考にした資料は、情報収集の段階で正確にメモしておき、最後にリストとしてまとめるのを忘れないようにしましょう。 参考文献をきちんと明記することで、レポートの説得力が増し、丁寧な作成態度をアピールすることができます。
まとめ:中学生でもできる!手書きレポートの書き方をマスターしよう

この記事では、中学生のみなさんに向けて、手書きでのレポートの書き方を、準備から構成、清書のコツ、そして提出前のチェックポイントまで、順を追って解説しました。
レポート作成は、最初は難しく感じるかもしれませんが、一つひとつのステップを丁寧に進めていけば、誰でも必ず分かりやすいレポートを完成させることができます。大切なのは、自分が何に興味を持ち、何を伝えたいのかを明確にすること、そして、読み手のことを考えて、丁寧な文字と分かりやすい構成を心がけることです。今回紹介したポイントを参考に、ぜひ自信を持ってレポート作成に取り組んでみてください。




コメント