友人や先輩から大事な応援演説を頼まれたけど、「何から書けばいいかわからない…」「どうすれば候補者の魅力が伝わるんだろう?」と悩んでいませんか。応援演説は、候補者の人柄や熱意をみんなに伝え、投票につなげるための大切な役割を担っています。
しかし、いざ書こうとすると、構成や言葉選びで手が止まってしまいますよね。この記事では、そんな高校生のあなたのために、応援演説の基本的な書き方から、聞いている人の心をぐっと掴むためのコツまで、やさしく解説します。生徒会選挙や部活動の大会など、さまざまな場面で使える具体的な例文も紹介するので、ぜひ参考にしてください。この記事を読めば、自信を持って応援演説に臨めるようになり、大切な仲間の力になれるはずです。
応援演説の基本的な書き方【高校生向け構成テンプレート】

応援演説を成功させるためには、まず基本的な構成を理解することが大切です。いきなり書き始めるのではなく、話の流れを組み立てることで、候補者の魅力がより伝わりやすくなります。ここでは、高校生が応援演説の原稿を作る際に役立つ、基本的な構成と思いを伝えるためのポイントを解説します。
応援演説の役割とは?目的を理解しよう
応援演説の最も大切な役割は、第三者の視点から候補者の魅力を伝えることです。 候補者本人が自分の長所をアピールするのとは違い、友人や仲間であるあなたが語ることで、その言葉に客観性と信頼性が生まれます。聞いている生徒たちも「友達が言うなら本当なんだろうな」と、候補者の人柄をより深く理解してくれるでしょう。
目的は、ただ候補者を褒めることではありません。具体的なエピソードを交えながら、「なぜこの人が学校にとって必要なのか」「当選したらどんな良い変化が期待できるのか」を伝え、聴衆の共感を得て、最終的に投票行動につなげることがゴールです。 あなたの言葉が、候補者の未来を左右する力を持っているのです。
これで迷わない!基本の三部構成(序論・本論・結論)
どんなスピーチにも基本の型があるように、応援演説も「序論(はじめ)」「本論(なか)」「結論(おわり)」の三部構成で考えると、スムーズに書き進めることができます。
- 序論(はじめ): 自己紹介と、応援する候補者の紹介をします。ここで聴衆の関心を引きつけ、話を聞く姿勢を作ってもらうことが重要です。
- 本論(なか): 演説の核となる部分です。候補者の具体的なエピソードを交えながら、その人の長所や学校への思い、当選後のビジョンなどを語ります。
- 結論(おわり): これまでの話をまとめ、最も伝えたいメッセージを改めて強調します。最後に、候補者への投票を力強く呼びかけて締めくくります。
この3つの流れを意識するだけで、まとまりのある、聞きやすい演説になります。
【序論】聴衆の心を開く「つかみ」の作り方
演説の第一印象は、序論の「つかみ」で決まります。まずは、自分が誰で、誰を応援するためにこの場に立っているのかを明確に伝えましょう。
「皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介にあずかりました、〇年〇組の△△です。私が応援するのは、生徒会長に立候補した□□くんです」というように、ハキハキと聞き取りやすい声で自己紹介を始めます。
さらに、候補者との関係性をひと言加えると、話に親近感が湧きます。「□□くんとは、同じサッカー部の仲間で、毎日一緒に汗を流しています」のように、簡単な一言で構いません。少しユーモアを交えて、「彼のすごいところは…と話し始めると長くなるので、今日は3つだけお話しさせてください!」といった形で、聴衆の興味を引く工夫も効果的です。
【本論】候補者の魅力を伝えるエピソードの見つけ方
本論では、候補者の素晴らしい点を具体的に伝えていきます。 ただ「優しい人です」「リーダーシップがあります」と長所を並べるだけでは、聞き手の心には響きません。 その長所を裏付ける具体的なエピソードを語ることが非常に重要です。
例えば、「リーダーシップがある」と伝えたいなら、「文化祭の準備で意見がまとまらなかった時、□□くんは各クラスの意見を丁寧に聞き、それぞれの良いところを組み合わせた新しい企画を提案してくれました。彼の行動力のおかげで、私たちのクラスは最高の展示を作り上げることができました」というように、情景が目に浮かぶような話を盛り込みましょう。
候補者の人柄(責任感、行動力、優しさなど)、これまでの実績(委員会活動、ボランティア経験など)、そして候補者に期待することを明確に伝えることで、説得力が増します。
【結論】印象に残る締め方と力強いメッセージ
結論は、演説全体の印象を決定づける大切な部分です。本論で伝えた候補者の魅力を簡潔にまとめ、「だからこそ、□□くんは私たちの学校に必要です」と力強く訴えかけましょう。
そして、候補者が当選したらどんな未来が待っているのか、ポジティブなビジョンを共有します。 「□□くんなら、きっと私たちの学校生活をより楽しく、充実したものに変えてくれます」 というように、聞いている人たちにワクワクするような期待感を持たせることがポイントです。
最後は、感謝の言葉と投票のお願いで締めくくります。「ご清聴ありがとうございました。皆さんの貴重な一票を、ぜひ□□くんに、□□□□によろしくお願いいたします!」と、候補者の名前をはっきりと伝え、深くお辞儀をすることで、誠実な気持ちが伝わります。
【高校生向け】シーン別!応援演説で使える例文集

ここでは、高校生活の様々な場面で使える応援演説の例文を紹介します。生徒会選挙、体育祭・文化祭、部活動の大会という3つのシーンを想定しました。基本的な構成は同じですが、場面に合わせて言葉の選び方や強調するポイントを変えるのがコツです。自分の言葉でアレンジして使ってみてください。
生徒会選挙での応援演説例文
生徒会選挙では、候補者が学校全体をより良くしてくれるという期待感を抱かせることが重要です。真面目さだけでなく、親しみやすさもアピールしましょう。
【例文】
皆さん、こんにちは。
〇年〇組の△△です。私が今回、生徒会書記に立候補した、□□さんの応援演説をさせていただきます。
□□さんと私は、1年生の時から同じクラスで、いつも彼女の行動力に驚かされてきました。特に印象に残っているのが、去年の文化祭準備のことです。私たちのクラスは、なかなか出し物の内容が決まらず、雰囲気が悪くなりかけたことがありました。そんな時、最初に動いたのが□□さんでした。「みんなの意見が違うのは当たり前だよ。まずは、どんな学校行事にしたいか、小さなことでもいいから全部出してみよう」と、彼女はホワイトボードを手に全員に声をかけてくれたのです。
彼女は、目立つタイプではないかもしれません。しかし、誰もが意見を言いやすい空気を作り、一人ひとりの言葉に真剣に耳を傾けることができます。そして、集まった意見を丁寧に整理し、みんなが納得できる結論へと導いてくれました。この「聞く力」と「まとめる力」こそ、全校生徒の意見を吸い上げるべき生徒会書記に最も必要な力だと、私は確信しています。
もし□□さんが書記になったら、これまで以上に生徒の声が学校運営に反映されるでしょう。彼女なら、私たちの「もっとこうだったらいいのに」という小さな声を拾い上げ、学校をより良くするための大きな力に変えてくれるはずです。
皆さん、どうか彼女の誠実さと行動力に、皆さんの貴重な一票を託してください。書記候補、□□さんを、どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
体育祭・文化祭での応援演説例文
体育祭や文化祭では、イベントを盛り上げる団長や実行委員長などを応援する場面が考えられます。一体感や士気を高めるような、熱意のこもった言葉が効果的です。
【例文】
赤組の皆さん、こんにちは!
応援団の△△です。いよいよ体育祭が始まりますが、みんな、盛り上がる準備はできていますか!
私が応援するのは、ご存知、我らが赤組団長、□□くんです!
彼が団長に決まってから、私たちは毎日、放課後遅くまで応援の練習を重ねてきました。正直、大変なこともありました。動きがなかなか揃わなかったり、声がかれてしまったり。でも、□□くんは一度も弱音を吐きませんでした。一番大きな声を出し、一番汗を流し、誰よりも先に練習に来て、一番最後まで残って片付けをする。そんな彼の背中を見て、私たちは「この人についていけば、絶対に最高の体育祭になる」と確信しました。
彼は、私たち一人ひとりのことを本当によく見てくれています。「その振り付け、すごく良くなったな!」「声、昨日より出てるぞ!」彼にかけられた一言で、どれだけ多くの仲間が勇気づけられたことか分かりません。彼のリーダーシップは、決して力ずくで引っ張るものではなく、仲間の心に火をつけ、同じ方向を向かせてくれる太陽のような力です。
今日、この場所にいる赤組の仲間たち、そしてライバルである白組の皆さん。最高の体育祭にする準備は万端です。□□団長を先頭に、私たち赤組は、正々堂々、最後まで全力で戦い抜くことを誓います!
皆さん、□□団長に、そして私たち赤組に、熱い熱い声援をよろしくお願いします!赤組、優勝するぞー!
部活動の大会・壮行会での応援演説例文
部活動の壮行会などでは、選手のこれまでの努力を称え、大会での活躍を祈る気持ちを伝えます。選手たちが自信を持って本番に臨めるように、力強く背中を押してあげる言葉を選びましょう。
【例文】
選手の皆さん、そして全校生徒の皆さん、こんにちは。
生徒会を代表しまして、△△です。
いよいよ今週末、〇〇部の皆さんは、△△大会に出場されます。この日を迎えるまで、選手の皆さんがどれほどの努力を重ねてきたか、私たちは知っています。
朝早くから始まる朝練、日が暮れても続く厳しい練習。悔し涙を流した日も、仲間と励まし合った日もあったと思います。特に、キャプテンの□□さん。あなたは、誰よりもチームのことを考え、時には厳しい言葉で、そして時には誰よりも温かい言葉でチームをまとめてきました。あなたのその強い責任感と仲間への深い愛情が、このチームをここまで強くしたのだと、誰もが感じています。
皆さんが練習に打ち込む姿は、私たち全校生徒にとっても大きな誇りであり、勇気の源です。皆さんのひたむきな努力は、必ず本番で大きな力となるはずです。
大会では、練習の成果を存分に発揮し、これまで支えてくれた仲間、先生、そして家族への感謝の気持ちを胸に、一戦一戦、悔いのないプレーをしてきてください。学校から、私たち全員が皆さんの勝利を信じて、精一杯の応援を送ります。
頑張れ、〇〇部!皆さんの健闘を心から祈っています!
心を掴む!応援演説の書き方のコツ【高校生編】

構成や例文を理解した上で、さらに聴衆の心を掴むためのワンランク上のコツを紹介します。ありきたりな応援演説で終わらせないために、少しの工夫で候補者の魅力は何倍にも輝きます。あなた自身の言葉で、思いを伝えてみましょう。
具体的なエピソードで人柄を伝えよう
「優しい」「頼りになる」といった言葉だけでは、候補者の本当の魅力は伝わりません。 聞き手が「なるほど、確かにそういう人だな」と納得できるような、具体的なエピソードを話すことが何よりも大切です。
例えば、「彼は優しいです」と言う代わりに、「私が課題のことで悩んで落ち込んでいた時、彼は自分のことのように親身になって相談に乗り、一緒に解決策を考えてくれました。そのおかげで、私は諦めずに課題を提出することができました」と話す方が、人柄が鮮明に伝わります。
候補者と一緒に過ごした学校生活の中での出来事を思い出してみてください。文化祭や体育祭、普段の授業や休み時間など、候補者の人柄が表れた瞬間が必ずあるはずです。そのエピソードこそが、あなたの演説をオリジナルで説得力のあるものにしてくれます。
ポジティブな言葉選びを意識する
応援演説は、候補者の未来を応援し、学校全体を明るい方向へ導くためのスピーチです。そのため、使う言葉はポジティブなものを心がけましょう。
「〜が足りないから、彼が必要です」というような否定的な表現よりも、「〜という彼の素晴らしい力で、学校はもっと良くなります」といった肯定的な表現の方が、聞いている人に希望や期待感を与えます。
候補者が当選することで、学校生活がどれだけ楽しく、素晴らしいものになるかを語ることで、聴衆は「この人に投票してみたい」と感じるようになります。演説全体が、前向きで明るい雰囲気に包まれるように意識してみてください。
自分の言葉で語ることの重要性
インターネットや本で素晴らしい例文を見つけると、ついそのまま使いたくなるかもしれません。しかし、最も人の心を動かすのは、あなた自身の正直な言葉です。
なぜ、あなたがその人を応援したいと思ったのか。その人のどんなところに魅力を感じているのか。少し不器用でも、飾らない自分の言葉で語ることで、スピーチに熱意と誠実さが宿ります。
「私が彼を推薦する理由は、彼の持つ底抜けの明るさです」など、あなただけが知っている候補者の魅力を、あなたの視点で語りましょう。その熱意は必ず聴衆に伝わり、強い共感を生むはずです。
短く、分かりやすい言葉で伝える工夫
応援演説は、全校生徒など多くの人が聞くものです。難しい言葉や回りくどい表現は避け、誰にでも理解できる短く、分かりやすい言葉で話すことが大切です。
一つの文が長くなりすぎないように、「〜ですが、〜なので、〜です」と続けるのではなく、「〜です。なぜなら、〜だからです。」のように、適度に区切ることを意識しましょう。
また、演説の時間は限られています。 アピールしたいポイントをいくつも詰め込みすぎると、結局何も印象に残りません。 候補者の魅力を3つ程度に絞って伝えるなど、要点を明確にすることが、聞き手の記憶に残る演説にするコツです。
高校生が応援演説でやってはいけないNGな書き方
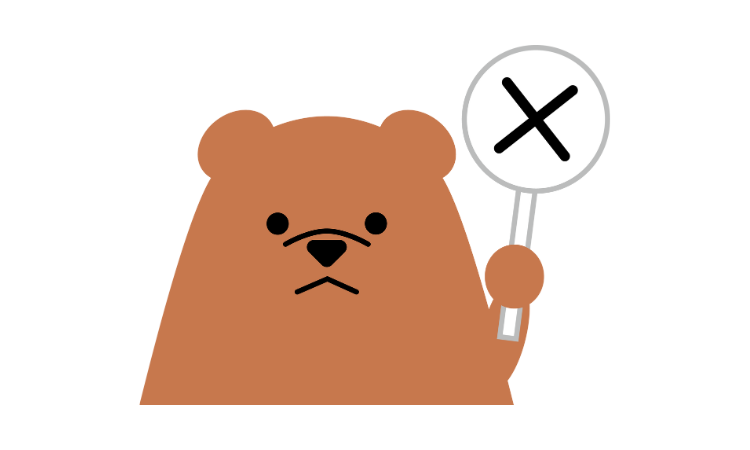
候補者を当選させたいという熱意が空回りして、逆効果になってしまうこともあります。応援演説で絶対に避けるべきNGな書き方や表現を知っておくことで、誰かを傷つけることなく、正々堂々と候補者の魅力をアピールできます。しっかりと確認しておきましょう。
他の候補者を批判・誹謗中傷する
応援演説の目的は、自分が応援する候補者の素晴らしさを伝えることです。そのために、他の候補者を貶めたり、批判したりするような発言は絶対にやめましょう。
「〇〇さんにはできないけれど、□□くんならできます」といった比較や、「前の生徒会は〜だった」のような過去の批判も避けるべきです。他の人を下げることで自分を上げようとする姿勢は、聞いている人に不快感を与え、応援している候補者自身の印象まで悪くしてしまいます。
スポーツマンシップに則り、あくまで自分たちが目指すポジティブな未来を語ることに集中しましょう。正々堂々とした態度こそが、多くの生徒の信頼と共感を得るための第一歩です。
抽象的で中身のない話をする
「□□さんは、とても素晴らしい人です。リーダーシップがあり、誰にでも優しいです。彼が生徒会長になれば、学校はもっと良くなるでしょう。だから、彼に投票してください」
このような演説を聞いて、あなたはどう感じますか?おそらく、具体的に何が素晴らしいのか全く伝わらず、印象に残りませんよね。これは、抽象的な言葉ばかりを並べた、中身のない話の典型例です。
前述の通り、具体的なエピソードが伴わない長所の羅列は、聞き手の心に響きません。 なぜリーダーシップがあると言えるのか、どんな行動を見て優しいと感じたのか、その根拠となる事実を語ることが不可欠です。あなたの演説が、ただの綺麗事の繰り返しになっていないか、原稿を書きながら常に確認しましょう。
長すぎるスピーチは逆効果
応援したい気持ちが強いほど、あれもこれもと多くのことを話したくなるものです。しかし、演説が長すぎると、聴衆の集中力は途切れてしまいます。 人が集中して話を聞ける時間は、それほど長くありません。
学校によって演説の持ち時間は決められている場合が多いですが、もし規定がなくても、簡潔にまとめることを意識しましょう。 時間内に収めるために早口で話すのも逆効果です。
伝えたいことを欲張らず、最も重要なポイントに絞り込む勇気も必要です。短い時間でいかに強い印象を残せるかが、スピーチの腕の見せ所と言えるでしょう。
嘘や大げさな表現は避ける
候補者をよく見せたいからといって、事実ではないエピソードを話したり、大げさに話を盛ったりするのは絶対にNGです。
例えば、クラスの話し合いをまとめた経験を「学校全体を動かすほどのリーダーシップを発揮した」のように過度に表現すると、かえって話の信憑性が失われます。また、後から嘘だと分かった場合、候補者だけでなく、応援したあなた自身の信頼も大きく損なうことになります。
等身大の候補者の姿を、誠実に伝えることが最も大切です。少し地味に思えるようなエピソードでも、そこに真実の心がこもっていれば、必ず人の心を動かすことができます。
応援演説の書き方から本番まで!高校生が成功するための準備

素晴らしい原稿が書けても、本番でそれを伝えきれなければ意味がありません。人前で話すのは誰でも緊張するものです。しかし、しっかりとした準備をすれば、自信を持って堂々とスピーチすることができます。ここでは、原稿作成後から本番までの具体的な準備について解説します。
原稿の作成と声に出して読む練習
原稿が完成したら、まずは何度も声に出して読んでみましょう。黙読しているだけでは気づかなかった、言いにくい言葉のリズムや、文章の不自然なつながりが見つかるはずです。
実際に声に出すことで、文章が自分の言葉として馴染んできます。また、時間を計りながら読むことで、規定の時間内に収まるかを確認することもできます。もし時間がオーバーしてしまう場合は、どこを削るべきかを検討しましょう。
練習中は、家族や友人に聞いてもらうのも非常に効果的です。客観的な意見をもらうことで、自分では気づかなかった改善点が見つかります。「声が小さい」「早口になっている」「ここが分かりにくい」といったフィードバックを素直に受け止め、より伝わるスピーチを目指しましょう。
時間配分を意識した練習方法
スピーチには、聞き手を引き込むための「間(ま)」が重要です。しかし、緊張するとつい早口になりがちです。時間配分を意識した練習を取り入れましょう。
例えば、3分間のスピーチなら、「序論で30秒、本論で2分、結論で30秒」というように、大まかな時間配分を決めます。そして、ストップウォッチを使いながら、その時間配分通りに話す練習を繰り返します。
特に、強調したいメッセージの前には、少し間を置くと効果的です。聴衆が言葉を理解し、心に刻む時間を与えることができます。こうしたテクニックも、練習を重ねることで自然に身についていきます。
堂々と話すための姿勢と視線
本番では、話す内容だけでなく、あなたの立ち姿や表情、視線も聴衆にメッセージを伝えます。自信がなさそうに下を向いて話していると、どんなに良い内容でも説得力が半減してしまいます。
練習の時から、背筋を伸ばし、少し顎を引いて、堂々とした姿勢を意識しましょう。鏡の前で練習するのもおすすめです。自分の姿を確認しながら、最も自信を持って見える立ち方を探してみてください。
視線は、なるべく会場全体を見渡すように心がけます。 一点だけを見つめるのではなく、聴衆一人ひとりと目を合わせるような気持ちで、ゆっくりと視線を動かすと、会場に一体感が生まれます。 「皆さんに語りかけていますよ」という気持ちが伝わり、聴衆もあなたの話に引き込まれやすくなります。
緊張を和らげるためのリラックス法
「人前に立つと頭が真っ白になる…」という人も多いでしょう。緊張するのは当たり前のことです。大切なのは、緊張とどう向き合うかです。
本番前には、深呼吸を試してみてください。ゆっくりと鼻から息を吸い、口から時間をかけて吐き出す。これを数回繰り返すだけで、心拍数が落ち着き、リラックス効果が得られます。
また、「うまく話そう」と完璧を目指しすぎないことも大切です。「候補者のために、自分の思いを伝えよう」という気持ちに集中すれば、自然と言葉が出てくるはずです。もし途中で言葉に詰まっても、焦らずに「えーと」と正直に言って、少し間を置いても大丈夫。誠実な態度は、必ず聴衆に好意的に受け止められます。
まとめ:高校生の応援演説、書き方のポイントを押さえて大切な仲間を後押ししよう

この記事では、高校生が応援演説の原稿を書く際の構成やコツ、そして具体的な例文を紹介しました。応援演説で最も大切なのは、候補者の魅力を自分の言葉で、具体的なエピソードを交えて伝えることです。 ただ褒めるのではなく、「なぜこの人が学校に必要なのか」を熱意を持って語ることで、聞いている人の心を動かすことができます。構成の基本を押さえ、ポジティブな言葉を選び、何度も練習を重ねれば、きっと素晴らしい応援演説ができるはずです。あなたの言葉で、大切な仲間を力強く後押ししてあげてください。




コメント