高校生になると、学校の課題や進路選択の場面で「将来の夢」についての作文を書く機会が増えます。しかし、いざ書こうとすると「何を書けばいいのかわからない」「そもそも将来の夢なんてまだ決まっていない」と悩んでしまう人も少なくないでしょう。
将来の夢についての作文は、単に文章力を示すだけのものではありません。自分自身の内面と向き合い、興味や価値観を探求し、未来について考える貴重な機会となります。 先生や入試の担当者は、作文を通してあなたがどんなことに興味を持ち、物事をどう捉え、未来をどう描こうとしているのかを知ろうとしています。
この記事では、将来の夢の作文に悩む高校生のために、基本的な書き方のステップから、評価される構成、具体的な職業別の例文まで、やさしくわかりやすく解説していきます。また、「夢がまだない」という人向けの書き方のヒントも紹介しますので、ぜひ参考にして、あなたらしい将来の夢の作文を完成させてください。
将来の夢の作文、何から始める?【高校生向け基本ステップ】
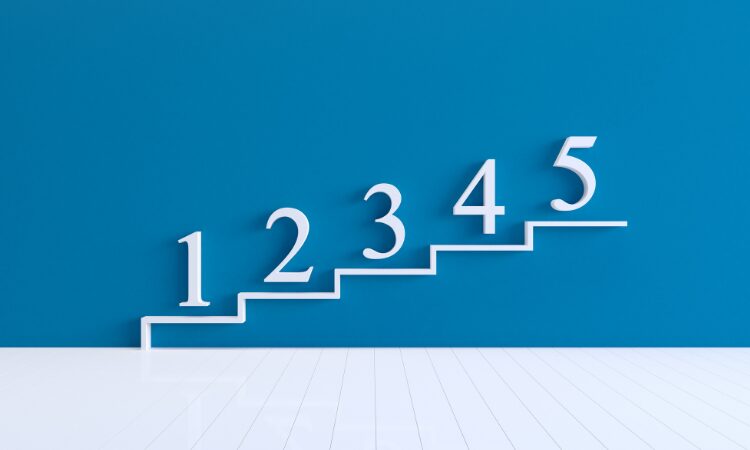
将来の夢の作文を書き始める前に、いくつか準備をしておくとスムーズに進みます。まずは自分自身と向き合い、書きたいことの材料を集めることから始めましょう。
まずは自分と向き合う「自己分析」
将来の夢について考えることは、自分自身を深く知ることから始まります。いきなり「夢は何か?」と問われても、すぐに答えられないのは自然なことです。まずは、自分の好きなこと、得意なこと、興味があること、大切にしている価値観などを紙に書き出してみましょう。
例えば、「友達と話しているときが楽しい」「黙々と絵を描くのが好き」「困っている人を助けると嬉しい気持ちになる」といった些細なことでも構いません。また、過去の体験を振り返り、「どんな時に心を動かされたか」「どんなことに感動したか」を思い出すのも良い方法です。 こうした自己分析を通して、自分の興味の方向性や、どんなことにやりがいを感じるのかが見えてきます。それが、将来の夢のヒントになるはずです。
将来の夢に関する情報を集める「リサーチ」
自己分析で興味のある分野が見えてきたら、次はその分野について詳しく調べてみましょう。例えば「子どもと関わる仕事がしたい」と思ったら、保育士、幼稚園教諭、小学校の先生、ベビーシッター、小児科の看護師など、様々な職業があります。
それぞれの仕事が具体的にどんな内容なのか、どんなスキルや資格が必要なのか、どんな人が向いているのかをインターネットや書籍で調べてみてください。大学や専門学校のウェブサイトで、関連する学部や学科の情報を集めるのも有効です。憧れの職業に就いている人のインタビュー記事を読んだり、実際に話を聞く機会があれば、より具体的なイメージが湧き、作文に深みが増すでしょう。このリサーチの過程で、漠然としていた興味が、より具体的な目標へと変わっていくこともあります。
作文の骨組みを作る「構成案の作成」
書きたいことの材料が集まったら、いきなり文章を書き始めるのではなく、まずは作文全体の設計図となる「構成案」を作成しましょう。 構成案を作ることで、話の筋が通り、論理的で分かりやすい文章になります。
一般的な将来の夢の作文は、「結論(私の夢は〇〇です)→夢を持ったきっかけ(理由・エピソード)→夢を実現するための努力(具体的な行動計画)→将来の展望(夢を叶えて社会にどう貢献したいか)」という流れで構成されます。
まず、それぞれの項目で何を書くのかを箇条書きでメモしていきます。例えば、「きっかけ」の項目では「中学時代の職場体験で看護師の優しさに触れたこと」、「努力」の項目では「理系科目の勉強に力を入れる」「看護体験に参加する」といった具体的な内容を書き出します。この骨組みに沿って文章を作成していくことで、伝えたいことが明確になり、まとまりのある作文に仕上げることができます。
【高校生必見】将来の夢の作文で評価される構成とは?

作文には基本的な「型」があります。この型に沿って書くことで、読み手にあなたの考えがスムーズに伝わり、説得力のある文章になります。ここでは、将来の夢の作文で一般的に用いられる、評価されやすい4部構成を紹介します。
結論:将来の夢は何かを明確に(序論)
作文の冒頭では、まず「私の将来の夢は〇〇になることです」と、結論をはっきりと述べましょう。 最初に夢を明確に提示することで、読み手はこれから何について書かれるのかを理解し、スムーズに文章を読み進めることができます。
ここでのポイントは、単に職業名を挙げるだけでなく、「なぜそうなりたいのか」に繋がるような一言を添えることです。例えば、「私の将来の夢は、患者さんの心に寄り添える看護師になることです」のように書くと、あなたの価値観や人柄が伝わり、より印象的な書き出しになります。「どのような〇〇になりたいか」という視点を加えることで、後の文章への期待感を高める効果もあります。 抽象的な表現は避け、具体的で分かりやすい言葉で自分の夢を宣言しましょう。
理由:なぜその夢を持ったのか(本論① – きっかけ)
次に、なぜその夢を持つようになったのか、そのきっかけや理由を具体的に説明します。 ここでは、あなた自身の体験談を交えて書くことが非常に重要です。個人的なエピソードは、文章にリアリティと説得力を与え、読み手の共感を呼びます。
例えば、「小学生の時に入院した際、担当の看護師さんが不安な私を励ましてくれた経験から、私も人の心を支えられる仕事がしたいと思うようになった」というように、具体的な出来事やその時に感じた気持ちを詳しく描写しましょう。また、本を読んだこと、映画を見たこと、家族や先生から影響を受けたことなど、夢を抱くに至った背景を丁寧に説明することで、あなたの夢が単なる憧れではなく、確固たる意志に基づいていることを示すことができます。
具体例:夢を実現するために何をするか(本論② – 努力)
夢を語るだけでなく、その夢を実現するために具体的に何をしているのか、またはこれから何をしようとしているのかを示すことは、作文の説得力を大きく高める要素です。 夢への本気度を伝えるためにも、ここは非常に重要な部分です。
現在取り組んでいることとして、「夢の実現に必要な理系科目の学習に力を入れている」「地域のボランティア活動に参加して、様々な年代の人と関わる経験を積んでいる」といった具体的な行動を挙げましょう。さらに、高校卒業後の進路についても触れ、「〇〇大学の看護学部で専門知識を学びたい」というように、具体的な計画を示すと良いです。 この部分で、夢がただの空想ではなく、現実的な目標として捉えていることをアピールできます。
結論:将来どのように貢献したいか(結論)
作文の締めくくりとして、夢を実現した先に、自分が社会に対してどのように貢献したいのかという未来への展望を述べます。 これは、あなたの夢が自己満足で終わるものではなく、他者や社会との関わりの中で価値を持つものであることを示すために重要です。
例えば、「私が看護師になったら、専門知識や技術はもちろん、患者さん一人ひとりの気持ちを理解し、心身ともにサポートすることで、地域医療に貢献したいです」といった形で、自分の夢が社会に与えるポジティブな影響について語りましょう。最後に、「その日のために、これからの高校生活も一日一日を大切に過ごしていきたい」というように、改めて夢への決意を表明することで、文章全体が力強くまとまり、読み手に前向きな印象を残すことができます。
職業別!将来の夢の作文で使える例文集【高校生向け】

ここでは、高校生に人気の職業をテーマにした作文の例文をいくつか紹介します。構成や表現を参考にしながら、あなただけのエピソードを加えて、オリジナルの作文を作成してみてください。
例文①:看護師
私の将来の夢は、患者さんだけでなく、そのご家族の心にも寄り添える看護師になることです。
この夢を抱いたのは、中学生の時に祖母が入院したことがきっかけです。毎日不安そうな顔をしていた祖母でしたが、担当の看護師さんがいつも笑顔で話しかけ、祖母だけでなく私たち家族の心配事まで親身に聞いてくれました。その姿を見て、病気だけでなく人の心までケアできる看護師という仕事の素晴らしさを知り、強く憧れるようになりました。
現在、私は夢を実現するために、理科系の科目、特に生物の勉強に力を入れています。人体の仕組みを深く理解することが、適切な看護に繋がると考えているからです。また、地域の高齢者施設でボランティア活動に参加し、コミュニケーション能力を養っています。様々な方と接する中で、相手の話を丁寧に聞く「傾聴」の姿勢の大切さを学んでいます。
高校卒業後は、貴学の看護学部で高度な専門知識と実践的な技術を学びたいと考えています。そして将来的には、患者さんが安心して療養生活を送れるよう、心と身体の両面からサポートできる看護師として、地域医療に貢献していきたいです。
例文②:教師
私の将来の夢は、生徒一人ひとりの個性を引き出し、学ぶことの楽しさを伝えられる高校の数学教師になることです。
私はもともと数学が苦手でした。しかし、高校に入学して出会った先生の授業は、公式を暗記させるだけでなく、その公式が生まれた歴史的背景や、日常生活でどのように使われているかを教えてくれるものでした。先生のおかげで、数学の世界の奥深さに気づき、苦手意識は知的好奇心へと変わりました。この経験から、私もかつての自分のように、勉強に苦手意識を持つ生徒の可能性を広げる手助けがしたいと強く思うようになりました。
現在、私は数学の面白さを友人に伝えるため、休み時間に勉強会を開いています。人に教えることで、自分自身の理解がさらに深まることも実感しています。また、教育関連の書籍を読み、現代の教育が抱える課題や、生徒の主体性を引き出す指導法について学んでいます。
大学では教育学部で数学の専門知識を深めるとともに、教育心理学やカウンセリングについても学びたいと考えています。そして、生徒たちが自ら問いを立て、探求していく喜びを発見できるような授業作りができる教師になりたいです。知識を教えるだけでなく、生徒たちの成長を支え、未来への一歩を踏み出す勇気を与えられる存在になることが私の目標です。
例文③:ITエンジニア
私の将来の夢は、IT技術を用いて社会的な課題を解決するITエンジニアになることです。
この夢を持つきっかけとなったのは、コロナ禍でのオンライン授業の経験です。最初は戸惑いもありましたが、場所に縛られずに学べるITの力に大きな可能性を感じました。同時に、デジタル化から取り残されてしまう人々がいるという課題にも気づきました。この経験から、誰もがITの恩恵を受けられるような、インクルーシブ(誰一人取り残さない)な社会の実現に貢献したいと考えるようになりました。
現在、私はプログラミング言語の学習に独学で取り組んでいます。基本的なウェブサイトを作成できるようになり、自分のアイデアを形にする楽しさを感じています。また、情報処理技術者試験の勉強を通して、ITに関する体系的な知識の習得に努めています。情報系のニュースにも常にアンテナを張り、最新技術の動向を追うように心がけています。
大学では情報工学を専攻し、AIやデータサイエンスといった最先端の技術を学びたいです。将来的には、高齢者や障がいを持つ方々が、より快適に社会生活を送るためのアプリケーションやサービスを開発したいと考えています。ITの力で、人々の生活を豊かにし、より良い社会を築く一端を担えるエンジニアになることが私の目標です。
例文④:保育士
私の将来の夢は、子どもたちの豊かな感受性と個性を育むことができる保育士になることです。
私が保育士に憧れるようになったのは、近所の保育園で職場体験をさせていただいたことがきっかけです。子どもたちの純粋な好奇心や、日々成長していく姿を間近で見て、このかけがえのない時期を支える仕事に大きな魅力を感じました。特に、一人の内気な子が、私が作った折り紙をきっかけに心を開いてくれた時の喜びは、今でも忘れられません。
現在、私は夢を叶えるために、ピアノの練習に励んでいます。子どもたちと一緒に歌ったり、リズム遊びをしたりする際に役立つと考えたからです。また、絵本の読み聞かせのボランティアに参加し、子どもたちの想像力を引き出す表現方法を学んでいます。子どもたちの発達段階に関する本を読み、年齢に応じた適切な関わり方についての知識も深めています。
高校卒業後は、保育科のある大学で、子どもの心理や発達、保健について専門的に学びたいです。特に、多様性が重視される現代において、一人ひとりの子どもの背景を理解し、その子らしさを尊重できる保育士になることを目指しています。子どもたちの笑顔があふれる毎日を創り出し、健やかな成長を保護者の方々と共に見守っていけるような、信頼される保育士になりたいです。
例文⑤:公務員
私の将来の夢は、市民の声を直接聞き、地域社会の発展に貢献できる市役所の職員になることです。
私が公務員という仕事に興味を持ったのは、高校の授業で地域活性化について学んだことがきっかけです。私の住む町には、素晴らしい自然や文化があるにもかかわらず、人口減少や高齢化といった課題を抱えています。この現状を知り、生まれ育ったこの町のために何かできることはないかと考えたとき、行政の立場からまちづくりに携わる公務員の仕事に魅力を感じました。
現在、私は地域の課題をより深く理解するために、市の広報誌を隅々まで読んだり、市議会の傍聴に参加したりしています。また、地域の清掃活動やイベントに積極的に参加し、様々な年代の住民の方々と交流するよう心がけています。対話の中から、行政に対する市民の率直な意見や要望を知ることができ、大変勉強になっています。
大学では法学部や経済学部に進学し、行政に必要な法律や経済の知識を身につけたいと考えています。そして将来的には、市民と行政の架け橋となり、誰もが安心して快適に暮らせるまちづくりに貢献したいです。前例にとらわれず、新しいアイデアで地域課題の解決に挑戦できるような、創造性豊かな公務員になることが私の目標です。
「将来の夢がまだない…」高校生のための作文の書き方

「将来の夢」と聞かれても、すぐに具体的な職業が思い浮かばない人も多いはずです。しかし、心配する必要はありません。 作文は、必ずしも明確な職業について書かなければならないわけではありません。 ここでは、まだ夢が見つかっていない高校生が作文を書くためのヒントを紹介します。
興味・関心があることから広げてみる
現時点で「これだ!」という職業が見つかっていなくても、少しでも興味があることや、関心を持っていることは誰にでもあるはずです。例えば、「海外の文化に興味がある」「環境問題に関心がある」「絵を描くのが好き」といったことから、作文のテーマを広げていくことができます。
まずは、なぜそれに興味を持ったのか、そのきっかけとなった出来事を振り返ってみましょう。そして、その興味を将来どのように活かしていきたいかを考えてみます。「海外の文化が好きだから、将来は国籍の違う人々と協力して何かを成し遂げる仕事がしたい」というように、具体的な職業名ではなく、どんな分野で、どのように活躍したいかという方向性で書くのです。 このように、自分の興味を探求する過程を書くこと自体が、立派な「将来の夢」の作文になります。
憧れの人や尊敬する人をテーマにする
特定の職業にこだわらず、「こんな大人になりたい」という憧れの人物像をテーマに書くのも一つの良い方法です。 それは、歴史上の偉人かもしれませんし、身近な家族や先生、部活動の先輩かもしれません。
なぜその人に憧れるのか、その人のどんな点に魅力を感じるのかを具体的に分析してみましょう。「常に前向きで、周りの人を明るくする先輩のようになりたい」「困難な状況でも諦めずに挑戦し続けた〇〇のように、強い意志を持った人間になりたい」など、その人物像を軸にして、自分が目指す未来の姿を描いていきます。そして、そのような大人になるために、高校生活で何を学び、どんな経験を積んでいきたいかを述べることで、将来に向けた前向きな姿勢を示すことができます。
どんな大人になりたいかを考えてみる
将来の夢は、職業という「点」で考えるだけでなく、「どんな生き方をしたいか」「どんな人間になりたいか」という、より広い視点で考えることもできます。 例えば、「困っている人を助けられる、思いやりのある大人になりたい」「新しいことに挑戦し続け、生涯学び続ける大人になりたい」「家族や友人を大切にし、周りの人々を幸せにできる大人になりたい」といった、自分のあり方や価値観をテーマにすることができます。
なぜそうありたいと思うのか、その価値観を形成した経験やエピソードを交えながら説明します。そして、その理想の大人像に近づくために、日々の生活で心がけていることや、これから取り組みたいことを具体的に述べましょう。職業という形にはまらなくても、自分の人生の目標を真剣に考える姿勢は、十分に魅力的であり、読み手の心に響く作文になります。
まとめ:自分らしい将来の夢の作文を書いてみよう【高校生へのメッセージ】

この記事では、高校生が「将来の夢」の作文を書く際のポイントや構成、具体的な例文、そして夢がまだ見つからない場合の対処法について解説しました。
作文を書く上で最も大切なのは、うまい文章を書くことよりも、自分自身と正直に向き合うことです。 なぜその夢に惹かれるのか、どんな大人になりたいのか、そのために今何ができるのか。こうした問いに一つひとつ向き合うプロセスそのものが、あなたを成長させてくれます。
今回紹介した構成や例文はあくまで一つの参考に過ぎません。大切なのは、あなた自身の言葉で、あなた自身の体験や想いを綴ることです。たとえ夢がまだ漠然としていても、それを探求しようとする真摯な姿勢が伝われば、きっと素晴らしい作文になります。 この作文を書き上げる経験が、あなたの未来を考える大きな一歩となることを願っています。




コメント