「将来の夢」というテーマで作文の宿題が出たけれど、「自分にはまだ将来の夢なんてない…」と頭を抱えていませんか?実は、将来の夢がまだ決まっていない中学生は決して少なくありません。 大切なのは、焦らずに自分と向き合うことです。
この作文の目的は、必ずしも「〇〇になりたい!」という具体的な職業を発表することだけではありません。むしろ、今の自分が何に興味があり、どんなことに心を動かされるのか、そしてこれからどうなっていきたいのかを考える良い機会なのです。
この記事では、将来の夢が決まっていない中学生が、どのように作文と向き合えば良いのかを、具体的なテーマの見つけ方から構成のコツ、さらにはそのまま参考にできる作文例まで、やさしく解説していきます。この記事を読めば、白紙の原稿用紙を前に固まることなく、自分らしい作文を書くための一歩を踏み出せるはずです。
なぜ?将来の夢が決まってない中学生が多い理由

「周りの友達は夢があってすごいな…」なんて、焦りを感じてしまうこともあるかもしれません。でも、安心してください。中学生の段階で将来の夢が決まっていないのは、ごく自然なことです。 その背景にある理由を一緒に見ていきましょう。
まだ社会を知らないから
中学生のみなさんが日常的に接している大人は、主に家族や学校の先生など、限られた範囲の人たちではないでしょうか。世の中には、私たちがまだ知らない職業がたくさんあります。 例えば、テレビやインターネットで目にする華やかな仕事の裏側にも、それを支える様々な専門家がいます。
また、社会は常に変化しており、今はない新しい職業が将来生まれる可能性も大いにあります。 家と学校の往復だけでは、社会の多様な側面に触れる機会は限られてしまいます。 経験や知識がまだ少ない段階で、たくさんの選択肢の中から「これだ!」という夢を見つけるのは、むしろ難しいことなのです。だからこそ、今夢がないからといって、自分を責める必要はまったくありません。
自分の「好き」や「得意」がわからないから
「何が好き?」と聞かれても、すぐに答えられない人もいるでしょう。部活動や勉強に一生懸命取り組んでいても、それが本当に自分の「好き」や「得意」なのか、自信を持てないこともあるかもしれません。
自分の得意なことを見つけるのは、意外と難しいものです。 自分では当たり前にできることが、実は他の人から見たら「すごいね!」と言われるような特別なスキルである可能性もあります。また、様々な経験を重ねる中で、新たな「好き」が見つかることもあります。
例えば、友達に勉強を教えたときに「分かりやすい」と言われて、人に何かを伝える楽しさに気づくかもしれません。あるいは、文化祭の準備で黙々と作業をすることに、思いがけない充実感を覚えるかもしれません。このように、自分の「好き」や「得意」は、日々の生活や新しい挑戦の中に隠れていることが多いのです。
周りと比べて焦ってしまうから
「〇〇ちゃんは看護師になるって言ってたな」「〇〇くんはプログラマーを目指すらしい」といった友達の話を聞くと、「自分だけ何も決まっていない…」と不安になってしまう気持ちはよくわかります。特に、中学校では進路について考える機会が増えるため、将来の夢がないことに焦りを感じやすい時期でもあります。
しかし、夢を見つけるペースは人それぞれです。 早く決まる人もいれば、高校生や大学生、あるいは大人になってから自分のやりたいことを見つける人もたくさんいます。 他の誰かと比べる必要は全くありません。
大切なのは、周りに流されて無理に夢を決めることではなく、自分の心とじっくり向き合う時間を持つことです。焦りは視野を狭めてしまうこともあります。今は、これからたくさんの可能性が広がっている大切な時期だと捉え、自分のペースで興味のアンテナを広げていくことを意識してみましょう。
将来の夢が決まってない中学生でも書ける!作文のテーマ探し
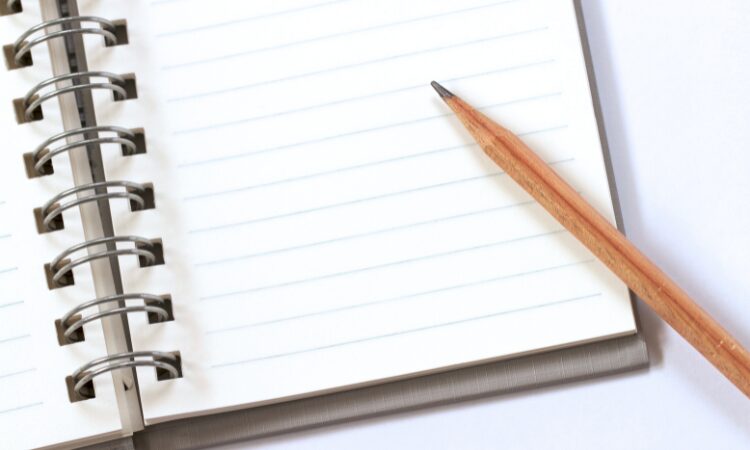
「夢がない」という事実を前に、何を書けばいいのか途方に暮れてしまいますよね。しかし、視点を少し変えるだけで、作文のテーマはたくさん見つかります。大切なのは、「職業」という枠にとらわれすぎないことです。 ここでは、将来の夢が決まっていない中学生でも書きやすいテーマ探しのヒントをご紹介します。
興味・関心があることを掘り下げてみよう
今はまだ「将来の夢」と呼べるほど大きなものではなくても、「なんとなく好き」「気になる」ということはありませんか? 例えば、「ゲームをするのが好き」「動物の動画を見るのが好き」「絵を描くのが好き」など、どんな些細なことでも構いません。その「好き」という気持ちを、少しだけ深く掘り下げてみましょう。
なぜゲームが好きなのかを考えてみると、「友達と協力して目標を達成するのが楽しいから」「作り込まれたストーリーに感動するから」といった理由が見えてくるかもしれません。そこから、「チームで何かを成し遂げる仕事」や「人を感動させる物語を作る仕事」へと興味が広がっていく可能性があります。
動物が好きなら、「なぜ好きなのか」「どんな動物に特に惹かれるのか」を考えてみましょう。「動物が安心して暮らせる環境を守りたい」という気持ちに気づけば、獣医や動物園の飼育員だけでなく、環境保護活動家や研究者といった道も見えてきます。このように、自分の興味・関心を深掘りすることで、将来やりたいことのヒントが見つかるはずです。
憧れの「人」や「生き方」をテーマにしよう
具体的な職業でなくても、「こんな人になりたい」という憧れの人物像なら、思い浮かぶ人もいるのではないでしょうか。 それは、歴史上の偉人かもしれませんし、スポーツ選手、アーティスト、あるいは身近な家族や先生かもしれません。
その人のどんなところに惹かれるのかを考えてみることが、作文のテーマになります。「困難に立ち向かう強さ」「周りの人を明るくする優しさ」「自分の信念を貫く姿勢」など、憧れる理由を具体的に言葉にしてみましょう。そして、「自分もその人のように、周りの人を助けられる人間になりたい」「失敗を恐れずに挑戦し続けられる人になりたい」といった形で、自分の目指す人物像について書いていくのです。
これは、単なる職業紹介ではなく、自分の価値観や人生の目標について考えることにつながります。 憧れの生き方をテーマにすることで、より深く自分自身を見つめ直した、オリジナリティあふれる作文になるでしょう。
どんな大人になりたいかを考えてみよう
「将来の夢」を「どんな大人になりたいか」という少し広い視点で考えてみるのも一つの方法です。 職業という具体的な形ではなく、自分のあり方やライフスタイルに焦点を当ててみましょう。
例えば、「家族との時間を大切にできる大人になりたい」「困っている人がいたら、自然に手を差し伸べられるような優しい大人になりたい」「常に新しいことを学び続ける、好奇心旺盛な大人になりたい」など、様々な理想の大人像が考えられます。
なぜそうなりたいのか、その理由を自分の経験と結びつけて書くと、より説得力のある文章になります。例えば、「いつも忙しそうだったけれど、時間を作って話を聞いてくれた両親を見て、家族を大切にする大人になりたいと思った」というように、具体的なエピソードを盛り込むと良いでしょう。どんな生き方をしたいかを考えることは、将来の進路を選択する上での大切な指針にもなります。
好きな教科や得意なことからヒントを得よう
学校の勉強の中に、将来の夢につながるヒントが隠れていることもあります。あなたが「楽しい」と感じる教科や、「これは得意かもしれない」と思える分野はありますか?
例えば、数学の問題を解くのが好きなら、論理的に物事を考えることが得意なのかもしれません。その力は、プログラマーや研究者、データ分析の仕事などで活かせる可能性があります。歴史が好きなら、過去の出来事から未来を予測したり、物事の背景を深く探求したりすることに興味があるのかもしれません。それは、ジャーナリストや学芸員、商品開発などの仕事につながるかもしれません。
「なぜその教科が好きなのか」「どんなところに面白さを感じるのか」を自己分析してみましょう。 そして、「この得意なことを、将来どのように社会で活かしていけるだろうか」と考えてみるのです。好きな教科をきっかけに、今まで知らなかった職業や学問分野に興味が湧いてくることもあります。
構成がカギ!将来の夢が決まってない中学生の作文の書き方

テーマが見つかったら、次はいよいよ作文を書き始めます。将来の夢が決まっていない場合、構成を工夫することが、説得力のある文章を書くための重要なポイントになります。 「夢がない」というマイナスの状態を、前向きな探求の物語へと変えていきましょう。ここでは、基本的な三部構成に沿った書き方のコツを紹介します。
書き出し:「今、夢がない」ことを正直に書く
作文の冒頭で、「私にはまだ、将来の夢がありません」と正直に書くことから始めるのは、とても効果的な方法です。 読んでいる先生も、「正直な生徒だな」と好印象を持つかもしれません。ただし、そこで終わってしまっては、ただの報告になってしまいます。
大切なのは、「夢がない」という現状を述べた後で、「だからこそ、これから真剣に考えていきたい」「この作文をきっかけに、自分自身と向き合ってみたい」という前向きな姿勢を示すことです。
例えば、「正直に言うと、私にはまだ『これだ』と断言できる将来の夢はありません。周りの友達が具体的な夢を語るのを聞くと、少し焦る気持ちもあります。しかし、だからこそ今、私は自分の未来についてじっくりと考えてみたいと思っています」のように書き出すことで、読者を引き込み、これからの文章への期待感を高めることができます。
本文:夢を探すための「過程」や「考え」を書く
作文の中心となる本文では、夢を見つけるための自分の考えや探求の過程を具体的に記述していきます。前の章で見つけたテーマ(興味があること、憧れの人、なりたい大人像など)をここで詳しく展開しましょう。
例えば、「興味があること」をテーマにするなら、なぜそれに興味を持ったのか、その魅力はどこにあるのか、そしてそれについて調べる中で何がわかったのか、といった探求のプロセスを書きます。「最近、宇宙に関するドキュメンタリー番組を見て、ブラックホールの謎に強く惹かれました。そこで図書館で関連する本を読んでみたところ…」というように、具体的な行動を交えて書くと、文章にリアリティが生まれます。
「憧れの人」をテーマにするなら、その人のどんな言動に心を動かされたのか、具体的なエピソードを挙げながら説明します。そして、その人のようになりたいと考えた結果、自分はこれから何を大切にしていきたいと思うようになったのか、内面の変化を丁寧に描写しましょう。この部分は、あなたがどのように自分や社会と向き合っているかを示す、作文の最も重要な部分です。
結び:これからの目標や抱負で締めくくる
作文の最後は、未来に向けた前向きな決意や抱負で締めくくります。 本文で述べた探求の過程を経て、自分がこれからどうしていきたいのかを宣言する部分です。
ここで大切なのは、壮大な夢を語る必要はないということです。「まだ具体的な職業は決められないけれど、人の役に立てるような仕事を見つけるために、まずは様々なことに挑戦してみたいです」「憧れの〇〇さんのように、周りの人を笑顔にできる人間になるために、日々の挨拶や思いやりのある行動を心がけていきたいです」といった、身近で具体的な目標を掲げましょう。
「この作文を書くことを通して、将来の夢について深く考えることができました。今はまだ探している途中ですが、自分の興味や関心を大切にしながら、一歩ずつ前に進んでいきたいと思います」のように、作文を書いたこと自体の意味づけで締めくくるのも良いでしょう。未来への希望を感じさせる、力強い結びになるはずです。
そのまま使える!将来の夢が決まってない中学生の作文例

ここまでのポイントを踏まえて、具体的な作文例を3つのパターンで紹介します。構成や表現に迷ったときの参考にしてみてください。もちろん、丸写しではなく、自分の言葉やエピソードに置き換えて、あなただけのオリジナルな作文を完成させましょう。
作文例①:興味があることを探求したい
タイトル:私の「好き」の探求
正直に言うと、今の私には「将来、絶対この職業に就きたい」という明確な夢はありません。周りの友達が看護師や教師といった具体的な夢を語るのを聞くと、少しだけ焦りを感じることもあります。しかし、この作文を書くにあたって自分自身と向き合ったとき、私には夢中になれる「好きなこと」がいくつかあることに気づきました。その一つが、物語の世界に浸ることです。
私は、小説や漫画、映画など、ジャンルを問わず物語に触れるのが大好きです。特に、登場人物の心の動きが丁寧に描かれている作品に惹かれます。なぜこれほどまでに物語が好きなのかを考えてみると、それは、自分とは違う人生を疑似体験できるからだと気づきました。物語を通して、普段の生活では味わえないような喜びや悲しみ、そして感動を知ることができます。最近読んだ歴史小説では、困難な時代を生き抜いた人々の強さに心を打たれ、自分の悩みがとても小さなものに感じられました。このように、物語は私の視野を広げ、物事を多角的に見る手助けをしてくれるのです。
まだ、この「好き」という気持ちを、将来どんな仕事に繋げていけるのかは分かりません。もしかしたら、物語を作る編集者や作家という道があるかもしれませんし、あるいは、たくさんの人に物語の魅力を伝える本屋さんや図書館の司書という仕事もあるかもしれません。今はまだ、たくさんの可能性の中から一つを選ぶことはできません。だからこそ、これから高校では文芸部に入ったり、様々なジャンルの本をさらに読み深めたりして、自分の「好き」をもっと探求していきたいです。この探求の先に、いつか私の進むべき道が見えてくると信じています。
作文例②:憧れの人のようになりたい
タイトル:祖父のような温かい人になるために
私の将来の夢は、と聞かれて、具体的な職業をすぐに答えることができません。しかし、「どんな大人になりたいか」と聞かれれば、迷わずに「祖父のような人になりたい」と答えます。私の祖父は、特別な職業に就いているわけではありません。定年退職し、今は静かに暮らしている、ごく普通の人です。しかし、私にとって祖父は、誰よりも尊敬できる憧れの存在です。
私が祖父を尊敬する理由は、その温かい人柄にあります。祖父は、誰に対しても分け隔てなく、いつも笑顔で接します。私が学校で嫌なことがあって落ち込んでいるとき、祖父は何も聞かずに、ただ黙って隣に座り、温かいお茶を淹れてくれます。その何気ない優しさに、私はいつも救われてきました。また、祖父は地域のボランティア活動にも積極的に参加しています。公園の清掃活動や、子どもたちの見守り活動など、人のために行動することを当たり前のように続けているのです。その姿を見ていると、「人の役に立つ」ということは、大きなことでなくても、身近な場所から始められるのだと気づかされます。
私は、祖父のような、周りの人を自然な形で助け、温かい気持ちにさせられる大人になりたいです。そのために、まずは自分の身の回りのことから始めていきたいと思っています。困っている友達がいたら声をかけること。家族への感謝の気持ちを言葉で伝えること。そういった小さな思いやりの積み重ねが、祖父のような大きな優しさにつながっていくのだと信じています。将来、どんな職業に就くとしても、この「人を思いやる心」だけは、ずっと持ち続けていきたいです。それが、今の私の最も大切な目標であり、夢なのです。
作文例③:好きな教科を深めたい
タイトル:理科の実験から広がる未来
「将来の夢を書きなさい」。そう言われても、私の頭にはなかなか具体的な職業が浮かんできませんでした。しかし、学校の授業の中で、私が時間を忘れるほど夢中になれる瞬間があります。それは、理科の実験の時間です。薬品を混ぜ合わせると色が変わったり、予想もしなかった気体が発生したり、目の前で起こる化学変化の一つひとつが、私にとっては驚きと発見の連続です。
特に印象に残っているのは、酸性とアルカリ性について学んだ実験です。リトマス試験紙の色が変わる様子は単純なようで、その背景には物質の性質という深い原理があることを知りました。私たちの身の回りにある食品や洗浄剤にも、すべて科学的な理由があるのだと考えると、世界が少し違って見えてきました。実験が上手くいかないこともありますが、仲間と協力して仮説を立て、試行錯誤を繰り返す過程そのものに、私は大きな魅力を感じています。なぜそうなるのか、という知的な好奇心を満たしてくれる理科の時間が、私にとっては何よりも楽しいのです。
この「理科が好き」という気持ちが、将来どんな道につながっていくのか、今はまだはっきりと分かりません。研究者になって新しい物質を発見する道や、学校の先生になって子どもたちに科学の楽しさを伝える道もあるかもしれません。あるいは、食品開発や化粧品開発など、私たちの生活に身近な分野でこの知識を活かすこともできるでしょう。今はまだ、その可能性を一つに絞ることはできませんが、まずはこの好奇心を大切に育てていきたいです。高校に進学したら、さらに専門的な化学や物理を学び、自分の興味がどこにあるのかをじっくりと見極めていきたいと考えています。
まとめ:将来の夢が決まってない中学生も、作文を通して自分を見つめよう

今回は、将来の夢が決まっていない中学生に向けた作文の書き方について、テーマの見つけ方から構成のコツ、具体的な作文例まで詳しく解説しました。
大切なのは、「夢がないこと」をネガティブに捉えるのではなく、自分自身と向き合う絶好の機会だと考えることです。具体的な職業が決まっていなくても、自分の興味があること、憧れる人の生き方、なりたい大人像、好きな教科など、作文のテーマはたくさんあります。
「今、夢がない」という正直な気持ちから書き始め、夢を探す過程や自分の考えを丁寧に記述し、未来に向けた前向きな抱負で締めくくる。この構成を意識すれば、きっとあなたらしい、素敵な作文が書けるはずです。この作文への取り組みが、あなた自身の未来を考える、価値ある一歩となることを願っています。




コメント