夏休みや冬休みの宿題の定番ともいえる「交通安全の作文」。いざ書こうと思っても、「何から手をつければいいの?」「どんなことを書けばいいんだろう?」と、ペンが止まってしまうことはありませんか。交通安全は身近なテーマだからこそ、かえって内容を絞るのが難しいと感じるかもしれません。
この記事では、そんな悩みを解決するために、交通安全の作文の書き方を、テーマの決め方から構成の作り方、表現の工夫まで、小学生から中学生まで誰にでも分かりやすく解説します。具体的な例文も紹介するので、書き方のイメージがぐっと掴みやすくなりますよ。作文を通じて交通安全への意識を深め、自分だけでなく周りの人の命を守ることの大切さを一緒に考えていきましょう。
交通安全の作文の書き方の基本!まずはテーマを決めよう
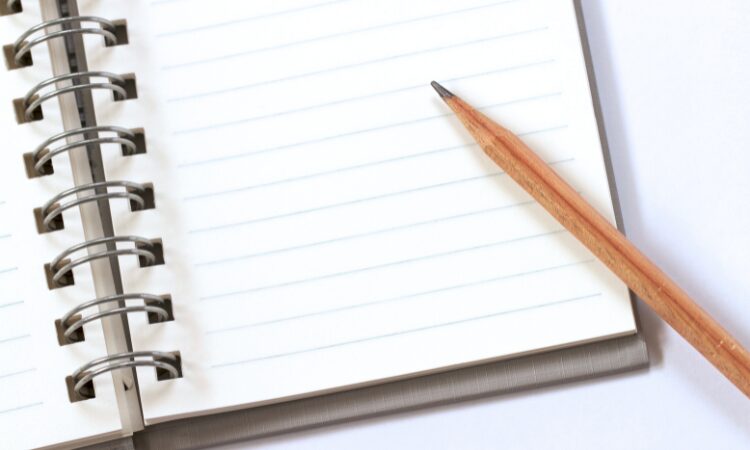
交通安全とひとことで言っても、その内容は多岐にわたります。自転車の乗り方、横断歩道の渡り方、自動車の危険性など、さまざまな切り口が考えられます。まずは、自分が一番書きたいこと、伝えたいことは何かを明確にすることが、スムーズに書き進めるための第一歩です。
なぜ交通安全の作文を書くの?目的を理解しよう
「なぜ交通安全の作文を書かなければいけないの?」と感じる人もいるかもしれません。この作文は、私たち一人ひとりが交通ルールの重要性を再認識し、安全な行動をとるための大切な学習機会です。 交通事故は、誰にでも起こりうる身近な危険であり、一瞬の不注意が取り返しのつかない事態を招くこともあります。
作文を書くために、自分の普段の行動を振り返ったり、家族と交通安全について話し合ったりすることで、これまで気づかなかった危険を発見できるかもしれません。 そして、自分の考えを文章にすることで、交通安全への意識がより一層深まります。 作文を通じて学んだことや感じたことを他の人に伝えることで、社会全体の交通安全意識を高めることにも繋がるのです。 まずは、「自分と周りの人の命を守るため」という目的をしっかり意識してみましょう。
身近な体験からテーマを見つける方法
作文のテーマを見つける最も効果的な方法は、自分自身の体験を振り返ることです。 難しく考える必要はありません。日常生活の中に、テーマのヒントはたくさん隠されています。
例えば、以下のような体験はなかったでしょうか。
- ヒヤリとした体験:急に自転車が飛び出してきて、ぶつかりそうになった。
- 危ないと感じた場所:見通しの悪い交差点や、信号機のない横断歩道。
- ルールを守らない人を見て感じたこと:歩きスマホをしている人や、赤信号を無視する自転車を見て怖いと思った。
- 自分がしてしまった反省:友達とおしゃべりに夢中で、周りを見ずに道を渡ってしまった。
このような具体的な体験は、作文にリアリティと説得力を与えてくれます。 その時、「なぜ危なかったのか」「どうすれば防げたのか」「その時どう感じたのか」まで深く掘り下げて考えてみると、より内容の濃い作文になります。 家族に「どこか危ない場所はない?」と聞いてみるのも良い方法です。
ニュースや社会問題からヒントを得る
自分の体験だけでなく、テレビのニュースや新聞、インターネットで報じられている交通問題に目を向けるのも一つの方法です。社会で起きていることと自分を結びつけて考えることで、より広い視野で交通安全を捉えることができます。
最近よく話題になるテーマとしては、以下のようなものがあります。
- 自転車のヘルメット着用:なぜヘルメットが努力義務化されたのか、その効果は何か。
- 高齢者の交通事故:なぜ高齢者の事故が多いのか、自分たちにできることは何か。
- あおり運転:なぜあおり運転は起きるのか、その危険性とは。
- ながらスマホの危険性:歩きながら、または自転車に乗りながらスマートフォンを操作することの危険性。
これらのテーマについて、インターネットなどで少し調べてみるのも良いでしょう。事故の統計データなどを引用すると、作文の説得力が増します。 ただし、調べたことを丸写しするのではなく、「その問題に対して自分はどう思うか」「自分なら何ができるか」という視点を必ず加えることが大切です。
具体的なテーマの例
ここまでのヒントを元に、具体的なテーマの例をいくつかご紹介します。この中から選んでも良いですし、自分なりにアレンジしてみるのもおすすめです。
【小学生向けのテーマ例】
- わたしの交通安全宣言「止まって、見て、待つ」
- 自転車に乗るときに気をつけていること
- こわかった!とび出しはぜったいにしない
- ランドセルカバーが教えてくれたこと
- 雨の日の通学路で考えたこと
【中学生向けのテーマ例】
- 自転車の「かもしれない運転」の重要性
- スマートフォンが奪うもの〜交通安全の視点から〜
- 地域の交通安全のために中学生ができること
- イヤホンと交通事故の危険な関係
- ヘルメット着用は「自分のため」
【重要】交通安全の作文で高評価を得る構成の作り方
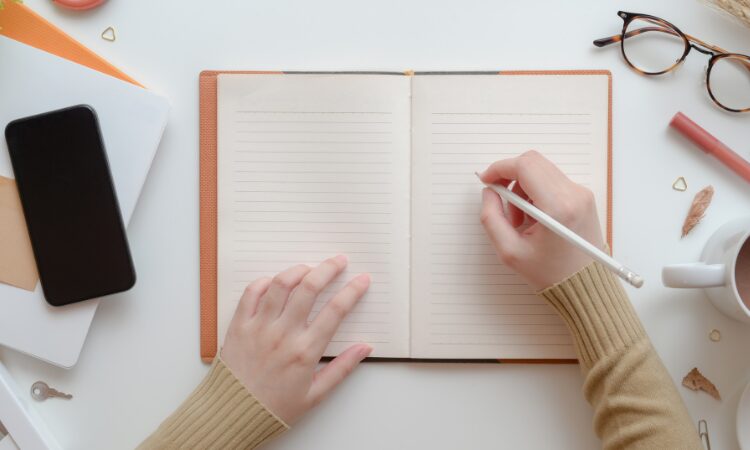
書きたいテーマが決まったら、次はいよいよ構成を考えます。構成とは、文章の設計図のようなものです。いきなり書き始めるのではなく、最初に構成をしっかり立てることで、内容が整理され、論理的で分かりやすい作文になります。
基本の三段構成「はじめ・なか・おわり」とは?
作文の基本構成は、「はじめ(序論)・なか(本論)・おわり(結論)」の三段構成です。 この型にあてはめて書くことで、言いたいことが明確に伝わる、まとまりのある文章になります。
- はじめ(序論):作文の導入部分です。これから何について書くのかを読者に示し、興味を引きつけます。問題提起や、きっかけとなった自分の体験などを書きます。
- なか(本論):作文の中心となる最も重要な部分です。「はじめ」で提起したことについて、具体的な体験談や、調べたこと、それによって考えたことなどを詳しく書きます。
- おわり(結論):「なか」で書いたことを踏まえて、全体のまとめをします。学んだことや、今後の決意、社会への提案などを書いて締めくくります。
この三段構成を意識するだけで、作文の質は格段に上がります。それぞれの部分で何を書くのか、箇条書きでメモを作ってから書き始めると、さらにスムーズに進みます。
「はじめ」で問題提起!読者の心をつかむ書き出し
「はじめ」は、読者が「この先を読んでみたい」と思うかどうかを決める大切な部分です。自分の体験をストレートに書いたり、読者に問いかけたりするなど、工夫次第でぐっと引き込まれる書き出しになります。
例えば、次のような書き出し方が考えられます。
- 体験談から入る:「『危ない!』母の鋭い声と、すぐ耳元で聞こえた急ブレーキの音。僕は、今でもあの時のことを思い出すと、心臓が凍りつくような気持ちになります。」
- 問いかけから入る:「皆さんは、自転車に乗るとき、必ずヘルメットをかぶっていますか。少し前までの僕は、正直に言うと『面倒くさいな』と感じていました。」
- 一般的な事実から入る:「テレビのニュースを見ていると、毎日のように交通事故の報道が流れてきます。その多くは、少しの注意で防げたかもしれない事故だと聞きます。」
このように、これから何について書こうとしているのかが読者に伝わるように意識することがポイントです。自分の体験と結びつけて書くことで、オリジナリティのある書き出しになります。
「なか」で具体的に!体験談や調べたことを盛り込む
「なか」は、作文の中で最も文字数を割くべき中心部分です。ここで、「はじめ」で提示したテーマを深く掘り下げていきます。 ここでのポイントは、具体的に書くことです。
例えば、「危ない体験をした」と書くだけでなく、「いつ、どこで、誰が、どうした」という情景が目に浮かぶように詳しく描写します。「信号のない交差点で、左右をよく確認せずに飛び出してしまったら、左から来た車が急ブレーキをかけた。キキーッというタイヤの音がして、運転手さんが驚いた顔でこちらを見ていた」というように書くと、読者にその時の状況や気持ちが伝わりやすくなります。
また、自分の体験だけでなく、客観的な情報を加えると説得力が増します。 例えば、「警察庁の統計によると、自転車事故で亡くなった人の約6割は頭部に致命傷を負っています。このデータを知って、ヘルメットがいかに重要かということを改めて感じました」といった形で、調べたことを盛り込むと良いでしょう。 この部分で、体験を通して何を考え、何を感じたのかを丁寧に書くことが、作文に深みを与えます。
「おわり」でまとめ!決意や提案で締めくくる
「おわり」は、作文の締めくくりです。「はじめ」「なか」で書いてきたことを受けて、最終的に自分が何を伝えたいのかを明確に示します。
締めくくり方としては、いくつかのパターンがあります。
- 今後の決意を述べる:「この経験を通して、交通ルールを守ることは、自分の命だけでなく、周りの人の命も守ることにつながると分かりました。これからは、『だろう運転』ではなく、『かもしれない運転』を心がけ、絶対に事故を起こさない、遭わないようにしたいです。」
- 社会への提案や呼びかけで締めくくる:「僕一人が気をつけても、交通事故はなくなりません。この作文を読んだ皆さんも、もう一度自分の行動を見直し、誰もが安心して暮らせる交通社会を一緒につくっていきませんか。」
- 学んだことや気づきをまとめる:「たった一つの交通ルールですが、その裏にはたくさんの人の安全への願いが込められているのだと気づきました。これからは、一つひとつのルールを大切に守っていこうと思います。」
このように、作文全体を振り返り、自分の考えをまとめることで、読者に強い印象を残すことができます。
すぐに使える!交通安全の作文の例文を紹介

ここでは、小学生、中学生、高校生それぞれの視点に合わせた交通安全の作文の例文を紹介します。構成や内容の展開の仕方を参考に、自分自身の言葉で作文を書いてみましょう。
【例文】小学生向け:自転車の安全な乗り方
題名:ぼくの「安全アンテナ」
(はじめ)
「危ない!」
公園からの帰り道、友達と競争するように自転車をこいでいた時、角から人が急に飛び出してきて、ぼくは慌てて急ブレーキをかけました。キキーッという大きな音と一緒に、心臓がどきりとしました。幸い、ぶつかることはありませんでしたが、もしブレーキが間に合わなかったらと思うと、今でも背中がひんやりします。この出来事をきっかけに、ぼくは自分の自転車の乗り方について、真剣に考えるようになりました。
(なか)
今までぼくは、自転車に乗るのが速いことがかっこいいと思っていました。でも、あの日以来、それは大きな間違いだったことに気づきました。お父さんにその話をすると、「運転には『かもしれない運転』という考え方が大切なんだよ」と教えてくれました。 「人が飛び出してくるかもしれない」「車が急に曲がってくるかもしれない」と、常に危険を予測しながら運転することだそうです。
次の日、ぼくは教わった「かもしれない運転」を意識して、通学路を自転車で走ってみました。見通しの悪い交差点では、いつもよりスピードを落として、「誰か来るかもしれない」とアンテナを立てます。すると、今まで気にしていなかった電柱のかげや、駐車している車のうしろなど、たくさんの危険な場所があることに気づきました。アンテナを立てると、景色がいつもと違って見えました。
(おわり)
あの日のできごとは、ぼくにとって怖い体験でした。しかし、そのおかげで、交通安全で本当に大切なのは、スピードではなく、周りへの注意や危険を予測する心、つまり「安全アンテナ」を立てることだと学びました。これからは、常に心の中に「安全アンテナ」を立てて、自分だけでなく、周りの人の安全も守れるような運転をしていきたいです。そして、友達にもこのアンテナの大切さを伝えていこうと思います。
【例文】中学生向け:スマートフォンと交通事故
題名:ポケットの中の危険
(はじめ)
私たちの生活に欠かせないスマートフォン。しかし、その便利さの裏には、大きな危険が潜んでいます。先日、下校中にイヤホンで音楽を聴きながら歩いていたところ、後ろから来た自転車に気づかず、ぶつかりそうになりました。幸い、相手の方がすぐに避けてくれたため事なきを得ましたが、もし気づくのが遅れていたら、大きな事故につながっていたかもしれません。この「ヒヤリハット」体験をきっかけに、私は「ながらスマホ」の危険性について深く考えるようになりました。
(なか)
「ながらスマホ」が危険なのは、画面に集中するあまり、周囲への注意力が著しく低下するからです。警察庁のデータによると、歩きスマホなどが原因の事故は年々増加傾向にあるといいます。特に、イヤホンで音楽を聴いていると、車のクラクションや救急車のサイレンなど、危険を知らせる音が聞こえなくなり、非常に危険です。
私の友人の中にも、歩きながらメッセージを確認したり、ゲームをしたりしている人がいます。彼らに注意をすると、「周りは見ているから大丈夫」という返事が返ってくることがほとんどです。しかし、本当にそうでしょうか。私の体験のように、危険は予期せぬ方向からやってきます。自分は大丈夫だという過信が、最も危険なのだと痛感しました。 自転車に乗りながらのスマホ操作は、さらに危険であり、法律で禁止されているにもかかわらず、平然と行っている人を多く見かけます。これは、自分だけでなく、他人の命をも危険にさらす行為です。
(おわり)
この経験を通して、私はスマートフォンを使う際には、TPO(時・場所・場合)をわきまえることがいかに重要であるかを学びました。道路を歩いている時や自転車に乗っている時は、スマートフォンはポケットやカバンにしまい、周囲の状況に集中する。当たり前のことですが、この当たり前を徹底することが、交通事故を防ぐ第一歩だと考えます。私のこの経験と考えが、少しでも多くの人に伝わり、「ながらスマホ」による悲しい事故が一つでも減ることを心から願っています。
【例文】高校生向け:地域の交通課題と自分の役割
題名:地域の一員として考える交通安全
(はじめ)
私が毎日利用する駅前の交差点は、朝の通勤・通学時間帯になると、歩行者、自転車、自動車が入り乱れ、非常に混雑します。特に、信号が青に変わる直前の見切り発車や、無理な右折をする車が多く、何度も危険な場面に遭遇してきました。こうした日常に潜む交通課題に対し、私たちは単なる「通行人」として無関心でいて良いのでしょうか。私は、高校生である自分も地域の一員として、交通安全のために果たせる役割があるのではないかと考えるようになりました。
(なか)
まず、私は地域の交通状況をより客観的に把握するため、その交差点で一時間ほど観察を行いました。すると、短い時間の中でも、スマートフォンの画面を見ながら横断する歩行者、イヤホンで音楽を聴きながら猛スピードで走り抜ける自転車、そして歩行者がいるにもかかわらず一時停止をしない自動車など、数多くの危険行為が確認できました。これらの行為の多くは、個々の交通参加者の「少しだけなら大丈夫だろう」という甘い認識から生まれているように感じられました。
しかし、この問題を個人のマナーだけに帰結させるべきではありません。交差点の構造自体にも改善の余地があるのではないかと考え、市役所のウェブサイトを調べたところ、過去に同様の市民からの意見が寄せられていました。例えば、歩行者と自転車の通行帯を色で明確に分ける「ナビマーク」の設置や、注意喚起の看板を増やすといった対策が考えられます。こうした具体的な改善策を行政に提案することも、私たちにできる行動の一つです。
(おわり)
交通安全は、誰か一人が頑張れば達成できるものではなく、地域社会全体で取り組むべき課題です。私にできることは小さいかもしれません。しかし、まずは自分自身が交通ルールを遵守し、危険な場面では勇気をもって注意を促すこと。そして、友人や家族と地域の交通問題について話し合い、必要であれば改善策を提案していくこと。こうした地道な行動の積み重ねが、誰もが安心して通行できる街づくりにつながると信じています。受動的に安全を享受するのではなく、能動的に安全を創造する一員でありたい。それが、私の交通安全に対する結論です。
交通安全の作文の書き方で差がつく!表現のポイント

内容や構成がしっかりしていても、表現が単調だと読者の心には響きにくいものです。ここでは、あなたの作文をより魅力的で、説得力のあるものにするための表現のポイントを紹介します。
五感を活用して情景をリアルに描く
体験談を書くときには、五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)を意識して描写すると、文章が生き生きとしてきます。読者がまるでその場にいるかのような、臨場感あふれる作文になります。
- 視覚(見たもの):「目の前で光った真っ赤なブレーキランプ」「運転席から見えた、ドライバーの青ざめた顔」
- 聴覚(聞こえた音):「キキーッという耳をつんざくようなブレーキ音」「救急車のサイレンが遠くからだんだん近づいてくる音」
- 触覚(感じたこと):「ぶつかりそうになった時に感じた、全身の血の気が引くような感覚」「転んで擦りむいた膝の、ジンジンとした痛み」
このように、具体的な描写を加えるだけで、単に「危なかった」と書くよりも、その時の緊張感や恐怖が格段に伝わりやすくなります。
データや統計を使って説得力をアップさせる
自分の意見を主張する際に、客観的なデータや統計を用いると、内容の説得力が格段に高まります。 「多くの事故が起きている」と書くよりも、「昨年一年間で、〇〇件もの自転車関連事故が発生しています」と具体的な数字を示す方が、問題の深刻さがより伝わります。
データは、警察庁や自治体、交通安全協会のウェブサイトなどで調べることができます。
- 例:「警察庁の統計によると、交通事故による死亡者数は年々減少していますが、その一方で、全事故に占める自転車関連事故の割合は増加傾向にあるそうです。」
ただし、数字をただ並べるだけでは意味がありません。そのデータを見て、自分がどう感じたか、何を考えたかを必ずセットで書くようにしましょう。「この数字を見て、自転車に乗る私たちも、車と同じように加害者になりうるのだと、改めて身が引き締まる思いがしました」というように、自分の言葉でつなげることが重要です。
効果的な言葉選びのコツ
同じ内容でも、言葉の選び方一つで読者に与える印象は大きく変わります。いつも使っている言葉を少し工夫してみるだけで、文章はより豊かになります。
例えば、「危なかった」という言葉一つでも、
- 「肝を冷やした」
- 「心臓が凍りつくようだった」
- 「背筋がぞっとした」
など、さまざまな表現ができます。
また、比喩(たとえ)を効果的に使うのも良い方法です。「スマートフォンは便利な道具ですが、使い方を間違えれば、人の命を奪う凶器にもなります」のように、身近なものにたとえることで、言いたいことがより分かりやすく、印象的に伝わります。自分の気持ちにぴったりの言葉を探しながら書くことで、作文の表現力はぐんとアップします。
原稿用紙の正しい使い方と注意点
作文を手書きで提出する場合、原稿用紙の正しい使い方を知っておくことも大切です。基本的なルールをしっかり守ることで、読みやすく、丁寧な印象を与えることができます。
- 題名:最初の行の2〜3マスを空けて書き始めます。
- 氏名:題名の次の行に書きます。名字と名前の間は1マス空け、行の下も1〜2マス空けるようにします。
- 段落の始め:本文を書き始めるときや、段落を変えるときは、必ず1マス空けてから書き始めます。
- 句読点(。、)や括弧(「」):1マスを使って書きます。ただし、行の最初に句読点や閉じ括弧が来る場合は、前の行の最後のマスに文字と一緒に入れます。
これらのルールは、作文の内容そのものではありませんが、評価の対象となることもあります。書き終わった後に、原稿用紙の使い方が正しいかもしっかりと確認しましょう。
交通安全の作文の書き方でよくある質問

ここでは、交通安全の作文を書くにあたって、多くの人が疑問に思う点についてお答えします。これらのポイントを押さえて、作文の完成度をさらに高めましょう。
何文字くらい書けばいいの?
作文に求められる文字数は、学校の課題やコンクールによって異なりますが、一般的には原稿用紙2〜3枚(800字〜1200字)程度が目安となることが多いです。 まずは指定された文字数を確認することが大切です。
文字数が足りない場合は、特に「なか(本論)」の部分を膨らませることを考えましょう。体験談をより具体的に描写したり、その体験から考えたことをさらに深掘りしたり、調べたことやデータを加えたりすることで、内容を充実させることができます。逆に文字数がオーバーしてしまう場合は、話のポイントがずれている部分や、同じことを繰り返し書いている部分がないかを見直し、文章を削って整理しましょう。
良い題名(タイトル)が思いつかないときは?
題名は、作文の「顔」とも言える重要な部分です。読者が題名を見て、どんな内容なのか興味を持つような、魅力的なものにしたいですよね。
良い題名が思いつかない場合は、作文をすべて書き終えてから考えるのがおすすめです。本文を書き上げた後であれば、自分が一番伝えたかったことや、作文の中心となるキーワードが明確になっているはずです。
- 作文のキーワードを入れる:「ぼくの『かもしれない運転』」「命を守るヘルメット」
- 内容を要約する:「ヒヤリとした体験から学んだこと」
- 問いかける形にする:「その一時停止、本当にできていますか?」
- 印象的な言葉を使う:「ポケットの中の危険」
このように、いくつかのパターンで考えてみると、ぴったりの題名が見つかりやすくなります。
書いた後、必ず見直し(推敲)をしよう
作文を書き終えたら、必ず見直し(推敲:すいこう)を行いましょう。急いで書くと、自分では気づかないうちに誤字脱字があったり、文章のつながりが不自然になっていたりすることがよくあります。
見直しのポイントは以下の通りです。
- 誤字脱字はないか:特に、「お・を」「は・わ」「え・へ」などの間違いやすい助詞に注意しましょう。
- 文章のねじれはないか:主語と述語が正しく対応しているか確認します。
- 読点(、)の位置は適切か:文章が長すぎると読みにくくなります。適度に読点を打って、意味の区切りを分かりやすくしましょう。
- 同じ言葉や表現を繰り返し使っていないか:特に文末が「〜でした。」「〜ました。」ばかりにならないように工夫すると、文章にリズムが生まれます。
少し時間をおいてから読み返したり、声に出して読んでみたりすると、おかしな点に気づきやすくなります。家族や先生に読んでもらい、感想を聞くのも非常に効果的です。
まとめ:交通安全の作文の書き方をマスターして、意識を高めよう

この記事では、交通安全の作文を書くための具体的なステップとコツを、例文を交えながら解説してきました。
作文を上手に書くためのポイントは、以下の通りです。
- テーマ決め:自分の身近な体験や、ニュースなどで関心を持ったことから、一番伝えたいことを一つに絞る。
- 構成:基本の「はじめ・なか・おわり」の三段構成で、話の流れを組み立てる。
- 内容の具体性:体験談は五感を使い、情景が目に浮かぶように詳しく書く。
- 表現の工夫:データを用いて説得力を持たせたり、効果的な言葉を選んだりして、読者の心に響く文章を目指す。
- 見直し:書き終えたら必ず推敲し、誤字脱字や不自然な表現を修正する。
交通安全の作文を書くことは、単なる宿題ではありません。自分自身の行動を振り返り、命の大切さを改めて考える貴重な機会です。 今回紹介した書き方を参考にして、あなたの心からのメッセージを言葉にしてみてください。あなたの作文が、あなた自身や周りの人々の交通安全意識を高めるきっかけになることを願っています。

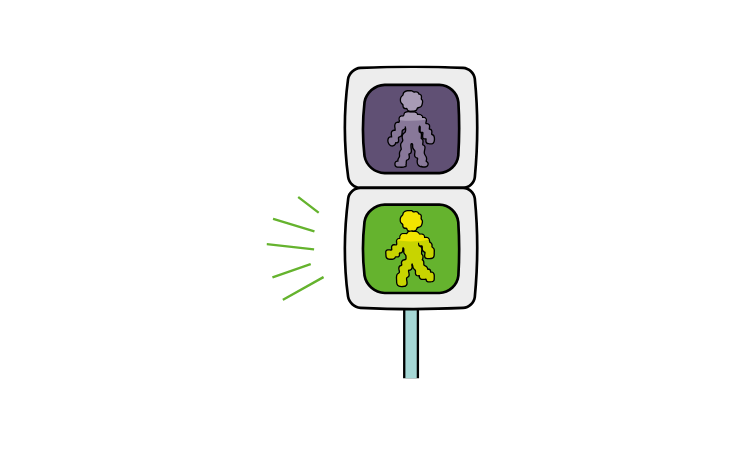


コメント