夏休みの宿題などで出されることが多い交通安全作文。「何を書けばいいか分からない…」と悩んだ末に、インターネットで例文を探して「ちょっとだけなら…」と、つい交通安全作文のパクリを考えてしまった経験はありませんか?
この記事では、そんな悩みを抱えるあなたのために、なぜ作文のパクリがいけないのか、そしてどうすればバレてしまうのかを具体的に解説します。さらに、パクリに頼らなくても、自分の力で素晴らしい交通安全作文を書くためのコツや、すぐに使えるテーマと構成例もご紹介します。この記事を読めば、もう作文の宿題で悩むことはありません。あなた自身の言葉で、交通安全の大切さを伝える作文を完成させましょう。
交通安全作文で「パクリたい」と思ってしまう心理

夏休みの宿題の定番ともいえる交通安全作文ですが、多くの小中学生が「何を書けばいいのだろう」と頭を悩ませています。そんな時、つい「他の人の作文を参考にしてしまおう」という考えが浮かんでしまうのは、なぜなのでしょうか。
なぜ「何を書けばいいか分からない」と感じるのか
交通安全というテーマは、あまりにも身近で当たり前のことであるがゆえに、かえって何を書けば良いのか分からなくなってしまうことがあります。毎日気をつけていること、例えば「信号を守る」「左右を確認して横断歩道を渡る」といった事柄は、日常生活に溶け込みすぎていて、わざわざ文章にするのが難しいと感じるのです。
また、交通事故の経験がなければ、その怖さや重要性を実感として語ることも難しくなります。自分に特別なエピソードがないと感じ、「書くことがない」という考えに陥ってしまうことが、パクリを考えてしまう最初のきっかけになることが多いのです。
「良い評価が欲しい」というプレッシャー
作文には評価がつきものです。「どうせ書くなら、先生に褒められるような立派な作文を書きたい」「コンクールで入賞したい」といった気持ちが、プレッシャーになることもあります。
インターネットで検索すれば、過去の入賞作品や上手な例文がたくさん見つかります。 それらの完成度の高い文章と自分の文章を比べてしまい、「自分にはこんなに上手に書けない」と自信をなくしてしまうのです。その結果、少しでも良い評価を得たいという思いから、上手な文章の表現や構成をそのまま真似してしまいたくなるのです。
時間がない、面倒くさいという気持ち
夏休みは、部活動や塾、友達との遊びなど、やりたいことがたくさんあります。そんな中で、作文という時間がかかる宿題は、どうしても後回しにされがちです。
締め切りが近づくにつれて焦り始め、「早く終わらせたい」「面倒くさい」という気持ちが強くなります。そうなると、自分でじっくり考えて文章を組み立てるよりも、手っ取り早くインターネット上の例文をコピー&ペースト(コピペ)して終わらせてしまいたい、という誘惑に駆られてしまうのです。このような焦りや面倒だという気持ちも、パクリにつながる大きな要因の一つと言えるでしょう。
交通安全作文のパクリがバレる理由と重大なリスク

「少しだけならバレないだろう」と安易な気持ちで他の人の作文を真似してしまうと、思わぬ事態を招く可能性があります。ここでは、なぜパクリがバレてしまうのか、そしてパクリが発覚した場合にどのようなリスクがあるのかを詳しく解説します。
先生にはどうしてバレる?
学校の先生は、毎年多くの子どもたちの作文を読んでいます。そのため、生徒一人ひとりの文章のクセや語彙力、表現の仕方をある程度把握しています。もし生徒が普段使わないような難しい言葉を使っていたり、急に大人びた文章を書いてきたりすると、「おや?」と違和感を覚えるのです。
また、インターネット上でよく使われている例文や、過去のコンクールの入賞作品は、多くの先生が目にしています。 そのため、有名な文章をそのまま、あるいは少しだけ変えて提出しても、すぐに見抜かれてしまう可能性が高いのです。先生はあなたのことをよく見ていますから、自分の言葉で正直に書くことが何よりも大切です。
コピペチェックツールの存在
近年、文章の盗用や剽窃(ひょうせつ)を防ぐために、コピペチェックツールというものが広く使われるようになっています。 これは、提出された文章がインターネット上の他の文章とどれくらい似ているかを自動で判定してくれる便利なツールです。
学校の先生がこのツールを使えば、あなたが参考にしたウェブサイトやブログ記事が瞬時に特定されてしまいます。無料で利用できるツールも多く存在するため、以前よりも簡単にパクリを発見できるようになっているのです。 「ネットの海から見つけられるはずがない」という考えは、もはや通用しないと心得ておきましょう。
パクリが発覚した際のペナルティ
もし交通安全作文のパクリが発覚した場合、単に「書き直し」で済めば良い方です。場合によっては、もっと深刻な事態につながる可能性があります。
まず、学校の成績(内申点)に大きく影響する可能性があります。 提出物に対して不正を働いたと見なされ、評価が大きく下がってしまうかもしれません。これは、高校受験などを考えている生徒にとっては、将来に響く大きな問題です。
さらに、著作権の侵害という法律上の問題に発展する可能性もゼロではありません。 他の人が書いた文章は、その人に「著作権」という権利があります。 それを無断でコピーして自分の作品として発表することは、他人の財産を盗むのと同じような行為なのです。 学校の宿題で法的な問題になることは稀ですが、パクリは決して許される行為ではないことを、しっかりと認識しておく必要があります。
交通安全作文のパクリを防ぐ!オリジナルの作文を書くための5つのステップ
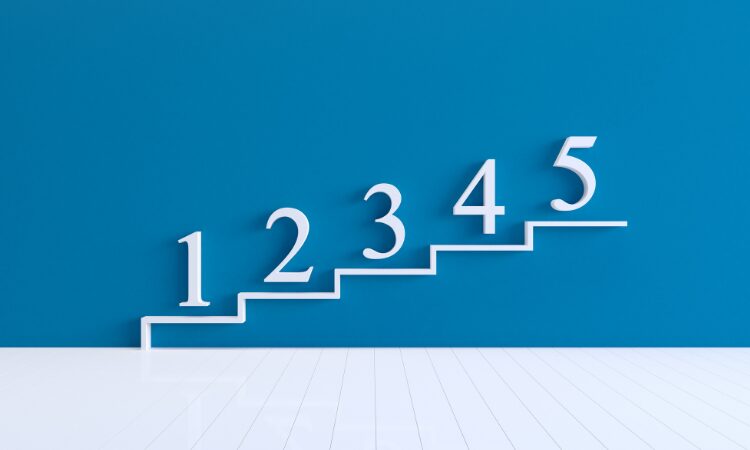
「パクリはダメだとわかったけど、やっぱり何から手をつけていいかわからない…」そんなあなたのために、誰でも簡単にオリジナルの交通安全作文が書けるようになる5つのステップをご紹介します。この手順に沿って進めれば、あなただけの素晴らしい作文が必ず書けるはずです。
ステップ1:テーマを決める(自分の体験を洗い出す)
まずは、作文の核となるテーマを決めましょう。難しく考える必要はありません。あなたの身の回りの体験からヒントを探すのが一番の近道です。
- 通学路でヒヤリとした経験:急に自転車が飛び出してきて危なかった、見通しの悪い交差点で怖い思いをしたなど。
- 家族との交通安全に関する会話:「いってらっしゃい、気をつけてね」という毎朝の挨拶の意味を考えてみる、親から自転車の乗り方で注意されたことなど。
- ニュースで見た交通事故:なぜ事故が起きたのか、自分だったらどうするかを考えてみる。
- 交通安全教室で学んだこと:特に印象に残っているルールや、その大切さを再確認する。
このように、自分の経験や感じたことを紙に書き出してみると、書きたいテーマが自然と見つかります。あなた自身の体験こそが、オリジナリティあふれる作文の源になります。
ステップ2:構成を考える(序論・本論・結論)
テーマが決まったら、次は文章の設計図となる構成を考えます。作文は基本的に「序論・本論・結論」の三段落構成で考えると、スムーズに書き進められます。
- 序論(はじめ):作文の導入部分です。ステップ1で決めたテーマ(問題提起)や、自分の体験談を簡潔に書きます。「私は先日、信号のない横断歩道でヒヤリとした経験をしました」といった書き出しです。
- 本論(なか):作文の中心部分です。序論で書いた体験について、その時の状況や自分の気持ち、そしてその経験から学んだことや考えたことを具体的に書きます。交通ルールがなぜ大切なのか、自分やまわりの人が安全に過ごすために何ができるかを深掘りしていきましょう。
- 結論(おわり):作文のまとめです。本論で述べたことを踏まえて、これからの自分の決意や、社会全体への呼びかけなどを書きます。「この経験を忘れず、これからは時間に余裕を持って行動し、周りをよく見て運転することを誓います」といった形で締めくくります。
この構成メモを作っておくだけで、文章が脱線することなく、言いたいことが明確に伝わる作文になります。
ステップ3:具体的なエピソードを盛り込む
構成に沿って文章を書いていく際に、最も重要なのが具体的なエピソードを盛り込むことです。単に「危なかったです」と書くのではなく、その時の情景が目に浮かぶように描写することで、読者の共感を得ることができます。
例えば、「自転車で角を曲がったら、急に人が出てきて危なかった」という経験を書くなら、
「部活に遅れそうで焦っていたその日、僕はいつもの角をスピードを落とさずに曲がりました。その瞬間、目の前に小さな男の子が立っていて、心臓が止まるかと思いました。キーッと音を立てて急ブレーキをかけましたが、あと少しでぶつかるところでした。」
というように、その時の自分の気持ち(焦り、驚き)や状況(音、距離感)を詳しく書くと、よりリアルで説得力のある文章になります。
ステップ4:自分の考えや学びを書く
体験談を語るだけで終わらせず、その経験を通じて何を学び、どう考えたのかをしっかりと書くことが、作文の深みを増す上で非常に重要です。
前の例で言えば、「ただ危なかった」で終わるのではなく、
「もしあの子にぶつかっていたら、大怪我をさせてしまっていたかもしれません。僕自身の焦りが、一歩間違えれば重大な事故につながるところでした。この出来事を通して、自転車は便利な乗り物であると同時に、人の命を奪う可能性もある危険なものなのだと痛感しました。」
というように、経験から得た教訓や反省を自分の言葉で表現しましょう。 ここが、あなたのオリジナリティが最も発揮される部分です。
ステップ5:読みやすく推敲(すいこう)する
作文が最後まで書けたら、必ず読み返しをしましょう。これを「推敲(すいこう)」と言います。 誤字脱字がないかはもちろん、以下の点もチェックしてみてください。
- 一文が長すぎないか:読点が多すぎる文は、適度な長さで区切ると読みやすくなります。
- 主語と述語の関係はおかしくないか
- 同じ言葉や表現を繰り返し使っていないか
- 声に出して読んでみる:リズムがおかしいところや、意味が分かりにくい部分が見つけやすくなります。
書きっぱなしにせず、少し時間をおいてから客観的な視点で読み返すことで、文章の完成度は格段に上がります。タイトルは、作文全体の内容を表すものを最後につけると良いでしょう。
【例文あり】交通安全作文でパクリを疑われないためのテーマと構成例

ここでは、小学生、中学生それぞれに向けた具体的なテーマと、それに沿った作文の構成例をご紹介します。これらの例を参考に、あなた自身の経験や考えを当てはめてみてください。パクリではなく、あなただけのオリジナル作文を作るためのヒントになるはずです。
小学生向けのテーマ例と書き方のポイント
小学生のうちは、自分の身近な体験や素直な気持ちを書くことが大切です。難しい言葉を使う必要はありません。
テーマ例:「僕の交通安全宣言」
- 序論(はじめ):通学路でヒヤリとした経験を書きます。
- (例文)「ぼくは毎日、小学校まで歩いて通っています。いつもは車に気をつけていますが、この前、信号のない横断歩道でとてもこわい思いをしました。」
- 本論(なか):その時の詳しい状況と、自分の気持ち、そしてその経験から学んだことを書きます。
- (例文)「急いでいたぼくは、左右をよく見ないで道をわたろうとしました。そのとき、一台のトラックが急ブレーキをふんで止まってくれました。運転手のおじさんはおこらずに、ぼくに『気をつけてね』と言ってくれました。ぼくは、自分の不注意で事故になるところだったと分かり、とてもはずかしくなりました。そして、いつも『気をつけていってらっしゃい』と言ってくれるお母さんの顔を思い出しました。」
- 結論(おわり):これからの自分の行動目標や決意を書きます。
- (例文)「ぼくは、二度とあのような危ないことをしないと決めました。横断歩道をわたる前には、必ず止まって右、左、もう一度右をしっかり見ます。そして、運転手さんに『わたります』という気持ちが伝わるように、手をあげてわたります。自分の命は自分で守るために、交通ルールをしっかり守ることをここに宣言します。」
中学生向けのテーマ例と書き方のポイント
中学生になったら、自分の体験だけでなく、そこから一歩進んで社会的な視点や他者への思いやりについても触れてみると、より深みのある作文になります。
テーマ例:「『かもしれない運転』の大切さ」
- 序論(はじめ):自転車でのヒヤリハット体験や、交通事故のニュースなど、問題提起から入ります。
- (例文)「『大丈夫だろう』。この油断が、取り返しのつかない事故を引き起こすことがあります。私はこの夏、自転車に乗っている時にそのことを痛感する出来事を経験しました。」
- 本論(なか):具体的なエピソードを詳しく描写し、そこから得た気づきや考えを深めていきます。
- (例文)「見通しの悪い交差点にさしかかった時、私は『車は来ないだろう』と思い込み、スピードをあまり落とさずに進入しました。その直後、左から来た自動車が急ブレーキをかけ、すれすれのところで衝突を免れました。運転手の方に謝ると、彼は『自分も『自転車は来ないかもしれない』と予測すべきだった』と言ってくださいました。この言葉で、私はハッとしました。交通安全は、車や歩行者、どちらか一方だけが気をつけるのではなく、お互いが『~かもしれない』と危険を予測し、譲り合う心を持つことで成り立つのだと気づかされたのです。」
- 結論(おわり):自分の行動の変化と、社会全体への提案やメッセージで締めくくります。
- (例文)「この経験以来、私は自転車に乗る時、常に『曲がり角から人が飛び出してくるかもしれない』『ドアが急に開くかもしれない』と考えるようになりました。ほんの少し想像力を働かせるだけで、危険を回避できる場面はたくさんあります。私たち一人ひとりが『かもしれない運転』を心掛けることが、悲しい交通事故をなくすための、最も確実で大切な一歩なのだと、私は強く信じています。」
作文で他の人の意見を参考にするときの注意点
インターネットや本で見た良い意見や表現を、自分の作文に取り入れたいと思うこともあるでしょう。その場合、「パクリ」と見なされないためには正しい引用と自分の言葉での表現が不可欠です。
他の人の文章をそのまま使う場合は、「」(かぎかっこ)で囲み、誰の言葉(あるいはどの本からの言葉)なのかを明記するのが引用のルールです。 しかし、学校の作文で厳密な引用をすることは少ないかもしれません。
大切なのは、参考にした情報を鵜呑みにせず、その情報をもとに自分自身で考え、自分の言葉で書き直すことです。例えば、「交通事故の原因は『だろう運転』にある」という一文を参考にするなら、「多くの事故は、『自分は大丈夫だろう』という少しの油断から生まれるのだと知りました」というように、自分の解釈を加えて表現し直す工夫をしましょう。 これにより、文章はあなたのオリジナルなものになります。
まとめ:交通安全作文はパクリに頼らず、自分の言葉で伝えよう

この記事では、交通安全作文のパクリがなぜいけないのか、そしてパクリに頼らずに自分の力で作文を書き上げるための具体的な方法について解説しました。
- パクリはバレる:先生はあなたの文章の個性を知っていますし、コピペチェックツールを使えば簡単に見抜かれてしまいます。
- パクリのリスク:成績への悪影響だけでなく、著作権というルールを破る行為であることを理解しましょう。
- オリジナルの作文は自分の体験から:特別な経験は必要ありません。通学路でのヒヤリとした体験や家族との会話など、身近な出来事こそが最高のテーマになります。
- 構成を立ててから書く:「序論・本論・結論」の型に沿って、具体的なエピソードと自分の考えを盛り込むことで、説得力のある文章になります。
交通安全作文を書く目的は、単に宿題を終わらせることではありません。交通安全について真剣に考え、自分や周りの人の命を守る意識を高めるための大切な機会です。 他の誰かの言葉を借りるのではなく、あなた自身の体験から生まれた素直な気持ちや考えを、自分の言葉で表現してみてください。その作文は、きっと誰の心にも響く、世界に一つだけの素晴らしい作品になるはずです。




コメント