「高校生になったらバイトを始めたい!」と考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、多くの高校ではアルバイトをするために「アルバイト許可証(アルバイト届)」の提出が必要です。いざ書こうと思っても、「理由はどう書けばいいの?」「保護者の欄はどうしよう?」と悩んでしまいますよね。
この記事では、そんな悩みを抱える高校生や保護者の皆さんに向けて、バイト許可証の書き方を分かりやすく徹底解説します。申請理由の具体的な例文から、各項目の記入例、提出する際の注意点まで、この記事を読めばスムーズに書類を準備できるようになります。安心して楽しいアルバイト生活をスタートさせるために、まずは正しい許可証の書き方をマスターしましょう。
バイト許可証とは?なぜ必要なの?

アルバイトを始める前に、まずは「アルバイト許可証」がどのようなもので、なぜ学校に提出する必要があるのかを理解しておきましょう。この書類の重要性を知ることで、より誠実な内容で作成することができます。
アルバイト許可証(アルバイト届)の役割
アルバイト許可証とは、高校生がアルバイトを始める際に、学校から許可を得るために提出する正式な書類です。 学校側はこの書類を通じて、生徒がどのような環境で、どのくらいの時間働くのかを把握します。 主な目的は、生徒の本分である学業との両立が可能か、そして安全で健全な労働環境であるかを確認することです。 また、保護者がアルバイトに同意しているかどうかの確認も重要な役割の一つです。 このように、アルバイト許可証は、生徒がトラブルに巻き込まれることなく、学業と両立しながら有意義な社会経験を積むための、学校と家庭、そして生徒自身の大切な約束事のようなものなのです。
学校がバイトを許可制にする理由
そもそも、なぜ多くの学校ではアルバイトが原則禁止、あるいは許可制なのでしょうか。その最も大きな理由は、生徒の本分である学業に専念させるためです。 アルバイトに時間を費やすあまり、授業の予習・復習がおろそかになったり、テストの成績が下がったりすることを学校側は懸念しています。
また、生徒の安全確保も大きな理由の一つです。 深夜の勤務や危険を伴う職種など、高校生にふさわしくない労働環境から生徒を守る目的があります。 万が一、アルバイト先でトラブルに巻き込まれた場合、学校側が状況を把握していないと対応が難しくなる可能性もあります。 このように、学校がアルバイトを許可制にしているのは、生徒の将来や安全を守るための重要な仕組みなのです。
バイト許可証がないとどうなる?
もし学校の校則で許可証が必要とされているにもかかわらず、無断でアルバイトをした場合はどうなるのでしょうか。最も多いのは、友人との会話やSNSへの投稿、先生による目撃などで発覚するケースです。
無断でのアルバイトが発覚した場合、まずは厳重注意や反省文の提出を求められることが一般的です。 場合によっては、保護者が学校に呼び出されて指導を受けることもあります。 校則が厳しい学校では、停学や謹慎などの重い処分が下される可能性もゼロではありません。 さらに、内緒でアルバイトをしていると、万が一職場でトラブルにあった際に、学校や親に相談しづらく、一人で抱え込んでしまう危険性もあります。 安心して働くためにも、必ず定められた手続きに従いましょう。
バイト許可証の入手方法と提出までの流れ
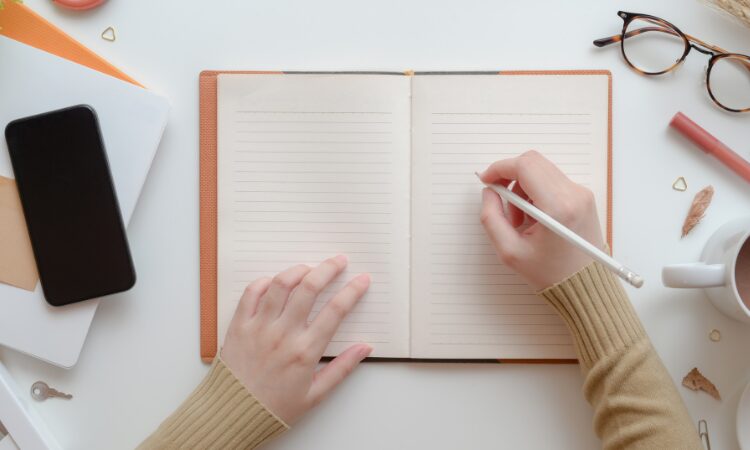
アルバイト許可証をスムーズに提出するためには、事前の準備と正しい手順を理解しておくことが大切です。ここでは、許可証を手に入れてから学校に提出するまでの一般的な流れを4つのステップで解説します。
ステップ1:学校のルールを確認する
まず最初に、自分の通う高校の校則を確認しましょう。 学校によっては、アルバイトを全面的に許可している場合もあれば、原則禁止で特別な理由がない限り許可されない場合もあります。 また、成績の基準(例:赤点を取っていないこと)や、勤務時間の上限、許可されない職種(例:酒類を提供する飲食店など)が細かく定められていることもあります。生徒手帳を読んだり、学校のウェブサイトを確認したり、一番確実なのは担任の先生に直接相談することです。 早い段階でルールを正確に把握しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
ステップ2:担任の先生に相談して許可証をもらう
学校のルールを確認したら、次に担任の先生にアルバイトをしたい旨を相談し、アルバイト許可証の申請用紙をもらいます。 この時、なぜアルバイトをしたいのか、どのような職種を考えているのかを具体的に伝えられると、先生もアドバイスをしやすくなります。先生は、あなたの学業の状況や学校生活の様子を一番よく理解してくれている存在です。真摯に相談することで、申請理由の書き方や、学業との両立について親身に相談に乗ってくれるでしょう。許可証の用紙は、学校の事務室や生徒指導室などで配布される場合もあります。
ステップ3:必要事項を記入し保護者の署名をもらう
申請用紙を手に入れたら、必要事項を丁寧に記入していきます。氏名やクラスなどの基本情報に加え、アルバイト先の情報(名称、住所、電話番号)、勤務時間、仕事内容などを正確に書きましょう。そして、最も重要なのが保護者の同意です。
必ず保護者にアルバイトをしたい理由をしっかりと説明し、理解を得た上で、署名と捺印をしてもらってください。 高校生は未成年であるため、保護者の同意なしに労働契約を結ぶことはできません。 学校側も家庭の理解と協力があるかを非常に重視しています。 この段階で親子できちんと話し合い、家庭内でのルール(門限、学業との両立の約束など)も決めておくと良いでしょう。
ステップ4:学校に提出して許可印をもらう
全ての項目を記入し、保護者の署名・捺印をもらったら、完成した許可証を担任の先生に提出します。 提出された書類は、担任の先生だけでなく、学年主任や生徒指導の先生などが確認し、問題がなければ承認の印鑑が押され、正式にアルバイトの許可が下ります。学校によっては、許可証の控えを自分で保管する場合や、アルバイト先に提出する必要がある場合もありますので、指示に従いましょう。これで、安心してアルバイトをスタートすることができます。
【見本付き】バイト許可証の基本的な書き方
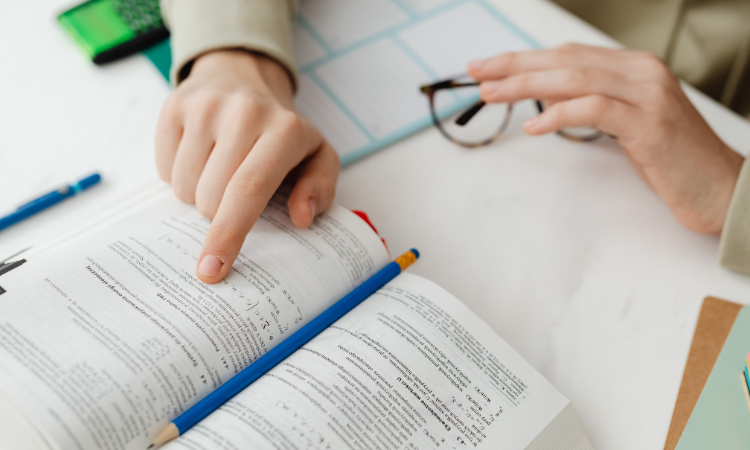
アルバイト許可証には、様々な項目を記入する必要があります。ここでは、一般的な許可証の様式を元に、各項目の具体的な書き方を解説します。正確かつ丁寧に記入することが、スムーズな許可を得るための第一歩です。
氏名・住所・連絡先など本人に関する情報
この欄には、あなた自身の情報を正確に記入します。具体的には、学年、組、出席番号、氏名、住所、電話番号などです。文字は誰が読んでも分かるように、楷書(かいしょ)で丁寧に書きましょう。特に、氏名や学籍番号は学校側が本人を確認するための重要な情報ですので、間違いのないように注意してください。住所は省略せず、都道府県からアパートやマンション名、部屋番号まで正確に記入します。連絡先は、日中に連絡がつきやすい電話番号を書いておくと良いでしょう。
アルバイト先(勤務先)に関する情報
次に、実際に働くことになるアルバイト先の情報を記入します。 この欄は、学校があなたの働く環境が適切かどうかを判断するための重要な部分です。
- 事業所名(店名):正式名称を正確に書きましょう。(例:株式会社〇〇 △△店)
- 所在地(住所):勤務先の住所を省略せずに記入します。
- 電話番号:お店の電話番号を記入します。
- 代表者氏名:店長や採用担当者の氏名を記入します。
- 仕事内容:どのような仕事をするのかを具体的に書きます。(例:飲食店でのホール業務(接客、配膳、レジ)、スーパーマーケットでの品出し・レジ業務)
これらの情報は、アルバイトの面接時に確認しておくか、採用が決まった際に受け取る契約書などを見て正確に転記してください。
勤務条件(勤務時間・期間など)
あなたの働き方が学業に支障をきたさないか、学校が確認するための項目です。
- 雇用期間:「〇年〇月〇日から長期」や「〇年〇月〇日~〇年〇月〇日まで」のように、働く期間を記入します。
- 勤務日・時間:「火曜日・木曜日の17時~20時」「土日祝日の10時~15時」のように、働く曜日や時間帯を具体的に書きます。 シフト制で曜日や時間が変動する場合は、その旨と週に何日、何時間程度働く予定かを補足で記入すると親切です。
- 労働時間:1日あたりの労働時間と、休憩時間を記入します。(例:1日3時間、休憩なし)
特に勤務時間は、学校の校則で定められた上限を超えていないか、必ず確認してから記入しましょう。
保護者署名・捺印欄
最後に、保護者の同意を示すための欄があります。この欄は、必ず保護者本人に記入・捺印してもらう必要があります。 保護者の氏名を自署してもらい、その横に捺印をお願いします。学校によっては、保護者の意見や所見を記入する欄が設けられている場合もあります。その場合は、アルバイトに同意する理由や、学業との両立を家庭でどのようにサポートするかなどを具体的に書いてもらうと、学校側の理解を得やすくなります。 (詳しくは次の章で解説します)
バイト許可証の書き方で悩むポイントと例文
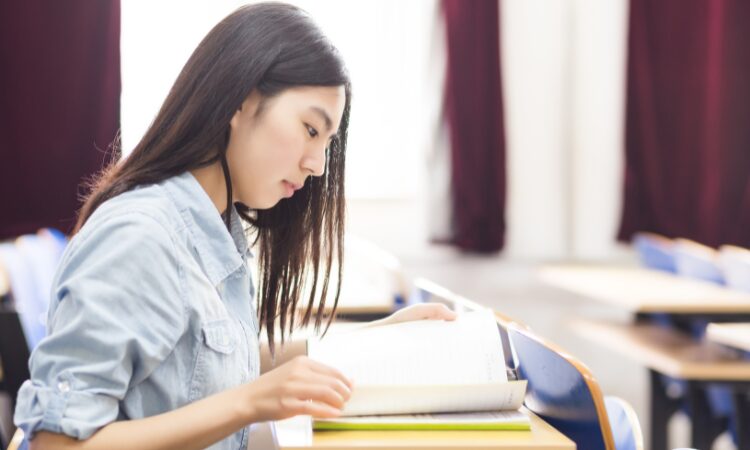
許可証を書く上で、多くの人が特に頭を悩ませるのが「アルバイトをする理由」の欄です。「お小遣いが欲しいから」という本音をそのまま書いて良いのか、どうすれば先生に納得してもらえるのか、具体的な例文を交えながら解説します。
説得力のある「アルバイトをする理由」の書き方(例文付き)
アルバイトをする理由は、正直かつ具体的に、そして前向きな姿勢が伝わるように書くことが大切です。 学校側が納得しやすい理由としては、経済的な事情や将来の目標に向けたものが挙げられます。
【例文1:進学費用のため】
「将来、〇〇大学(または〇〇専門学校)への進学を希望しており、そのための入学金や学費の一部を自分でも準備したいと考えています。親に負担をかけるだけでなく、自らの力で将来の資金を貯めることで、目標に対する責任感を持ちたいです。学業をおろそかにすることなく、計画的に両立させます。」
【例文2:社会経験のため】
「将来、接客業に就きたいという夢があります。実際に社会に出て働く経験を通じて、コミュニケーション能力やビジネスマナーを学びたいです。アルバイトで得た経験を、今後の進路選択や社会人としての基礎作りに活かしたいと考えています。」
【例文3:家庭の経済的支援のため】
「家計を少しでも助けるため、自分のお小遣いや携帯電話の料金は自分で賄いたいと考えています。アルバイトをすることで、働くことの大切さを学び、家族の一員としての責任を果たしたいです。」
【例文4:特定の目的のため】
「〇〇(資格名)の資格取得を目指しており、そのための教材費や受験費用を自分で貯めたいです。目標達成のためにアルバイトで努力する経験は、自分自身の成長につながると考えています。」
「学業との両立」をどうアピールするか
学校側が最も重視するのは、アルバイトが学業の妨げにならないかという点です。 したがって、理由の欄には、学業とアルバイトを両立させる具体的な意志を明確に示すことが非常に重要です。
文章の締めくくりに、以下のような一文を加えることで、先生に安心感を与えることができます。
- 「アルバイトを始めるにあたり、これまで以上に計画的に学習時間を確保し、学業を最優先することをお約束します。」
- 「定期テストの2週間前からはシフトを減らす(または休む)など、勉強に集中できる環境を自分で作ります。」
- 「もし成績が下がることがあれば、すぐにアルバイトの働き方を見直すことを保護者と約束しています。」
このように、具体的な行動計画を示すことで、あなたの真剣な姿勢が伝わり、許可が得やすくなります。
保護者意見欄の書き方とお願いのポイント
保護者意見欄や所見欄がある場合、ここでの記述も許可を得るための重要な要素となります。保護者の方には、お子さんの意思を尊重し、家庭でサポートしていく姿勢を示してもらうようお願いしましょう。
【例文1:子どもの意思を尊重する】
「いつもお世話になっております。本人が将来の進学資金を貯めたいという強い意志を持っており、その自立心を尊重したいと考えております。学業との両立が前提であることを本人とよく話し合いました。家庭でも生活面・健康面でのサポートを徹底してまいりますので、何卒ご許可いただけますようお願い申し上げます。」
【例文2:社会経験への期待】
「社会に出て働くという経験は、本人の成長にとって貴重な機会になると考えております。責任感や金銭感覚を養う良い機会と捉え、今回のアルバイトを許可いたしました。学業に支障が出ないよう、家庭でもしっかりと監督・指導してまいります。」
保護者の方に記入をお願いする際は、なぜアルバイトをしたいのかを自分の言葉でしっかり説明し、親子で将来について話し合う良い機会にしましょう。
バイト許可証を提出する際の注意点

書類が完成したら、いよいよ提出です。しかし、提出する前にいくつか確認しておくべき大切な注意点があります。これらを守らないと、後でトラブルになったり、許可が取り消されたりする可能性もあるため、最後まで気を抜かずにチェックしましょう。
虚偽の申請は絶対にNG!
アルバイト許可証に嘘の情報を書くことは絶対にやめましょう。例えば、勤務時間や仕事内容を偽って申請することは、学校や保護者との信頼関係を損なう行為です。万が一、虚偽の申請が発覚した場合、アルバイトの許可が取り消されるだけでなく、校則違反として厳しい指導や処分を受ける可能性があります。正直に、正確な情報を記入することが、信頼を得るための基本です。何か書きにくい事情がある場合は、嘘をつくのではなく、正直に先生に相談することが大切です。
バイト先が決まってから申請する
アルバイト許可証は、実際に働くアルバイト先が決定してから申請するのが一般的です。 なぜなら、許可証には勤務先の名称、住所、仕事内容、勤務時間など、具体的な情報を記入する必要があるからです。 アルバイトの面接を受ける際に、「採用が決まったら、学校の許可証を提出する必要があります」と事前に伝えておくとスムーズです。採用が内定してから、正式な勤務条件などを確認し、許可証を作成・提出するようにしましょう。
学校で禁止されているバイトではないか確認する
学校の校則では、生徒の安全や健全な育成の観点から、特定の業種でのアルバイトを禁止している場合があります。 一般的には、以下のような場所でのアルバイトが禁止されていることが多いです。
- お酒を提供する居酒屋やバーなど
- パチンコ店やゲームセンターなど
- 深夜(22時以降)に及ぶ勤務
自分の希望するアルバイト先が、学校のルールに違反していないか、提出前にもう一度しっかりと確認しましょう。もし判断に迷う場合は、必ず担任の先生に相談してください。
提出期限を守る
学校によっては、アルバイト許可証の提出期間が定められている場合があります。長期休業中のアルバイトなど、特定の期間だけ許可されるケースでは、申請の受付期間が限られていることもあります。先生への相談や書類の準備には時間がかかることもあるため、アルバイトを始めたいと思ったら、できるだけ早めに動き出し、余裕を持って提出するように心がけましょう。期限を守ることも、社会人としての第一歩です。
まとめ:バイト許可証の書き方をマスターして楽しいバイト生活を!

今回は、アルバイト許可証の書き方について、その目的から具体的な記入例、注意点まで詳しく解説しました。最後に、記事の重要なポイントを振り返ります。
- アルバイト許可証は、学業との両立と安全な労働環境を確認するための大切な書類です。
- 申請理由は、進学費用や社会経験など、具体的かつ前向きな内容で伝えましょう。
- 学業を最優先する姿勢を明確にアピールすることが許可を得るための鍵となります。
- 保護者の同意は必須です。 日頃から親子でよく話し合い、協力して書類を完成させましょう。
- 虚偽の申請はせず、学校のルールを必ず守ることが、信頼につながります。
アルバイトは、お金を稼ぐだけでなく、社会の仕組みを学び、責任感を養うなど、人として大きく成長できる貴重な経験です。 この記事で紹介した内容を参考にして、しっかりと準備を行い、学校や保護者から応援される形で、充実したアルバイト生活をスタートさせてください。


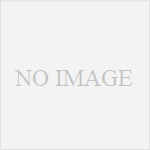

コメント