小学校5年生になると、学校の宿題で日記を書く機会が増えたり、自分の考えを文章で表現することが求められたりしますよね。「毎日何を書けばいいのか分からない」「いつも同じような内容になってしまってつまらない」と、日記の書き方について悩んでいる人もいるかもしれません。
この記事では、そんな小学校5年生のみなさんのために、日記を楽しく、そして上手に書くためのコツをわかりやすく解説します。日記は、ただ出来事を記録するだけのものではありません。文章を書く練習になったり、自分の気持ちを整理したり、毎日を振り返ることで新しい発見があったりと、たくさんのメリットがあります。 この記事を読んで、基本的な書き方から、もっと面白くするためのアイデアまで、いろいろなヒントを見つけて、今日からあなただけの日記を始めてみませんか?
小学校5年生が知っておきたい!日記の書き方の基本

日記を書くとき、何から手をつけていいか分からないと感じるかもしれません。でも、心配はいりません。いくつかの基本的なポイントを押さえるだけで、ぐっと書きやすくなります。まずは、文章の骨組みとなる部分をしっかりと組み立てる練習から始めましょう。
まずは「いつ・どこで・だれが・何をした」を書こう
日記を書くうえで一番大切なのは、「いつ・どこで・だれが・何をした」という基本の要素を入れることです。 これは「5W1H」とも呼ばれ、文章を分かりやすくするための基本です。 これらを意識するだけで、何があったのかがはっきりと伝わる文章になります。
例えば、「楽しかった」と一言で書くのではなく、
- いつ:今日の放課後
- どこで:公園で
- だれが:〇〇くんと△△さんと
- 何をした:サッカーをした
というように、具体的な情報を書き加えてみましょう。これだけで、ただ「楽しかった」と書くよりも、読んだ人がその時の様子をイメージしやすくなります。 最初は難しく考えずに、この4つの要素を文章に入れることを意識してみてください。慣れてきたら、「なぜそうしたのか(Why)」「どのようにしたのか(How)」を加えると、さらに詳しい内容になります。
気持ちや考えたことをプラスしてみよう
出来事を書くだけでなく、その時に自分がどう感じたか、何を考えたかを書き加えることが、日記をより面白くするポイントです。 「楽しかった」「うれしかった」「くやしかった」「びっくりした」など、自分の感情を素直に言葉にしてみましょう。
例えば、先ほどのサッカーの例に気持ちをプラスしてみましょう。
「今日の放課後、公園で〇〇くんと△△さんとサッカーをした。最初はパスがうまくつながらなくてくやしかったけど、最後に僕がシュートを決めて勝てたので、すごくうれしかった。まるでプロのサッカー選手になったみたいな気分だった。」
このように、「どうしてそう感じたのか」という理由や、「何みたいだったか」というたとえを入れると、より生き生きとした文章になります。 自分の心の中をのぞいて、その時に動いた気持ちを正直に書いてみることが大切です。最初は短い言葉でも大丈夫。少しずつ、自分の気持ちを表現する練習をしていきましょう。
見たことや聞いたことを具体的に書く練習
日記をより面白く、読んだ人がその場にいるかのように感じる文章にするためには、見たことや聞いたことを具体的に書くことが効果的です。 例えば、「きれいな花が咲いていた」と書く代わりに、どんな花だったかを詳しく説明してみましょう。
「学校の帰り道、花だんに赤いチューリップがたくさん咲いていた。太陽の光を浴びて、キラキラと輝いているように見えた。風が吹くと、みんなで楽しそうにダンスをしているみたいだった。」
このように、色、形、様子、音、においなど、五感を使って感じたことを言葉にしてみると、文章に深みが出ます。 また、友達や家族との会話を思い出して、実際に話した言葉を「」に入れて書くのも良い方法です。
「『ナイスシュート!』と〇〇くんが叫んだ。ぼくはうれしくて、思わずガッツポーズをした。」
このように会話文を入れると、その時の場の雰囲気がより伝わりやすくなります。日記を書き終えたら、もう少し詳しく書ける部分はないか、読み返してみるのもおすすめです。
【日記の書き方】小学校5年生がネタに困らないためのヒント

「毎日同じことのくり返しで、書くことがない…」というのは、日記を書くときに多くの人がぶつかる悩みです。でも、周りをよく見渡してみると、日記のネタは意外とたくさん隠れています。普段の生活の中から、面白い「種」を見つける方法を知っておけば、もうネタ探しに困ることはありません。
学校での出来事を深掘りしてみる
学校は、日記のネタの宝庫です。授業中に「なるほど!」と思ったこと、休み時間に友達と笑ったこと、給食でおかわりしたことなど、ささいなことでも立派な日記のテーマになります。
例えば、算数の授業で難しい問題が解けた時のことを書いてみましょう。「先生の説明を聞いても分からなかったけど、友達の〇〇さんがヒントをくれて、やっと解くことができた。分かった瞬間、頭の中に電球がピカッと光ったみたいにスッキリした。あきらめないでよかった。」というように、ただ「問題が解けた」だけでなく、その時の気持ちの変化や思ったことまで書くと、自分だけの特別な記録になります。
また、係の仕事や委員会活動、クラブ活動での出来事も良いネタになります。掃除の時間に見つけた面白い落とし物、係の仕事で協力した友達とのことなど、少し視点を変えるだけで、たくさんの発見があるはずです。
家族や友達との会話を思い出してみる
家族や友達と話した内容も、日記の素晴らしいネタになります。 夕食の時に家族で話したこと、登下校中に友達と盛り上がったことなど、印象に残っている会話を思い出してみましょう。
例えば、「今日、お母さんが『小学校の時、給食の揚げパンが大好きだったんだよ』と話してくれた。今の給食には揚げパンが出ないから、どんな味なのかすごく気になった。今度、お母さんと一緒に作ってみたいと思った。」というように、会話をきっかけに自分が考えたことや、次にやってみたいことを書くと、日記の内容が広がります。
友達との会話で面白かった冗談や、びっくりした話なども良いでしょう。その会話によって、自分がどんな気持ちになったのかを付け加えるのを忘れないでください。会話を思い出すことで、その日の出来事がより鮮明によみがえり、書くことが見つかりやすくなります。
好きなこと・夢中になっていることを書いてみよう
自分の好きなことや、今まさに夢中になっていることについて書くのも、とても楽しい作業です。ゲーム、漫画、アニメ、スポーツ、アイドル、習い事など、あなたの「大好き」を日記にぶつけてみましょう。
例えば、好きなキャラクターについて書くなら、「今日、好きなアニメの新しいグッズが発売された。おこづかいを貯めて絶対に手に入れたい。そのキャラクターのかっこいいところは、仲間を絶対に裏切らないところだ。ぼくも、そんな友達を大切にできる人になりたい。」というように、ただ「好き」というだけでなく、どこが好きなのか、どうして好きなのか、自分とどう関係があるのかを書いてみると、深い内容の日記になります。
読書が好きなら、読んだ本のあらすじと感想を書く「読書日記」にするのも良いアイデアです。自分が夢中になれることなら、きっとたくさんの言葉があふれてくるはずです。日記を書くのが面倒だと感じた日こそ、自分の「好き」をテーマに選んでみてください。
ニュースや天気など、身の回りの変化に目を向ける
自分の身の回りの出来事だけでなく、もう少し広い視野で世の中の出来事や自然の変化に目を向けてみるのも、ネタを見つける一つの方法です。
例えば、朝のニュースで見た気になる話題について、自分はどう思うかを書いてみましょう。「今日、ニュースで新しいロケットが打ち上げられたと言っていた。宇宙には何があるんだろう。大人になったら宇宙旅行に行って、自分の目で地球を見てみたいと思った。」このように、ニュースをきっかけに自分の考えや将来の夢につなげることができます。
また、天気や季節の変化も立派な日記のテーマです。 「今日は一日中雨だった。窓ガラスを流れる雨粒をぼーっと眺めていたら、雨粒たちが競争しているように見えて面白かった。」「帰り道、金木犀のいい匂いがした。もうすっかり秋なんだなあと感じた。」というように、五感を使って季節を感じ、それを言葉にする練習にもなります。空の色、雲の形、風の強さなど、毎日少しだけ意識して周りを観察してみると、たくさんの変化が見つかるはずです。
もっと楽しくなる!小学校5年生向け日記の書き方応用編

日記の基本的な書き方に慣れてきたら、次はもっと表現を豊かにして、自分だけのオリジナルな日記を目指してみましょう。ちょっとした工夫で、日記はもっと面白く、書くこと自体が楽しくなります。ここでは、表現の幅を広げるための応用テクニックをいくつか紹介します。
五感(見た、聞いた、味わった、さわった、におった)を使って表現する
文章を生き生きとさせるためには、「五感」を意識することがとても効果的です。 五感とは、見たもの(視覚)、聞いたもの(聴覚)、味わったもの(味覚)、さわったもの(触覚)、におったもの(嗅覚)のことです。 これらを使って出来事を表現すると、読んでいる人がまるでその場にいるかのような気持ちになります。
例えば、「海に行った」という出来事を五感を使って書いてみましょう。
- 見た(視覚):太陽の光がキラキラ反射する青い海、どこまでも続く白い砂浜
- 聞いた(聴覚):ザアザアと寄せては返す波の音、カモメの鳴き声
- 味わった(味覚):お昼に食べた焼きそばのソースの味、しょっぱい海水
- さわった(触覚):足の裏で感じる砂の熱さ、冷たい水の感触
- におった(嗅覚):潮の香り、日焼け止めのにおい
これらの要素を文章に入れると、「今日は海に行った。波の音を聞きながら、しょっぱい潮の香りをかいだ。熱い砂浜を歩いて冷たい水に入った時、とても気持ちよかった。」というように、情景が目に浮かぶような表現になります。日常の出来事でも、五感をフル活用して観察してみると、新しい発見があるかもしれません。
会話文を入れてみよう!「」の使い方
日記の中に会話文を入れると、文章にリズムが生まれて読みやすくなり、その場の雰囲気がよりリアルに伝わります。 友達や家族、先生が話した言葉で印象に残っているものを、「」(かぎかっこ)を使ってそのまま書いてみましょう。
例えば、友達と面白い話をした時のことを書くなら、
「休み時間に、〇〇くんが『昨日、うちの犬が僕の靴下を隠したんだ!』と話してくれた。僕はそれを聞いて、『それはまるで、宝探しみたいだね!』と言った。二人で顔を見合わせて大笑いしてしまった。」
というように、会話を入れるとその時の楽しそうな様子がよく伝わります。
会話文を書くときは、誰が話した言葉なのかが分かるように書くのがポイントです。「〇〇くんが言った。」のように言葉の後に書いてもいいですし、「〇〇くん『こんにちは。』」のように言葉の前に名前を書いても分かりやすいです。会話を入れることで、日記がぐっと物語のようになり、読み返すのがもっと楽しくなります。
イラストやシールで飾ってみよう
文章を書くだけでなく、イラストやシールを使ってページを飾るのも、日記を楽しく続けるための素敵なアイデアです。その日の出来事に関連する簡単な絵を描いたり、お気に入りのシールを貼ったりするだけで、あなただけの特別な一冊になります。
例えば、楽しかった遠足の日記の横に、バスや動物のイラストを描いてみましょう。文字だけでは表現しきれない楽しかった気持ちが、絵を通して伝わってきます。絵を描くのが苦手でも、簡単な顔マーク(ニコニコ、しょんぼりなど)でその日の気分を表すだけでも十分です。
また、雑誌の切り抜きや、拾ったきれいな落ち葉などを貼るのも面白いでしょう。写真が好きな人は、その日に撮った写真を印刷して貼る「写真日記」もおすすめです。文字とビジュアルを組み合わせることで、後から見返したときに、より鮮明に思い出がよみがえります。日記帳を自分の好きなものでいっぱいのスクラップブックのようにしてみましょう。
交換日記やテーマ日記に挑戦してみる
一人で日記を続けるのが難しいと感じたら、友達や家族と交換日記をしてみるのも一つの手です。 交換日記は、相手に読まれることを意識するため、分かりやすく伝えようという気持ちが働き、文章力が自然と鍛えられます。 友達の面白い日記を読めば、「次はもっと面白いことを書こう!」という意欲にもつながります。
また、毎日違うテーマを決めて書く「テーマ日記」もおすすめです。 例えば、「今日の給食ベスト3」「もしも魔法が使えたら」「一番笑ったこと」など、自分でテーマを決めたり、おうちの人に出してもらったりすると、何を書くか迷わずに済みます。
他にも、毎日3つの良かったことを書く「3行日記」や、好きなことだけを書き連ねる「好きノート」など、自分に合ったスタイルを見つけることが大切です。 必ずしも毎日びっしりと書く必要はありません。 無理なく、自分が「楽しい」と思える方法を見つけて、日記と長く付き合っていきましょう。
日記の書き方が上達する!小学校5年生におすすめの練習法

日記の書き方を上達させるには、毎日少しずつでも文章を書くことに慣れていくのが一番です。いきなり長い文章を書こうとすると大変に感じてしまうので、まずは簡単な練習から始めてみましょう。ここでは、楽しみながら文章力を鍛えられる、おすすめの練習方法を3つ紹介します。
短い文から始める「一行日記」
「毎日たくさん書くのは大変…」と感じる人には、「一行日記」がぴったりです。その名の通り、その日の出来事や気持ちをたった一行で記録する方法です。 長く書かなければいけないというプレッシャーがないので、気軽に始めることができます。
例えば、
- 「今日のドッジボール、最後まで逃げ切れてヒーローみたいだった。」
- 「新しい漢字を習ったけど、画数が多くて覚えるのが大変だ。」
- 「夕焼けがオレンジと紫のグラデーションですごくきれいだった。」
このように、その日の中で一番心に残ったことを一つだけ選んで書きます。短い文章だからこそ、「どんな言葉を使えば一番気持ちが伝わるかな?」と考える良い練習になります。まずはこの一行日記を習慣にすることから始めてみましょう。続けるうちに、自然と書くことに抵抗がなくなっていき、「もう少し詳しく書きたいな」と思える日が出てくるはずです。
見たものをそのまま書く「観察日記」
文章力をつけるためには、物事をじっくりと見て、それを言葉で表現する「観察力」を鍛えることが大切です。その練習に最適なのが「観察日記」です。植物や昆虫、ペットなどを観察して、その様子をありのままに書き留めてみましょう。
例えば、教室で飼っているメダカを観察するとします。「メダカは、キラキラ光る小さなうろこに覆われている。口をパクパクさせながら、水の中をすいすいと気持ちよさそうに泳いでいる。友達がエサをあげると、すごい速さで集まってきた。」というように、見たままの様子や動きを詳しく書きます。
観察対象は生き物でなくても構いません。道端の石、自分の鉛筆、空に浮かぶ雲など、何でもOKです。時間を決めてじっくりと見て、色、形、大きさ、手触り、変化などに気づいたことをメモしてみましょう。この練習を続けることで、物事を細かく見る力がつき、日記に書く内容も具体的で深みのあるものになっていきます。
感動したことを記録する「心が動いたこと日記」
日記をより豊かなものにするためには、自分の感情に目を向けることが重要です。 「心が動いたこと日記」は、その日に「うれしい」「楽しい」「悲しい」「くやしい」「感動した」など、心が大きく動いた出来事を記録する練習です。
ただ「うれしかった」と書くのではなく、「どうしてうれしかったのか」「どれくらいうれしかったのか」を深掘りしてみましょう。「今日、図工の時間に作った作品を先生が『アイデアが面白いね』と褒めてくれた。自分の考えたことを認めてもらえた気がして、胸の中がぽかぽかと温かくなった。スキップして家に帰りたくなった。」というように、気持ちを表す言葉や、その時の体の様子などを加えると、感情がより鮮明に伝わります。
自分の心の動きに敏感になることで、自己表現力が豊かになります。 また、自分の心がどんな時に動くのかを知るきっかけにもなり、自分自身をより深く理解することにもつながります。毎日、自分の心と対話する時間を作ってみてください。
まとめ:小学校5年生だからこそできる日記の書き方で、毎日を記録しよう

この記事では、小学校5年生のみなさんが日記を楽しく書くための、様々な書き方のコツやヒントを紹介してきました。
まずは、「いつ・どこで・だれが・何をした」という基本を大切にしながら、その時の気持ちや考えたことをプラスしてみましょう。 書くネタに困ったら、学校や家庭での出来事、自分の好きなこと、ニュースや天気など、身の回りにアンテナを張ってみると、たくさんの発見があるはずです。
慣れてきたら、五感を使ったり会話文を入れたりして、表現の幅を広げてみてください。 イラストやシールで飾ったり、一行日記や観察日記のような練習法を取り入れたりするのも、楽しく続けるための良い方法です。
日記を書くことは、文章力を高めるだけでなく、日々の出来事を振り返り、自分の成長を実感できる素晴らしい活動です。 完璧な文章を目指す必要はありません。 まずは短い文章からでもいいので、自分らしい言葉で、毎日の「きらり」と光る瞬間を記録していきましょう。

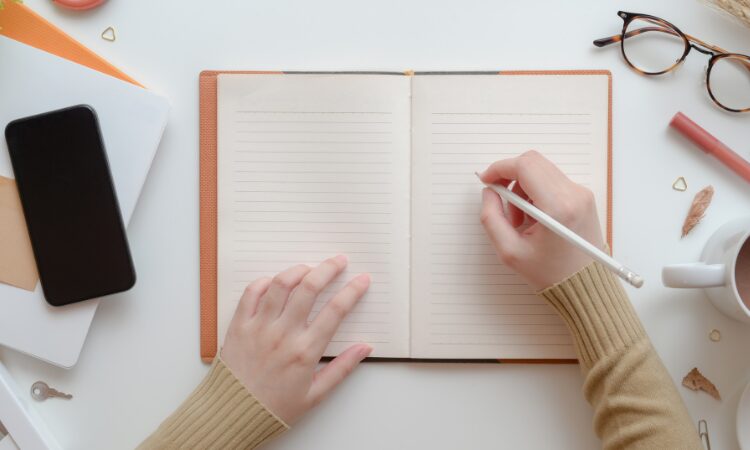


コメント