小学校6年生になると、学校の宿題で日記を書く機会が増えたり、自分の気持ちを記録として残してみたくなったりすることがあるかもしれません。しかし、「毎日何を書けばいいのかわからない」「文章をどう書けばいいのか難しい」と悩んでしまう人も少なくないでしょう。
この記事では、そんな小学校6年生のみなさんのために、日記の書き方の基本から、楽しく続けるためのコツまで、わかりやすく解説します。日記には、文章力を高めたり、自分の気持ちを整理したりと、たくさんのメリットがあります。 最初は短い文章からでも大丈夫です。 この記事を参考に、自分だけの素敵な日記作りを始めてみませんか?毎日の出来事や感じたことを言葉にして残すことで、きっと新しい発見があるはずです。
小学校6年生向け!日記の書き方の基本をおさえよう
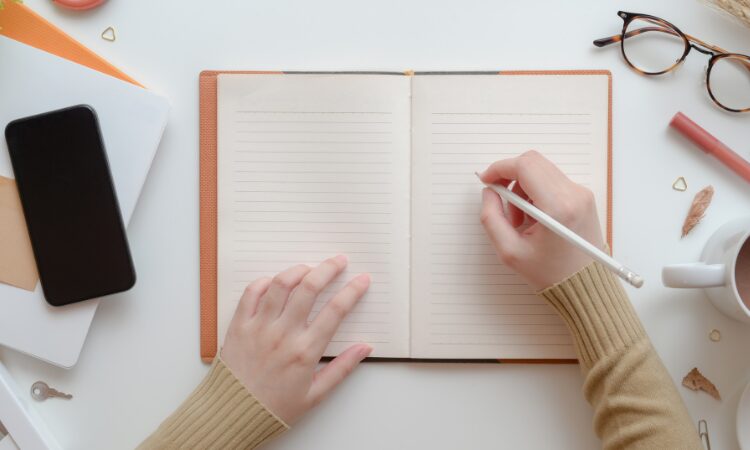
日記を書き始める前に、まずは基本的なポイントをおさえておきましょう。なぜ日記を書くのか、何を書けばいいのかを知ることで、ぐっと書きやすくなります。
なぜ日記を書くの?日記のメリット
日記を書くことには、みなさんの成長につながるたくさんのメリットがあります。
まず一つ目は、文章力や表現力が自然と身につくことです。 毎日少しずつでも文章を書く習慣をつけることで、自分の考えや出来事を言葉で表現する力が養われます。 最初はうまく書けなくても、続けるうちに使える言葉の数(語彙力)が増え、文章の組み立て方も上手になっていきます。
二つ目は、自分の気持ちを整理できることです。 楽しかったこと、悔しかったこと、不思議に思ったことなどを書き出すことで、「自分はこんなことを感じていたんだ」と客観的に自分を見つめ直すことができます。悩みを書き出すだけでも、気持ちがすっきりすることがあります。
三つ目は、大切な思い出を記録として残せることです。時間が経つと忘れてしまいがちな日々の出来事も、日記に書いておけば、後から読み返して鮮明に思い出すことができます。数年後に読み返すと、自分の成長を実感できて面白いかもしれません。 このように、日記は単なる記録ではなく、自分を成長させてくれる素晴らしいツールなのです。
何を書けばいい?日記の基本的な内容
「日記に何を書けばいいかわからない」というのは、多くの人が最初にぶつかる悩みです。そんなときは、「5W1H」を意識すると、文章の骨組みを作りやすくなります。 5W1Hとは、以下の6つの要素のことです。
- いつ(When): その出来事が起こった日時。 (例:「今日の放課後」「土曜日の午前中」)
- どこで(Where): 出来事が起こった場所。 (例:「学校の体育館で」「近所の公園で」)
- だれが(Who): 登場人物。自分だけでなく、関わった人も書きます。 (例:「クラスの〇〇さんと」「家族と」)
- なにを(What): どんなことをしたか、何が起こったか。 (例:「ドッジボールをした」「新しい本を読んだ」)
- なぜ(Why): なぜその行動をしたのか、なぜそう感じたのか。 (例:「優勝したかったから」「物語の主人公に感動したから」)
- どのように(How): どのように行動したか、どんな様子だったか。 (例:「全力でボールを投げた」「夢中になってページをめくった」)
もちろん、これらすべてを毎回無理に入れる必要はありません。 まずは「いつ、どこで、何をした」という基本的な出来事に、「どう思ったか(感想)」を加えるだけでも立派な日記になります。 大切なのは、その日一番心に残ったことを中心に書くことです。
いつ書くのがおすすめ?日記を書く時間
日記を続けるためには、いつ書くかを決めて習慣にしてしまうのがおすすめです。
例えば、夜寝る前の10分間を日記タイムにするのはどうでしょうか。一日を静かに振り返り、その日の出来事や気持ちを整理するのに最適な時間です。今日あったことを思い出しながら書くことで、記憶も定着しやすくなります。
あるいは、朝の時間に書くのも一つの方法です。前の日の出来事を少し客観的に見ながら書くことができますし、朝に頭を使うことで一日をすっきりとスタートできるかもしれません。
また、「家に帰ってきてすぐ」や「夕食の後」など、自分の生活リズムに合わせて決めるのも良いでしょう。大切なのは、「絶対にこの時間に書かなければいけない」と厳しく決めすぎないことです。「書けそうな時に書く」というくらいの軽い気持ちで始めてみましょう。もし書き忘れても、「まあ、いっか」と考えて、また次の日から書けば大丈夫です。自分にとって続けやすい時間を見つけることが、長続きの秘訣です。
【小学校6年生】日記の書き方で悩まない!ネタ探しのコツ

「毎日同じことの繰り返しで、書くことがない…」そう感じてしまう日もありますよね。でも、アンテナを少し広げてみると、日常の中には日記のネタがたくさん隠されています。ここでは、ネタ探しのコツをいくつか紹介します。
学校生活からネタを見つけよう
一日の大半を過ごす学校は、日記のネタの宝庫です。特別なイベントがなくても、毎日さまざまな出来事が起こっています。
例えば、授業中の発見について書いてみるのはどうでしょうか。「算数の授業で新しい公式を習って、難しい問題が解けてスッキリした」「理科の実験で、予想外の結果が出て驚いた」など、勉強の中で感じたことや考えたことは立派な日記のテーマになります。
休み時間や給食の時間にもネタはたくさんあります。友達とどんな話で盛り上がったか、面白い遊びをしたこと、今日の給食のメニューで好きだったものや苦手だったものについて、その理由と一緒に書いてみるのも良いでしょう。「〇〇さんの冗談が面白くて、みんなで大笑いした」といった具体的な会話や場面を書き留めておくと、後で読み返したときにその時の楽しい雰囲気がよみがえります。
普段の生活にもヒントはたくさん
学校以外の普段の生活にも、面白いネタはたくさん転がっています。
家族との会話も日記のテーマになります。「今日、お母さんと夕食の準備をしながら、学校であったことを話した」「弟とゲームで対戦して、本気で悔しがってしまった」など、何気ないやりとりの中にも、その時の自分の気持ちが表れています。
習い事やお手伝いで頑張ったこと、新しくできるようになったことを書くのもおすすめです。できなかったことができるようになった瞬間の喜びや、努力の過程を記録しておくことは、自分の自信にもつながります。
また、見たテレビ番組や読んだ本、聴いた音楽について書くのも良いでしょう。 ただ「面白かった」だけでなく、「どの場面が心に残ったか」「なぜそう感じたのか」まで一歩踏み込んで考えてみると、自分の興味や関心がどこにあるのかが見えてきます。
自分の気持ちや考えを深掘りしてみよう
日記は、単に出来事を記録するだけのものではありません。その出来事を通して自分が何を感じ、何を考えたのかを書き留めておくことが大切です。
例えば、「うれしかったこと」について書くなら、なぜうれしかったのかを考えてみましょう。「テストで良い点が取れてうれしかった」だけでなく、「毎日コツコツ勉強した努力が報われたから、達成感があってうれしかった」と書くと、より深みのある内容になります。
逆に、「悔しかったこと」や「悲しかったこと」などのネガティブな感情も、正直に書いてみましょう。 なぜ悔しかったのか、どうすれば次はうまくいくかを考えることで、次のステップへのヒントが見つかるかもしれません。日記に書き出すことで、もやもやした気持ちが整理される効果もあります。
読書やニュースからネタを広げる方法
自分の身の回りの出来事だけでなく、本やニュースで知ったことから考えを広げてみるのも、高学年ならではの日記の書き方です。
例えば、歴史の本を読んで「昔の人はこんな暮らしをしていたのか」と驚いたことや、ニュースを見て「世界ではこんな問題が起きているんだ」と考えさせられたことなどをテーマにしてみましょう。
さらに、「もし自分がその立場だったらどうするだろう?」「この問題について、自分にできることは何だろう?」というように、自分事として考えてみると、より深い内容の日記になります。このような練習は、物事を多角的に見る力を養い、自分の意見をしっかりと持つことにもつながります。日記を通して社会への関心を深めることができるなんて、少し大人になった気分がしませんか。
もっと伝わる!小学校6年生のための日記の書き方テクニック

いつもの日記に少し工夫を加えるだけで、文章がもっと生き生きとして、読み手に伝わりやすくなります。ここでは、文章表現を豊かにするためのテクニックをいくつか紹介します。国語の授業で習ったことも活かせますよ。
五感をフル活用して具体的に書こう
出来事をよりリアルに伝えるには、五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚) を使って書くのが効果的です。 「楽しかった」という一言だけでなく、その時何が見えて、どんな音が聞こえて、どんな匂いがしたかを具体的に描写してみましょう。
例えば、「給食のカレーがおいしかった」と書く代わりに、
- 見たもの(視覚): 「お皿に盛られたカレーは、つやつやした茶色で、中にはごろっとしたじゃがいもやニンジンが見えた。」
- 匂い(嗅覚): 「給食室から、スパイシーで食欲をそそる香りがしてきた。」
- 聞こえた音(聴覚): 「みんな『おいしい!』と言いながら、スプーンとお皿がカチャカチャ鳴る音が教室に響いていた。」
- 味わい(味覚): 「一口食べると、野菜の甘みと少しピリッとするスパイスの味が口いっぱいに広がった。」
と書くと、読んでいる人もまるでその場でカレーを食べているかのような気分になります。このように五感を使って書くことで、情景が目に浮かぶような、臨場感あふれる文章になります。
会話文を入れて臨場感アップ
日記の中に会話文を入れると、文章にリズムが生まれて、その場の雰囲気がより伝わりやすくなります。 誰かが言った印象的な言葉や、友達との面白いやりとりをそのまま書いてみましょう。
会話文を書くときは、カギカッコ「 」を使います。例えば、
「今日のドッジボール、すごかったね!」
と、太郎君が息を切らしながら言った。
「うん!最後の1球、まさかキャッチできるとは思わなかったよ」
と僕は興奮して答えた。
このように会話を入れることで、その時の人物の感情や関係性がよりはっきりと伝わります。誰が話しているのかわかるように書くのがポイントです。会話を思い出しながら書くことで、その時の情景も具体的に描写しやすくなるというメリットもあります。
比喩や擬人法を使ってみよう
国語の授業で習う比喩(ひゆ) や擬人法(ぎじんほう) を使ってみるのも、表現力をアップさせる良いトレーニングになります。
比喩は、「〜のようだ」「〜みたいだ」という言葉を使って、あるものを別のものにたとえる表現です。例えば、「入道雲がわたあめのように浮かんでいた」「雪のように白い肌」といった使い方をします。たとえを使うことで、物事の様子がよりイメージしやすくなります。
擬人法は、人間でないものを、まるで人間であるかのように表現する方法です。例えば、「お月様がにっこり笑っている」「風がささやく」といった表現です。これを使うと、文章がより生き生きとして、詩的な雰囲気になります。
最初は少し難しいかもしれませんが、身の回りにあるもので「これは何かに似ているかな?」と考えてみることから始めてみましょう。上手なたとえが見つかると、書くのがもっと楽しくなりますよ。
気持ちを表す言葉をたくさん知ろう
「うれしい」「楽しい」「悲しい」といった基本的な言葉だけでなく、もっと細やかな気持ちを表す言葉を使ってみましょう。 気持ちを表す言葉のレパートリーが増えると、自分の感情をより正確に、そして豊かに表現できるようになります。
例えば、「うれしい」気持ちにも色々あります。
- わくわくする(期待で胸がふくらむ気持ち)
- ほっとする(心配事がなくなって安心する気持ち)
- やったー!(達成感に満ちた気持ち)
- じーんとする(感動して胸が熱くなる気持ち)
同じように、「悲しい」にも、「しょんぼりする」「がっかりする」「切ない」など、さまざまな表現があります。どんな言葉が自分の今の気持ちにぴったりくるか、言葉を探してみるのも面白いです。国語辞典や類語辞典を使ってみるのもおすすめです。 いろいろな言葉を知って使いこなせるようになると、日記だけでなく、作文や普段の会話でも自分の思いを上手に伝えられるようになります。
小学校6年生必見!日記を楽しく続けるための書き方の工夫
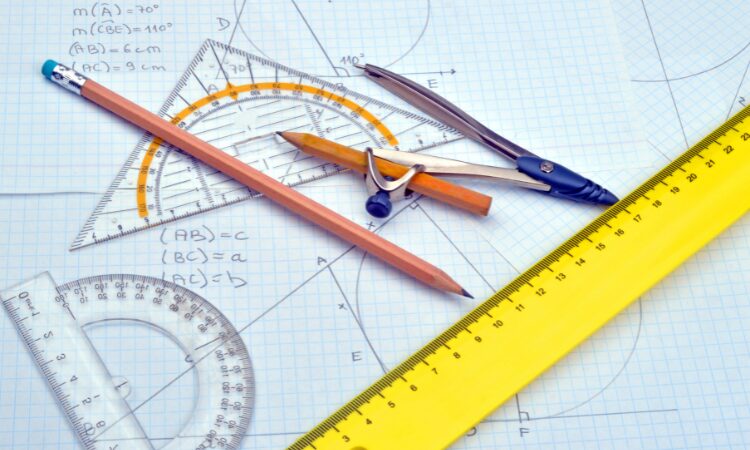
日記は、何よりも楽しく続けることが大切です。 「毎日書かなきゃ」と気負いすぎず、自分に合ったスタイルを見つけることが長続きの秘訣です。ここでは、日記を楽しむための工夫をいくつか紹介します。
毎日書かなくても大丈夫!自分ルールを作ろう
「日記は毎日書くもの」というイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうである必要はありません。 忙しい日や疲れている日に無理して書こうとすると、だんだん書くのが面倒になってしまいます。
そこで、自分だけのルールを作ってみましょう。例えば、「週に3回だけ書く」「面白いことがあった日だけ書く」「週末に一週間分をまとめて書く」など、自分が続けやすいペースで取り組むのが一番です。
大切なのは、完璧を目指さないこと。「今日は一行だけ」「単語をいくつか並べるだけ」でもOKです。 書くことへのハードルを下げて、「これなら続けられそう」と思える自分だけのスタイルを見つけてください。書くことがプレッシャーではなく、楽しみの一つになるはずです。
絵やイラスト、写真を活用しよう
文章を書くのが苦手だったり、気分が乗らない日があったりしたら、絵やイラスト、写真でその日の出来事を表現するのも素敵な方法です。
例えば、食べたケーキの絵を描いて「すごく甘くておいしかった!」と一言添えるだけでも、立派な絵日記になります。遠足で撮ったお気に入りの写真を貼って、その時の思い出を書き加えるのも良いでしょう。
文章だけでなく、ビジュアル的な要素が加わることで、日記帳がカラフルで楽しいものになります。後から見返したときにも、その日の出来事がより鮮明に思い出せます。シールを貼ったり、マスキングテープで飾り付けをしたりと、自分なりにノートをデコレーションするのも、日記を続けるモチベーションにつながります。
交換日記やブログもおすすめ
一人で黙々と書くのが続かないという人は、誰かと一緒に書くという方法もあります。
一番手軽なのは、友達や家族との交換日記です。 相手に読んでもらうことを意識するので、分かりやすく伝えようと工夫するようになりますし、相手からの返事を読むのも楽しみになります。お互いのことをより深く知るきっかけにもなるでしょう。
また、保護者の人と相談して、安全な範囲でブログを始めてみるのも一つの方法です。自分の好きなことや日々の出来事を発信し、コメントをもらうことで、書くことへの意欲がわくかもしれません。ただし、インターネット上に公開する際は、個人情報(本名、学校名、住所など)を書かない、知らない人と安易に連絡を取らないなど、家族としっかりルールを決めて安全に利用することがとても重要です。
短い文章から始めてみよう
最初から長い文章を書こうとすると、疲れてしまいます。まずは一行日記や三行日記といった、ごく短い文章から始めてみましょう。
- 一行日記: 「今日は、体育で走り高跳びの新記録が出てうれしかった。」
- 三行日記:
- (今日一番良くなかったこと・失敗したこと)算数のテストでケアレスミスをしてしまった。
- (今日一番良かったこと・感動したこと)友達が「ドンマイ!」と励ましてくれた。
- (明日の目標・考えたこと)次は見直しをしっかりしようと思った。
このように、書くことの型を決めてしまうと、悩まずに書き始められます。慣れてきて、もっと書きたいと感じるようになったら、自然と文章の量を増やしていけば良いのです。大切なのは、書くことを習慣づける第一歩を踏み出すことです。
まとめ:小学校6年生の日記の書き方をマスターして、毎日を記録しよう

この記事では、小学校6年生のみなさんが日記の書き方に悩まず、楽しく続けられるようなコツやテクニックをたくさん紹介しました。
まず、日記には文章力を高め、自分の気持ちを整理し、思い出を残せるといったたくさんのメリットがあることをお伝えしました。 何を書くかに迷ったら、「5W1H」をヒントに、その日一番心に残ったことを書いてみましょう。 ネタ探しは難しく考える必要はありません。学校生活や普段の暮らしの中に、たくさんのヒントが隠されています。
さらに、五感を使ったり、会話文を入れたり、気持ちを表す言葉を工夫したりすることで、いつもの日記がもっと生き生きとした表現になります。 そして何より大切なのは、完璧を目指さず、自分なりのスタイルで楽しむことです。 毎日書けなくても、短い文章からでも大丈夫。 絵や写真を使ったり、交換日記を試したりするのも良い方法です。
日記は、あなただけの特別な宝物になります。今日からさっそく、ペンをとって、日々の出来事や感じたことを書き留めてみませんか?




コメント