夏休みの宿題で、多くの小学生が頭を悩ませるのが「夏休みの思い出」をテーマにした作文ではないでしょうか。「何から書けばいいかわからない…」「どうやったら上手に書けるの?」そんなお悩みを抱えている人も多いはずです。
この記事では、小学生のみなさんが「夏休みの思い出」の作文を、楽しくスラスラ書けるようになるためのコツを、例文を交えながらわかりやすく解説します。作文を書く前の準備から、読んだ人が「おもしろい!」と感じる構成の作り方、そして表現力をアップさせるテクニックまで、たくさんのヒントを紹介します。この記事を読めば、あなたもきっと夏休みの素敵な思い出を、自分らしい言葉で表現できるようになりますよ。
夏休みの思い出の作文、何を書けばいい?【小学生向けテーマ探し】

夏休みの作文を書こうと思っても、まず「何について書くか」で手が止まってしまうことがありますよね。 でも、大丈夫です。特別な出来事でなくても、あなたの心に残ったことなら、何でも立派な作文のテーマになります。ここでは、テーマを見つけるためのヒントをいくつか紹介します。
まずは楽しかった出来事をリストアップしよう
まずは、夏休みにあった楽しかった出来事を、思いつくままに紙に書き出してみましょう。どんなに小さなことでも構いません。
- 家族で行った海水浴
- おじいちゃん、おばあちゃんの家に遊びに行ったこと
- 夏祭りで食べたかき氷
- 友達と公園でセミとりをしたこと
- 自由研究でがんばったこと
- 毎日続けたラジオ体操
このように、箇条書きでたくさん書き出すことで、頭の中が整理されます。 そして、リストを眺めながら、どれが一番心に残っているか、一番書きたいことは何かを考えてみましょう。 一番書きたいと思ったものが、あなたの作文のテーマになります。
心に残った「気持ち」を思い出してみよう
出来事だけでなく、その時に感じた「気持ち」を思い出してみるのも、テーマを見つける良い方法です。
- うれしかったこと: 逆上がりができるようになった、おじいちゃんに褒められた
- くやしかったこと: 欲しかったカブトムシが捕まえられなかった、友達とけんかしてしまった
- びっくりしたこと: 大きな花火の音、突然の夕立
- どきどきしたこと: 初めて一人でおつかいに行った、お化け屋敷に入った
楽しかった思い出だけでなく、くやしかったり、悲しかったりした経験も、なぜそう感じたのかを深く考えることで、他の人には書けない自分だけの作文になります。 その気持ちが一番強く動いた出来事を選ぶと、書きたいことがあふれてくるはずです。
家族や友達と話してヒントをもらおう
自分一人ではなかなか思い出せないことも、家族や友達と夏休みの出来事についておしゃべりすることで、忘れていたことを思い出したり、新しい発見があったりします。
「あの時、あんなことがあって面白かったね」「すごく大きなスイカだったよね」などと話しているうちに、「そうだ、あれを書こう!」とテーマが見つかることがあります。お父さんやお母さんに、「夏休みで一番印象に残っていることは何?」とインタビューしてみるのも良い方法です。 人と話すことで、自分では気づかなかった面白いエピソードが見つかるかもしれません。
写真や日記を見返してみよう
もし夏休みの間に撮った写真や、つけていた日記があれば、ぜひ見返してみてください。写真を見れば、その時の楽しかった場面や表情がよみがえってきます。日記を読み返せば、その日何をして、どう感じたかが詳しくわかります。
写真に写っている人の表情や周りの景色、日記に書いた言葉などから、「この時の気持ちを詳しく書きたいな」と思えるテーマが見つかることがあります。特に低学年のうちは、絵日記を書いている人も多いかもしれません。その絵を見ながら、何を描きたかったのか、どんな色が楽しそうに見えるかを考えてみるのも、作文のヒントにつながります。
【学年別】夏休みの思い出 作文の例文を紹介!

ここでは、夏休みの思い出の作文の例文を、小学校の低学年・中学年・高学年に分けて紹介します。学年によって、求められる文章のレベルや視点が少しずつ変わってきます。自分の学年に合った例文を参考に、自分ならどう書くかを考えてみましょう。
小学生【低学年】向けの作文 例文(例:海水浴)
低学年のうちは、見たことや聞いたこと、感じたことを素直に、いきいきと表現することが大切です。 難しい言葉を使わなくても、楽しかった気持ちが伝わるように書くことを意識しましょう。
題名:きらきら光る海
八月の一日、かぞくでうみへいきました。ぼくは、うみにいくのがはじめてだったので、とてもわくわくしていました。
うみは、すごくひろくて、キラキラとかがやいていました。「わあ、すごい!」とぼくはおもわずさけびました。さっそく、お父さんとうきわをもってうみにはいりました。水はすこしつめたかったけど、きもちよかったです。お父さんにおしてもらうと、うきわがプカプカうかんで、まるでふねにのっているみたいでした。
おひるごはんには、海のいえでやきそばをたべました。そとでたべるやきそばは、いつもよりずっとおいしくかんじました。そのあと、すなはまで大きな山をつくりました。おねえちゃんと二人で、バケツですなをはこんで、どんどん大きくしました。さいごにてっぺんにつうじるトンネルをほってかんせいです。とてもりっぱなおしろができて、うれしかったです。
うみであそんだ一日は、あっというまでした。かえるとき、くるまの中から見たゆうひが、うみをオレンジいろにそめていて、とてもきれいでした。また来年も、かぞくみんなでうみにいきたいです。
小学生【中学年】向けの作文 例文(例:自由研究)
中学年になると、出来事を順番に説明するだけでなく、自分がどうしてそう思ったのか、何に気づいたのかなど、少し掘り下げて書くことができるようになります。
題名:アサガオの観察日記
夏休みの自由研究で、ぼくはアサガオを育てることにしました。毎日水をあげて、いつさくかなと楽しみにしていました。
アサガオのたねは、小さくて黒いまめみたいでした。土にうめてから五日ほどで、かわいいふたばが出てきました。そのふたばが、日に日に大きくなって、つるがぐんぐんのびていく様子を見るのは、毎朝の楽しみでした。つるは、ぼくが立てたしちゅうに、くるくるとじょうずにまきついていきました。生きているんだなと実感しました。
一番心にのこっているのは、はじめて花がさいた日のことです。その日は、いつもより少し早く目がさめました。ベランダに出てみると、むらさき色の花が一つ、やさしい朝日をあびてさいていました。「さいた!」と思わず声が出ました。花びらはうすくて、やぶれてしまいそうなくらいでした。花のまん中が白色で、まるでだれかが絵の具で色をぬったみたいにきれいでした。
観察日記をつけていて、気づいたことがあります。アサガオの花は、朝早くにさいて、お昼すぎにはしぼんでしまうことです。そして、しぼんだ花のねもとから、たねができる場所がふくらんでくることも分かりました。はじめはたった一つのたねだったのに、一つの花からたくさんのたねができて、命がつながっていくのはすごいと思いました。この自由研究を通して、植物を育てる楽しさと、命のふしぎさを学ぶことができました。
小学生【高学年】向けの作文 例文(例:キャンプ)
高学年では、ただの出来事の報告で終わらせず、その経験を通して自分がどう成長したのか、何を考えたのかといった内面の変化まで書けると、より深みのある作文になります。
題名:星空の下で考えたこと
今年の夏休み、僕は初めて友達家族と一緒に二泊三日のキャンプに行きました。自然の中で過ごすことは好きでしたが、夜の森や火のおこし方など、知らないことばかりで少し不安な気持ちもありました。
キャンプ場に着いて、まず挑戦したのはテントの設営でした。説明書を読んでも、ポールをどこにさせばいいのか分からず、友達と四苦八苦しました。見かねた友達のお父さんが手伝ってくれ、ようやく僕たちの城が完成したときには、達成感でいっぱいでした。夕食のカレー作りでは、薪に火をつけるのに苦労しました。うちわであおいでも、なかなか火は大きくなりません。しかし、薪の組み方や空気の通り道を工夫することで、安定した火をおこすことができました。この経験から、何事もただやみくもにやるのではなく、仕組みを考えて工夫することの大切さを学びました。
夜になり、あたりが静かになると、空には今まで見たこともないような数の星が輝いていました。まるで黒いビロードの上に、ダイヤモンドをちりばめたようです。その星空を眺めていると、自分がとても小さな存在に感じられました。そして、いつも当たり前のように使っている電気や水道のない生活を体験したことで、僕たちの普段の暮らしがいかに多くのものに支えられているのかを実感しました。
このキャンプを通して、僕は自然の美しさや厳しさだけでなく、仲間と協力することの楽しさ、そして便利な生活への感謝の気持ちを学びました。大変なこともあったけれど、それ以上に得たものが大きい、忘れられない三日間になりました。これからの生活では、この経験で感じた感謝の気持ちを忘れずに過ごしていきたいです。
読んだ人を惹きつける!夏休みの思い出 作文の構成テクニック
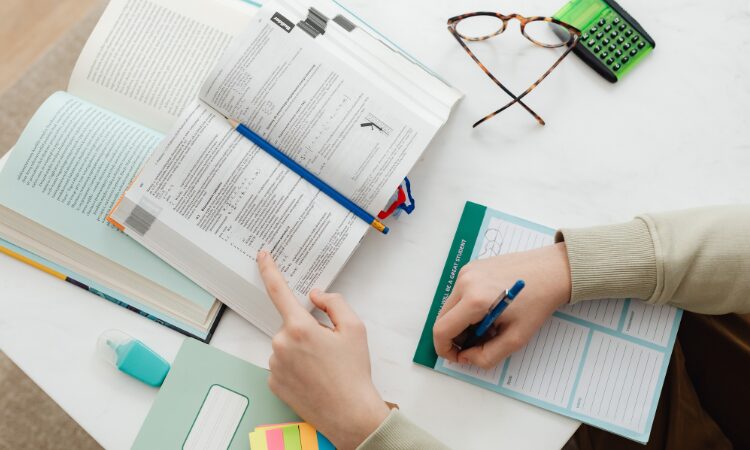
おもしろい作文には、実は「型」があります。いきなり書き始めるのではなく、まず文章の設計図である「構成」を考えると、伝えたいことがまとまり、ぐっと読みやすい文章になります。 ここでは、基本的な構成のテクニックを紹介します。
「はじめ・中・おわり」の三部構成を意識しよう
作文の基本は、「はじめ・中・おわり」の三つの部分で構成することです。 この流れを意識するだけで、文章全体がすっきりとまとまります。
- はじめ: これから何について書くのかを紹介する部分です。いつ、どこで、誰と何をしたのかを簡潔に書きます。
- 中: 作文の中心となる部分です。一番伝えたい出来事を具体的に、詳しく書きます。楽しかったこと、驚いたこと、その時の会話や自分の気持ちなどを盛り込みます。
- おわり: 作文のまとめの部分です。その経験を通して感じたことや学んだこと、これからの目標などを書きます。
この三つのブロックに、それぞれ何を書くかメモしてから書き始めると、話があちこちに飛ばず、スムーズに書き進めることができます。
「はじめ」で読者の心を掴む書き方
「はじめ」の部分は、読者が「この先を読んでみたい!」と思うかどうかを決める大切な導入部分です。
出来事をただ説明するだけでなく、一番印象に残っていることや、その時の気持ちから書き始めると、読者の興味を引くことができます。
普通の書き出し例:
「夏休みに、家族で水族館に行きました。」
読者を惹きつける書き出し例:
「目の前に現れた巨大なジンベイザメの姿に、ぼくは息をのんだ。夏休みに行った水族館での、一番の思い出だ。」
このように、一番の見どころやクライマックスの場面から書き始めたり、自分の気持ちを表す言葉を入れたりすることで、作文がより魅力的になります。
「中」で具体的なエピソードを詳しく書こう
「中」の部分は、作文で一番長くなる、いわばメインディッシュです。 ここでは、あなたが体験したことを、読者がまるでその場にいるかのように感じられるくらい、具体的に書くことがポイントです。
例えば、「楽しかった」と一言で終わらせるのではなく、なぜ、どのように楽しかったのかを詳しく書きましょう。
簡単な書き方:
「お祭りで金魚すくいをしました。楽しかったです。」
具体的な書き方:
「お祭りで一番楽しみだったのは、金魚すくいです。お店の人が持つポイは、すぐに破れてしまいそうなくらい薄くて、どきどきしました。そっと水に入れて、赤い金魚をねらいました。すくえたと思ったしゅんかん、ポイの紙が半分やぶれてしまい、『あぶない!』とあせりました。でも、なんとかおわんに入れることができて、思わず『やった!』とさけんでしまいました。」
このように、自分の行動や気持ちの動き、その時の情景を細かく描写することで、生き生きとした文章になります。
「おわり」で感想や学んだことをまとめよう
「おわり」の部分は、作文を締めくくる大切なまとめです。 ただ「楽しかったです」で終わるのではなく、その経験を通して自分がどう感じたか、何を学んだか、そしてこれからどうしたいかを書くと、作文に深みが出ます。
簡単な終わり方:
「キャンプは楽しかったです。また行きたいです。」
深みのある終わり方:
「このキャンプを通して、ぼくは自然の中で過ごす楽しさだけでなく、友達と協力することの大切さも学びました。火をおこすのは大変だったけれど、みんなで力を合わせたからこそ、おいしいカレーができたのだと思います。この経験をいかして、これからの学校生活でも、クラスのみんなと協力していきたいです。」
経験から得た教訓や、自分の成長につなげることで、読んだ人の心に残る作文になります。
もっと上手に!夏休みの思い出 作文をレベルアップさせる表現のコツ

構成がしっかりできたら、次は文章の表現を工夫してみましょう。少しのコツで、あなたの作文はもっと魅力的で、生き生きとしたものになります。いつも同じような表現になってしまう人も、ここで紹介するテクニックを使えば、表現の幅がぐっと広がります。
五感(見た・聞いた・におい・味・さわった感じ)を使おう
出来事を書くときに、「五感」を意識すると、文章がとても具体的でリアルになります。 五感とは、目(見た)、耳(聞いた)、鼻(におい)、舌(味)、肌(さわった感じ)のことです。
例えば、「花火を見ました」という一文も、五感を使うとこんなに豊かになります。
- 見た: 「夜空に、赤や緑の大きな花が咲いたように見えた。」
- 聞いた: 「『ドン!』という大きな音が、おなかにズシンとひびいた。」
- におい: 「風にのって、火薬のにおいが少しだけした。」
- さわった感じ: 「夜のむしっとした空気が、花火が上がるたびに少しだけゆれるのを感じた。」
このように、自分がその場で何を感じたかを思い出しながら書くと、読んでいる人もその場の空気を一緒に感じることができます。
会話文や心の声を入れてみよう
作文の中に、登場人物の会話や、その時の自分の心の声を入れると、文章に動きが出て、場面が想像しやすくなります。
会話文がない場合:
「弟が転んで泣き出したので、私は大丈夫かと声をかけました。」
会話文を入れた場合:
「弟が石につまずいて、大きな声で『うえーん!』と泣き出した。私はあわててかけより、『大丈夫?痛かったね』と背中をさすってあげた。」
また、その時の気持ちを「( )」を使って心の声として書くのも効果的です。
「目の前に出されたピーマンを見て、(うわー、にがそうだなあ)と思った。」
このように会話文や心の声を入れることで、文章が単調になるのを防ぎ、読者を物語の世界に引き込むことができます。
いろいろな言葉を使ってみよう(擬音語・擬態語)
「擬音語(ぎおんご)」や「擬態語(ぎたいご)」を使うと、文章がより生き生きとして、面白くなります。
- 擬音語: 物の音や動物の鳴き声などをまねた言葉。(例:ざあざあ、わんわん、ゴロゴロ)
- 擬態語: 物事の様子や状態を言葉で表したもの。(例:きらきら、ふわふわ、にこにこ)
例えば、「雨が降ってきた」という文も、
「ぽつぽつと雨が降り始め、あっという間にざあざあ降りの雨になった。」
と書くと、雨の降り方の変化がよくわかります。
「犬が走ってきた」も、
「子犬がてくてくとこちらにやってきた。」
「大きな犬がどしんどしんと走ってきた。」
と書くと、犬の大きさや様子が目に浮かぶようです。
普段の会話で使っている言葉を、ぜひ作文にも取り入れてみましょう。
ことわざや慣用句にチャレンジしてみよう(高学年向け)
高学年になったら、ことわざや慣用句(かんようく)を使ってみるのも、作文をレベルアップさせる一つの方法です。 自分の気持ちや状況にぴったりの言葉が見つかると、文章が引き締まり、表現が豊かになります。
例えば、「とても驚いた」という気持ちを表したいとき、
「カブトムシが飛んできて、とび上がるほどおどろいた。」
「とび上がるほど」は、「非常に驚く」という意味の慣用句です。
また、「努力したけれど失敗した」という状況では、
「あと一歩でゴールだったのに、転んでしまった。今までのどりょくが水のあわだ。」
「水の泡」は、「努力したことが無駄になる」という意味のことわざです。
ただし、意味を正しく理解して使うことが大切です。国語の教科書や辞書で調べて、使い方を確かめてからチャレンジしてみましょう。
【保護者の方へ】小学生の「夏休みの思い出 作文」サポートのコツ

夏休みの作文は、お子さん一人で完成させるのが難しい場合も多い宿題です。そんなとき、保護者の方がどのようにサポートすれば、お子さんのやる気を引き出し、書く力を伸ばすことができるのでしょうか。 ここでは、お子さんの作文をサポートする際のポイントをいくつか紹介します。
子どもの話をじっくり聞いてあげよう
お子さんが「何を書けばいいかわからない」と悩んでいたら、まずは夏休みの出来事について、じっくり話を聞いてあげてください。 「どこが一番楽しかった?」「その時、どんな気持ちだった?」などと質問を重ねることで、お子さん自身も自分の気持ちや考えを整理することができます。
このとき、大人が「これを書いたら?」とテーマを決めてしまうのではなく、あくまでもお子さんが話したいことを引き出すことに徹するのがポイントです。 親子で楽しくおしゃべりする時間そのものが、作文の材料集めになります。
質問で具体的なエピソードを引き出そう
お子さんの話が「楽しかった」「すごかった」だけで終わってしまう場合は、具体的なエピソードを引き出す質問をしてみましょう。
- 「その花火、どんな色だった? どんな形だった?」
- 「川の水は、さわってみてどんな感じだった? 冷たかった?」
- 「おじいちゃんは、どんな顔をして笑ってた?」
- 「『おいしい!』って言った時、どんな味がしたの?」
このように、五感を刺激するような質問をすることで、お子さんの記憶が鮮明によみがえり、作文に書くための具体的な描写が増えていきます。お子さんが話してくれたことをメモしてあげると、後で文章にする際に役立ちます。
ほめて伸ばす!子どものやる気を引き出す声かけ
お子さんが作文を書き始めたら、まずは「書こうとしている」その姿勢をたくさんほめてあげてください。特に作文が苦手なお子さんにとっては、原稿用紙に向かうだけでも勇気がいることです。
「一行でも書けてすごいね!」「その時の気持ち、よく思い出せたね」「この言葉の使い方がおもしろいね」など、小さなことでも具体的にほめることで、お子さんは自信を持って書き進めることができます。 「こう書きなさい」と指示するのではなく、「あなたはどう思ったの?」と問いかけ、お子さん自身の言葉で表現するのを見守りましょう。
間違いを直しすぎないで見守る姿勢も大切
お子さんが書いた文章を読むと、つい誤字脱字や文法の誤りなどを細かく直してしまいたくなるかもしれません。もちろん、最低限のルールを教えることは大切ですが、あまりに修正しすぎると、お子さんは書くこと自体が嫌になってしまう可能性があります。
まずは、お子さんが伝えたい内容が表現できていることを認め、ほめてあげましょう。 間違いの指摘は、一番伝えたいことが書き終わった後で、「ここの『は』を『が』にすると、もっと伝わりやすくなるかもね」というように、提案する形で優しく伝えるのが理想です。低学年のうちは特に、完璧な文章を目指すよりも、まずは「書くのって楽しい!」と思える経験をさせてあげることが何よりも大切です。
まとめ:自分だけの夏休みの思い出を作文にしよう!

この記事では、小学生のみなさんが「夏休みの思い出」の作文を書くためのテーマの見つけ方から、具体的な例文、構成のコツ、表現のテクニック、そして保護者の方のサポート方法まで、幅広く紹介しました。
作文は、特別な体験を書く必要はありません。あなたが見たこと、感じたこと、考えたことを、あなた自身の言葉で表現することが一番大切です。楽しかったこと、うれしかったこと、ちょっぴり悔しかったこと、そのすべてが、あなただけの素敵な「夏休みの思い出」です。
今回紹介したコツを参考に、まずは楽しかった出来事を思い出すことから始めてみてください。そして、「はじめ・中・おわり」の構成を意識しながら、自分の気持ちを素直に文章にしてみましょう。きっと、あなたにしか書けない、素晴らしい作文が完成するはずです。




コメント