夏休みの宿題の定番、自由研究。テーマ選びや実験・観察に夢中になるのは楽しいですが、最後のまとめ、特に「考察」で手が止まってしまう人はいませんか? 「結果は出たけど、何を書けばいいの?」「そもそも考察って何?」と悩むのは、決してあなただけではありません。考察は、自由研究の価値を大きく左右する、とても重要な部分です。実験や観察でわかった事実をもとに、自分なりに考えを深めていく作業であり、研究の面白さが一番表れるところでもあります。
この記事では、そんな自由研究の考察の書き方について、基本の構成から、学年別の例文、さらには困ったときの対処法まで、やさしく丁寧に解説していきます。この記事を読めば、考察を書くのが苦手な人も、自信を持ってスラスラ書けるようになるはずです。
そもそも自由研究の「考察」って何?

自由研究をまとめる上で、「結果」や「結論」と並んで出てくる「考察」という言葉。言葉は似ていますが、それぞれ役割が違います。まずは、考察がどのようなもので、他の項目とどう違うのかをしっかり理解することから始めましょう。
考察の役割と目的
自由研究における考察とは、「実験や観察の結果から何が言えるのか、なぜそのような結果になったのかを深く考えること」です。 つまり、ただ事実を並べるだけでなく、その事実が持つ意味を解釈し、自分の考えをまとめる部分が考察なのです。
例えば、「AとBを混ぜたらCができた」というのが「結果」だとします。それに対して、「なぜAとBを混ぜるとCができたのだろうか?」「もしかしたらAに含まれる〇〇という成分が、Bの△△という成分と反応したのかもしれない」と、結果の原因や理由を掘り下げて考えるのが「考察」です。 このように、考察は研究に深みを与え、自分だけのオリジナルの視点を加えるための重要な役割を担っています。
「結果」との違いを理解しよう
「結果」と「考察」は、自由研究のまとめで混同しやすいポイントですが、その違いは明確です。
- 結果:実験や観察をして「実際に起こったこと」や「わかった事実」をそのまま書きます。 ここでは、自分の考えや感想は入れず、客観的な事実だけを正確に記録することが大切です。例えば、「10円玉を酢に浸したら、ピカピカになった」「アサガオの種は、水に浸した方が早く芽が出た」といった、誰が見ても同じようにわかる事実が「結果」にあたります。数値を記録した場合は、表やグラフを使うと、より分かりやすくなります。
- 考察:「結果」で示された事実をもとに、「なぜそうなったのか」「この結果から何が考えられるか」を分析し、自分の考えを述べる部分です。 先ほどの例で言えば、「10円玉がピカピカになったのは、酢に含まれる酸が、10円玉の表面のサビ(酸化銅)を溶かしたからだと考えられる」と、結果の背景にある理由を探るのが「考察」です。
つまり、結果は「事実の報告」、考察は「事実の解釈」と覚えると分かりやすいでしょう。
「結論」との違いも知っておっておこう
「考察」と「結論」も、役割が異なります。「結論」は、研究全体を締めくくる部分です。
- 考察:結果を分析し、多角的に考える過程を詳しく記述する部分です。なぜその結果になったのか、予想とどう違ったのか、他の可能性はなかったかなど、考えを巡らせるプロセスそのものが考察になります。
- 結論:研究全体を通して、最終的に何がわかったのかを簡潔にまとめたものです。研究の目的で立てた問い(疑問)に対して、「〇〇ということが分かった」と明確に答える部分と言えます。考察で詳しく述べた内容の要点を、改めて整理して示すのが「結論」の役割です。
流れとしては、「結果(事実)」→「考察(分析・解釈)」→「結論(最終的なまとめ)」という順番になります。この3つの違いを意識するだけで、レポート全体がぐっと論理的で分かりやすくなります。
自由研究の考察の書き方の基本5ステップ
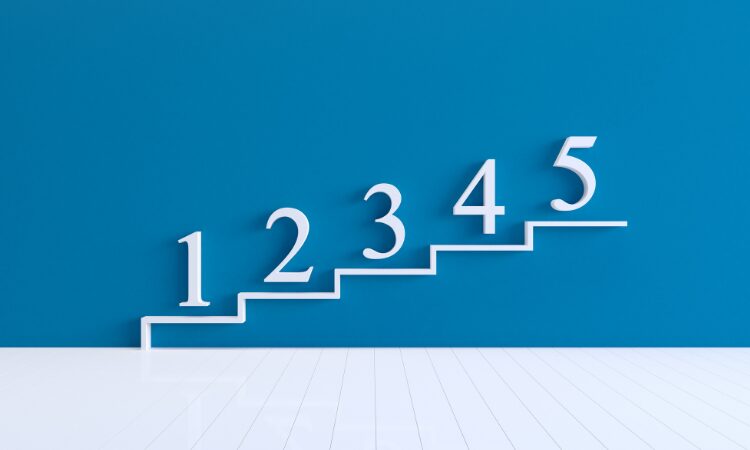
考察をいきなり書こうとすると、何から手をつけていいか分からなくなってしまいます。しかし、順番に沿って考えていけば、誰でもスムーズに考察をまとめることができます。ここでは、考察を書き進めるための基本的な5つのステップを紹介します。
ステップ1:実験・観察の結果を整理する
まずは、実験や観察で得られた「結果」を、もう一度じっくりと見直しましょう。記録したノートや写真、作成したグラフや表などを並べて、何が起こったのか、どのような変化があったのかを正確に把握します。
例えば、「植物の成長日記」であれば、「Aの鉢(日光が当たる場所)は1週間で5cm伸びたが、Bの鉢(日陰)は2cmしか伸びなかった」といった具体的な数値を再確認します。「10円玉をきれいにする実験」なら、どの液体が一番きれいになったか、どの液体は変化がなかったか、といった事実を一つひとつ整理します。
この段階では、まだ自分の考えを入れる必要はありません。客観的な事実だけを正確にリストアップしていくことが重要です。この整理された事実が、次のステップ以降で考えるための土台となります。
ステップ2:研究の「予想(仮説)」と結果を比べる
自由研究を始めるときに、「きっとこうなるだろう」という予想(仮説)を立てたはずです。 次に、その予想と、ステップ1で整理した実際の結果を比べてみましょう。
予想通りだった部分はどこでしょうか? また、予想とは違う意外な結果になった部分はありましたか?
例えば、「塩水の方が真水より早く凍るだろう」と予想していたのに、実際は「真水の方が早く凍った」という結果が出たとします。これは、予想と結果が異なった非常に興味深いポイントです。
予想と同じ結果だった場合も、「なぜ予想通りになったのか」を考えることで考察が深まります。 予想と結果を比べる作業は、「なぜ?」という疑問を見つけるための大切なステップであり、考察の中身を豊かにしてくれます。
ステップ3:結果から「何が言えるか(わかったこと)」を考える
整理した結果と、予想との比較から、「結局のところ、この研究で何が言えたのか」を考えて言葉にしてみましょう。これが考察の核となる部分です。
例えば、「日光を当てた植物と日陰の植物の成長を比べた結果」から、「植物が成長するためには日光が必要であるということが言える」といった、結果を一般化した発見を書きます。「いろいろな液体で氷の溶け方を比べた結果」からは、「砂糖や塩が混ざっている水は、真水よりも溶けにくいということがわかった」など、具体的な事実から導き出せる法則や傾向を見つけ出します。
ここでは、結果という点と点をつないで、一つの線にするようなイメージで考えてみてください。まだ難しい言葉を使う必要はありません。「〜ということがわかった」「〜という関係があるようだ」といった形で、自分なりに発見したことをまとめてみましょう。
ステップ4:「なぜそうなったのか?」原因や理由を探る
ステップ3で見つけ出した「わかったこと」に対して、「なぜ、そうなるのだろう?」と、さらに一歩踏み込んで原因や理由を考えるのが、考察で最も重要な部分です。
「植物の成長に日光が必要なのはなぜだろう?」→「植物は日光のエネルギーを使って、光合成で栄養を作っているからではないか」
「塩水が真水より溶けにくいのはなぜだろう?」→「水に何かが混ざっていると、凍る温度(凝固点)が下がるという性質があるらしい。溶けるときも同じような理由があるのかもしれない」
このように、「なぜ?」を繰り返すことで、現象の裏にある科学的な仕組みや原理に迫ることができます。すぐに答えが分からなくても大丈夫です。まずは自分なりに「こうだからじゃないか?」と考えてみることが大切です。この部分を考えるのが難しい場合は、図鑑や本、信頼できるウェブサイトなどで調べてみましょう。
ステップ5:今後の課題やさらなる疑問点を書く
最後に、今回の研究を通して新たに生まれた疑問や、次に調べてみたいことを書いて、考察を締めくくります。
例えば、「今回は日光の有無だけで比べたけれど、水の量を変えたらどうなるだろう?」「塩だけでなく、他のものを混ぜたら氷の溶け方はどう変わるだろうか?」といった、さらなる探求の可能性を示します。
また、「実験がうまくいかなかった」という反省点も、立派な考察の一部です。 「〇〇という方法ではうまくいかなかったので、次は△△という方法で試してみたい」と書くことで、研究に対する誠実な姿勢が伝わります。 このように、研究を一回で終わらせずに、次へとつなげていく視点を持つことで、自由研究全体の評価も高まります。
魅力的な自由研究にする考察の書き方のコツ
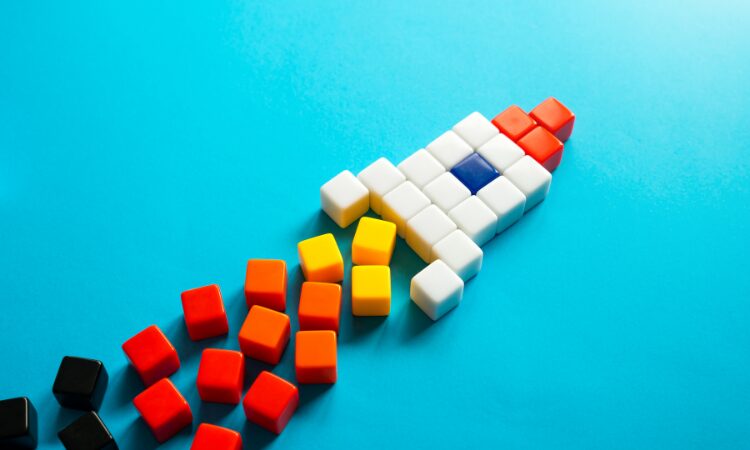
基本的なステップが分かったら、次はあなたの自由研究をさらにレベルアップさせるためのコツを紹介します。ちょっとした工夫で、考察がより分かりやすく、説得力のあるものになります。ぜひ取り入れてみてください。
グラフや図表を活用して分かりやすく
実験で多くの数値データを集めた場合、文章だけで説明しようとすると、とても分かりにくくなってしまいます。そんなときは、グラフや図、表を効果的に使いましょう。
例えば、植物の成長記録であれば、日付ごとの背丈を折れ線グラフにすると、成長の様子が一目で分かります。アンケート調査の結果は、円グラフや棒グラフにすると、割合や比較がしやすくなります。
グラフや図を使うメリットは、見た人が直感的に結果を理解できることです。考察の文章中に「(図1参照)」のように書き添えて、図と文章を連携させると、さらに説得力が増します。写真やイラストも、観察の様子や変化を伝えるのに非常に有効です。 どのグラフを使えば一番伝わるかを考えながら、工夫してまとめてみましょう。
複数の視点から多角的に考えてみる
一つの結果が出たとき、その原因を一つの理由だけで決めつけず、「もしかしたら、他の原因も考えられるのではないか?」と多角的な視点で考えてみることも大切です。
例えば、「Aの洗剤が一番汚れが落ちた」という結果が出たとします。その理由を「Aの洗浄成分が強力だから」と考えるだけでなく、「実験した日の水温が高かったからかもしれない」「使った布の種類との相性が良かったのかもしれない」というように、他の条件(要因)も検討してみましょう。
このように、いろいろな可能性を考えることで、物事を深く、そして公平に見る力が養われます。考察に「〇〇が主な原因だと考えられるが、△△という可能性も考えられる」といった一文を加えるだけで、思考の深さが伝わり、より科学的な考察になります。
参考文献や資料を引用して説得力をアップ
考察で「なぜそうなったのか」を考える際、自分の推測だけでなく、本や図鑑、信頼できるウェブサイトなどで調べた情報を根拠として示すと、考察の説得力が格段に上がります。
例えば、「10円玉が酢でピカピカになったのは、酸がサビを溶かす性質があるからだと考えられる。実際に〇〇という本にも、酸には金属の酸化物を溶かす働きがあると書かれていた」というように記述します。
このように、自分の考えを裏付ける客観的な情報を加えることで、あなたの考察が単なる感想ではなく、事実に基づいたものであることを示すことができます。ただし、どこから情報を得たのかをはっきりさせるために、レポートの最後には必ず参考にした本の名前やウェブサイトのURLを「参考文献」として記載しましょう。
失敗した実験からも考察を書くことが大切
「実験がうまくいかなかった」「予想と全く違う、変な結果になってしまった」――そんなとき、自由研究は失敗だと思いますか? そんなことはありません。実は、うまくいかなかった結果(失敗)こそ、素晴らしい考察を生む宝の山なのです。
大切なのは、「なぜ失敗したのか?」を考えることです。 「材料の混ぜる順番を間違えたのかもしれない」「温度管理がうまくできなかったからだ」「本の通りにやったのに結果が違ったのは、〇〇という条件が本とは違っていたからではないか」というように、失敗の原因を分析すること自体が、非常に価値のある科学的な探求活動です。
レポートにも、「当初は〇〇という結果を予想していたが、実際にはうまくいかなかった。その原因は△△だと考えられる。この経験から、実験では□□という点に注意することが重要だとわかった」と正直に書きましょう。成功への道のりだけでなく、失敗から学んだことも記録することで、研究の深みが増します。
【学年別】自由研究の考察の書き方と例文

考察の書き方は、学年によって求められるレベルが少しずつ変わってきます。ここでは、小学校低学年、高学年、中学生それぞれに合わせた考察の書き方のポイントと、具体的な例文を紹介します。自分の学年に合わせて参考にしてみてください。
小学校低学年向けのやさしい書き方と例文
小学校低学年のうちは、難しい言葉を使う必要は全くありません。自分が感じたことや思ったことを、素直な言葉で表現することが一番大切です。「びっくりした」「おもしろかった」といった感想も、立派な考察の第一歩です。
【ポイント】
- 「~だとおもいました」「~ということがわかりました」といった、簡単な言葉で書く。
- 実験の前と後で、どう変わったかを書く。
- 一番心に残ったことや、不思議に思ったことを中心に書く。
- 絵や写真をたくさん使って、見た人が楽しくなるように工夫する。
【例文:いろいろなものでこすって10円玉をピカピカにする実験】
けっか、お酢でこすった10円玉が、いちばんピカピカになりました。しょうゆでもすこしきれいになったけど、さとう水ではぜんぜんかわりませんでした。
こうさつ
さいしょは、どの10円玉もきたなくてちゃいろだったのに、お酢をつけたら金色にかがやいてびっくりしました。お酢はすっぱいあじがするから、そのすっぱさが10円玉のよごれをおとしたのかなとおもいました。こんどは、レモンじるでもためしてみたいです。レモンもすっぱいから、きっとピカピカになるとおもいます。おうちのそうじにもつかえるかもしれないので、お母さんにおしえてあげたいです。
小学校高学年向けのステップアップした書き方と例文
小学校高学年になったら、感想だけでなく、「なぜそうなったのか」という理由を少し意識して書けるようになると、ぐっとレベルアップします。 簡単な言葉でよいので、結果の背景にある原因を自分なりに考えてみましょう。グラフや表を使って、結果を分かりやすく整理するのもおすすめです。
【ポイント】
- 「結果」と「考察」をきちんと分けて書くことを意識する。
- 「なぜなら、~だからです」「~という理由が考えられます」といった、理由を示す言葉を使ってみる。
- 実験前の「予想」と「結果」を比べて、何が違ったのか、なぜ違ったのかを考える。
- 図鑑やインターネットで少し調べて、分かったことを自分の言葉で付け加える。
【例文:氷の溶け方の実験(真水、食塩水、砂糖水で比較)】
結果
氷がすべて溶けるまでの時間は、真水が一番早く、次に砂糖水、そして食塩水が一番遅いという結果になった。考察
予想では、どの氷も同じくらいの速さで溶けると考えていたので、こんなに差が出たことに驚きました。この結果から、水に何かが混ざっていると、溶けるのが遅くなるということが分かりました。
なぜ食塩水が一番溶けにくかったのかを考えてみました。水は0℃で凍りますが、塩が混ざることで凍る温度がもっと低くなる(凝固点降下)という性質があるそうです。それと同じように、溶けるときも真水よりも多くの熱が必要になるため、溶けるのが遅くなったのではないかと考えられます。雪が降ったときに道路にまく塩も、これと同じ原理だと知りました。次は、塩や砂糖の濃度(こさ)を変えたら、溶ける時間にさらに違いが出るのかを調べてみたいです。
中学生向けの論理的な書き方と例文
中学生になったら、より科学的で論理的な視点で考察を書くことが求められます。実験結果を客観的に分析し、専門用語も使いながら、筋道を立てて説明することを目指しましょう。複数の要因を関連付けたり、参考文献を引用したりして、考察に厚みを持たせることが重要です。
【ポイント】
- 「~と考えられる」「~と推察される」「~が示唆された」など、科学的なレポートで使われる表現に挑戦する。
- 実験結果から導き出される法則性や原理について言及する。
- 実験の精度や限界にも触れ、今後の課題を具体的に示す。
- 参考文献を明記し、自分の考えと引用した情報を区別して書く。
【例文:植物の光合成に関する実験(オオカナダモを使用)】
結果
試験管A(日光に当てたオオカナダモ)からは、多くの気泡が発生した。一方、試験管B(アルミホイルで覆ったオオカナダモ)からは、気泡の発生はほとんど見られなかった。試験管Aに溜まった気体に線香の火を近づけると、炎を上げて激しく燃えた。このことから、発生した気体は酸素であることが確認できた。考察
本実験の結果から、植物は光がある条件下でのみ気体を発生させ、その気体は酸素であることが示された。これは、植物が光エネルギーを利用して二酸化炭素と水から有機物と酸素を合成する「光合成」を行っていることを裏付けるものである。
試験管Bで気泡の発生が見られなかったのは、光が遮断されたことで光合成が行われなかったためだと考えられる。植物も呼吸を行っているため、厳密には二酸化炭素がわずかに放出されているはずだが、今回の実験ではそれを観測するには至らなかった。
今回の実験では光の有無のみを条件としたが、光の強さや波長(色)、水中の二酸化炭素濃度などを変化させた場合、酸素の発生量にどのような影響が出るのかを定量的に調査することが、今後の課題として挙げられる。
自由研究の考察で困ったときの対処法

自由研究を進めていると、思わぬ壁にぶつかることがあります。「予想と全然違う結果が出た」「実験自体がうまくいかなかった」など、困ったときにどうすれば良いのでしょうか。ここでは、そんなピンチを乗り切るための対処法をご紹介します。
予想と違う結果が出た場合
実験を始める前に立てた「予想(仮説)」と、実際の結果が大きく食い違うことはよくあります。しかし、これは失敗ではありません。むしろ、新しい発見のチャンスです。
まず、「なぜ予想と違ったのだろう?」と考えてみましょう。その原因を探るプロセスこそが、素晴らしい考察になります。 もしかしたら、あなたの予想が間違っていたのかもしれませんし、実験の条件に何か見落としがあったのかもしれません。
例えば、「ビタミンCが多いはずのレモンより、ピーマンの方が試験薬の色の変化が大きかった」という結果が出たとします。その場合、「一般的にはレモンにビタミンCが多いイメージがあったが、実はピーマンの方が含有量が多いということが分かった。これは大きな発見だった」と書くことができます。このように、予想とのギャップに注目することで、研究はより面白くなります。
うまく結果が出なかった・失敗した場合
「カビを育てる実験をしたのに、カビが生えてこなかった」「結晶を作る実験で、きれいな形にならなかった」など、期待した結果が全く得られないこともあります。そんな時でも、諦めてはいけません。「なぜ、うまくいかなかったのか」を考えることが、そのまま考察になります。
まずは、失敗した原因を正直に分析してみましょう。「温度管理が難しく、カビが生育するのに適した環境を保てなかった可能性がある」「溶液を冷やすスピードが速すぎて、大きな結晶に成長する時間がなかったのかもしれない」というように、考えられる理由をいくつか挙げてみます。
そして、「この失敗から、〇〇を成功させるためには△△という条件が重要だということが学べた。次に挑戦する機会があれば、この点を改善して再実験したい」と、次につながる学びとしてまとめましょう。失敗の記録とそこからの分析は、成功例と同じくらい価値のあるデータなのです。
何を書けばいいか全く思いつかない場合
結果を見ても、何も考えが浮かばず、考察が一行も書けない…。そんな時は、一度一人で抱え込むのをやめて、誰かに話してみるのがおすすめです。
まずは、お父さんやお母さん、学校の先生などに、「こんな実験をして、こんな結果が出たんだけど、どう思う?」と気軽に話してみましょう。自分では気づかなかった視点や、「それって、こういうことじゃない?」といったヒントをもらえるかもしれません。
また、実験で起きたことを、時系列に沿って細かく書き出してみるのも一つの手です。「最初はこうだった」「次にこうしたら、こうなった」「その時、〇〇という変化があった」と、事実を並べているうちに、結果と結果の間のつながりや、注目すべきポイントが見えてくることがあります。考え込まず、まずは手を動かしてみることも大切です。
まとめ:自由研究の考察の書き方をマスターして、研究を完成させよう!

この記事では、自由研究の要となる「考察」の書き方について、基本的な考え方から具体的なステップ、学年別の例文まで詳しく解説してきました。
考察とは、単なる感想ではなく、実験や観察で得られた「結果」をもとに、「なぜそうなったのか」「このことから何が言えるのか」を深く考える、研究の心臓部です。 「結果」や「結論」との違いをしっかり理解し、今回紹介した5つのステップに沿って考えていけば、誰でも論理的で説得力のある考察を書くことができます。
予想通りにいかなくても、失敗してしまっても、心配ありません。 その原因を探ることこそが、考察の醍醐味です。この記事で紹介したコツや困ったときの対処法を参考にして、あなただけのオリジナルな視点を見つけてください。考察をしっかりと書くことで、あなたの自由研究はただの作業記録から、価値ある一つの「研究」へと大きくステップアップするはずです。

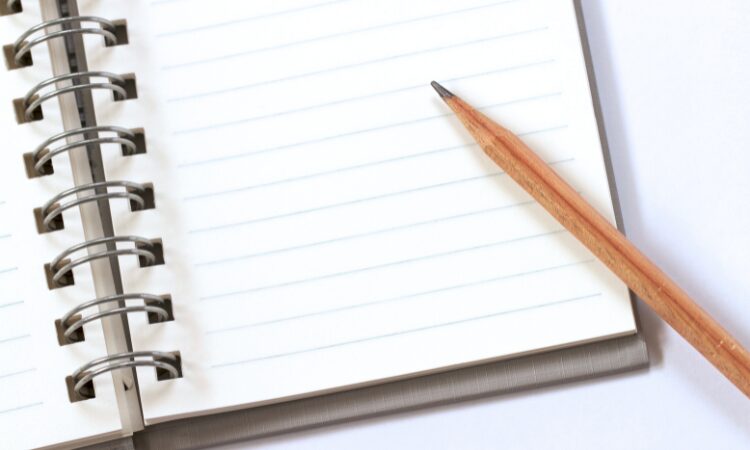


コメント