夏休みの宿題の中でも、特に手ごわいのが読書感想文ではないでしょうか。「何を書けばいいかわからない」「原稿用紙がうめられない」と、親子で頭を悩ませてしまうことも多いかもしれません。特に小学3年生になると、これまでの絵日記のような感想文とは少し違い、文章の構成や表現力も少しずつ求められるようになります。
しかし、心配はいりません。読書感想文には、誰でも上手に書けるようになる「コツ」があります。この記事では、小学3年生の読書感想文の書き方について、本の選び方から、具体的な構成の立て方、表現を豊かにする工夫まで、5つのステップに分けてやさしく解説します。この記事を読めば、お子さんが自分の力でスラスラと感想文を書けるようになり、本を読むことや文章を書くことがもっと好きになるはずです。
小学3年生の読書感想文は準備が大切!書き始める前の3ステップ
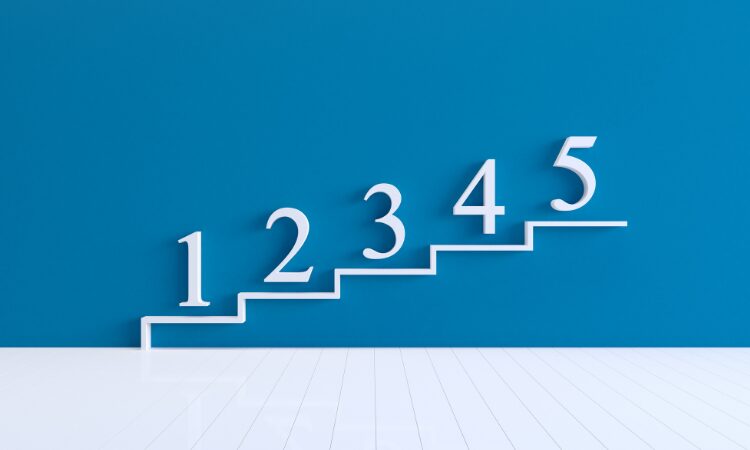
いざ原稿用紙を前にしても、すぐに書き始めるのは難しいものです。実は、スラスラと読書感想文を書くためには、本を読んでいる時からの準備がとても重要になります。ここでは、本格的に書き始める前にやっておきたい3つの準備ステップをご紹介します。
ステップ1:感想文が書きやすい本を選ぼう
読書感想文の成功は、本選びから始まっていると言っても過言ではありません。 大人が読んでほしい本ではなく、お子さん自身が「読みたい!」と心から思える本を選ぶことが一番のポイントです。 興味を持って夢中で読める本なら、自然と感じることも多くなり、感想文の材料がたくさん見つかります。
小学3年生の場合、物語のページ数が100ページ程度の児童文学などがおすすめです。 主人公が同年代の物語は、自分と重ね合わせやすく、気持ちを想像しやすいでしょう。 また、少し不思議なファンタジーの世界や、ドキドキハラハラする冒険の物語も、想像力をかき立てられるので感想文に適しています。昔から読みつがれている世界の名作も、ストーリーが分かりやすく、共感できるポイントが多いのでおすすめです。
ステップ2:心が動いたところに「ふせん」を貼ろう
本を読みながら、少しでも「おもしろい!」「すごいな」「なんでだろう?」と心が動いたページにふせんを貼っていく方法がとても効果的です。 ふせんを貼ることで、後から感想文に書く内容を探しやすくなります。
例えば、以下のようなポイントにふせんを貼ってみましょう。
- 一番おもしろかった場面
- 登場人物の素敵なセリフ
- びっくりした出来事
- 悲しくなった、または嬉しくなった場面
- 自分も同じような経験をしたことがあると感じた部分
保護者の方は、「どの登場人物が好き?」「どうしてそう思ったのかな?」などと質問を投げかけて、お子さんが自分の気持ちに気づく手助けをしてあげると良いでしょう。
ステップ3:何を書くか「感想マップ」で整理しよう
本を読み終え、ふせんを貼り終わったら、いきなり文章を書き始めるのではなく、まずは何を書くかを整理しましょう。大きな紙やノートの中心に本の題名を書き、そこから線(枝)を伸ばして、ふせんを貼った部分の内容や、その時に感じた気持ちを自由に書き出していく「感想マップ」を作るのがおすすめです。
例えば、「主人公の勇気がすごい」という枝の先に、「自分だったらあんなことできない」「どうして勇気を出せたんだろう」と書き加えたり、「悲しい場面」という枝の先に、「胸がぎゅっとなった」「友達とけんかした時のことを思い出した」と自分の経験を書き加えたりします。このように、頭の中にある考えを「見える化」することで、文章の組み立てがとても楽になります。
これで迷わない!小学3年生向け読書感想文の書き方の基本構成

感想マップで材料が集まったら、いよいよ文章を組み立てていきます。読書感想文は、大きく分けて「はじめ」「なか」「おわり」の3つの部分で構成すると、まとまりのある文章になります。 ここでは、それぞれの部分で何を書けばよいのかを具体的に解説します。
はじめ:本の紹介と、なぜこの本を選んだのか
読書感想文の書き出しである「はじめ」の部分では、主に2つのことを書きます。
- 本の題名と、簡単な紹介
- その本を読んでみようと思ったきっかけや理由
難しく考える必要はありません。「わたしが読んだ本は『〇〇』です」と書き始めたら、次に「なぜこの本を手に取ったのか」を書いてみましょう。きっかけは、「表紙の絵がきれいだったから」「題名がおもしろそうだったから」「友達にすすめられたから」など、正直な理由で大丈夫です。 例えば、「図書館でこの本の背表紙がキラキラして見えて、どんなお話なのかワクワクして読んでみたくなりました」のように書くと、自分だけのオリジナルの書き出しになります。
なか①:心に残ったあらすじ
「なか」の部分は感想文の中心です。まず、本のあらすじを短くまとめます。 ただし、物語のすべてを説明する必要はありません。特に自分の心が動いた場面、つまりふせんをたくさん貼った場面を中心に説明するのがコツです。
「この物語は、〇〇という主人公が、△△を目指して冒険するお話です」といった簡単な紹介から始め、一番印象に残った出来事を少し詳しく書きます。「特に心に残っているのは、主人公が大きな困難に立ち向かう場面です。なぜなら~」と続けることで、感想につなげやすくなります。あらすじが長くなりすぎないように注意し、感想を書くための準備と捉えましょう。
なか②:一番心に残った場面と自分の感想
あらすじを紹介したら、いよいよ一番伝えたい感想を書きます。「なか」で最も重要な部分です。 ふせんを貼った箇所や感想マップを見ながら、一番心が動いた場面について、「なぜそう感じたのか」を深掘りしていきましょう。
例えば、「主人公の〇〇が言った『あきらめない』というセリフに感動しました」と書くだけでなく、「なぜなら、ぼくも苦手な逆上がりの練習をしていた時、何度もあきらめそうになったからです。でも、このセリフを読んで、もう少し頑張ってみようという勇気をもらいました」というように、自分の経験や気持ちと結びつけると、ぐっと深みのある感想になります。 登場人物の気持ちを想像したり、「もし自分だったらどうするかな?」と考えてみるのも良い方法です。
おわり:本を読んで考えたことと、これからの自分
最後の「おわり」の部分では、読書感想文全体のまとめをします。本を読み終えて、自分がどう成長したか、これからどうしたいかを書くことで、きれいに締めくくることができます。
例えば、以下のような視点で書いてみましょう。
- 本を読む前と後で、自分の考え方がどう変わったか
- 主人公の素敵なところを真似して、これからどんなことに挑戦したいか
- この本を読んで学んだ一番大切なこと
「この本を読んで、友達と仲良くすることの大切さを改めて感じました。これからは、もっと友達の気持ちを考えて行動したいです」や、「主人公のように、失敗を恐れずに新しいことにチャレンジする人になりたいと思いました」といった、未来に向けた前向きな言葉で終われると、とても良い読書感想文になります。
もっとすごい読書感想文にする書き方のコツ

基本的な構成がわかったら、次は他の人とは一味違う、自分らしい読書感想文にするための工夫をしてみましょう。少しのコツで、文章が生き生きと輝き始めます。
表現を豊かにする言葉を使ってみよう
「おもしろかったです」「すごかったです」という言葉ばかりを使っていませんか? 自分の気持ちを表す言葉はたくさんあります。例えば、「おもしろい」なら「ハラハラドキドキした」「思わずにっこりしてしまった」「次のページをめくるのが待ちきれなかった」のように、具体的な情景が目に浮かぶような言葉を探してみましょう。
また、登場人物の会話や、心に残ったセリフを「」を使って文章に入れると、臨場感が出ます。 物語の中の音やにおい、景色などを想像して、「ビュービューと風がうなる音が聞こえてくるようでした」のように五感を使った表現を入れるのも効果的です。
自分の体験と物語を重ねてみよう
読書感想文で一番大切なのは、「自分だけの考えや気持ち」を書くことです。物語の出来事と、自分の実際の経験を重ね合わせることで、感想に説得力が生まれます。
例えば、主人公が友達とけんかする場面を読んだら、「わたしもこの前、ささいなことで友達とけんかしてしまった時のことを思い出しました。主人公と同じように、なかなか『ごめんね』が言えなくて、悲しい気持ちになりました」と書いてみましょう。自分の体験を書くことで、本の世界がより身近なものになり、読んでいる人にも気持ちが伝わりやすくなります。
魅力的なタイトルを考えてみよう
読書感想文のタイトルは、「『〇〇』を読んで」だけでも間違いではありませんが、少し工夫すると、読む人の興味をぐっと引くことができます。 タイトルは、感想文をすべて書き終えてから考えるのがおすすめです。
自分がその本を読んで一番伝えたかったことや、一番心に残った言葉をタイトルにしてみましょう。例えば、「勇気を出した一言」や「ぼくが見つけた宝物」のように、物語の内容と自分の感想を組み合わせたタイトルにすると、オリジナリティあふれる素敵なタイトルになります。
小学3年生の読書感想文が書きやすい!おすすめの本の種類

どんな本を選べばいいか迷ってしまう人のために、小学3年生が感想文を書きやすい本のジャンルをいくつかご紹介します。本屋や図書館で本を選ぶ際の参考にしてください。
主人公に共感しやすい物語
主人公が自分と同じくらいの年齢だったり、似たような悩みを持っていたりする物語は、感情移入しやすく、感想文が書きやすいです。 学校生活を舞台にした話や、友達との友情、家族との関わりを描いた作品は、自分の経験と重ね合わせやすいポイントがたくさん見つかるでしょう。 苦手なことに挑戦して乗り越えていく主人公の姿に、自分を重ねて感想を書くのも良い方法です。
ドキドキワクワクする冒険・ファンタジー
現実とは少し違う、不思議な世界を冒険する物語やファンタジーも、小学3年生の豊かな想像力を刺激します。 「もし自分がこんな世界に行ったらどうするだろう?」「こんな魔法が使えたら何をするかな?」と、自由に考えを広げることができます。物語の結末を読んで、「自分だったらこんな結末にしてみたい」と想像を膨らませて書くのも面白いでしょう。
新しいことを知れるノンフィクション・伝記
物語だけでなく、動物や科学、歴史上の人物についてのノンフィクションや伝記も、読書感想文の題材になります。本を読んで新しく知ったことや驚いたことを中心に、「この本を読むまで〇〇だと思っていたけれど、本当は△△だと知って驚きました」と書きます。そこからさらに、「なぜそうなるのかもっと知りたくなった」「この人のこんなところがすごいと思った」と、自分の興味や考えを深めていくと、立派な感想文になります。
小学3年生の読書感想文は書き方のコツをつかめば大丈夫!

今回は、小学3年生の読書感想文の書き方について、準備から構成、表現のコツまで詳しく解説しました。
読書感想文を書く上で大切なのは、上手な文章を書くことよりも、本を読んで感じた自分だけの気持ちを素直に表現することです。まずは、本選びを楽しみ、ふせんを貼りながらワクワクした気持ちで本を読み進めることから始めてみてください。そして、「はじめ・なか・おわり」という基本的な構成に沿って、自分の言葉で一つひとつ丁寧に文章を組み立てていけば、必ず素敵な読書感想文が完成します。
この記事で紹介したステップやコツを参考に、ぜひ親子で楽しく読書感想文に取り組んでみてください。文章を書くことの楽しさを発見する、素晴らしいきっかけになるはずです。




コメント