6年間の小学校生活も、もうすぐ終わり。卒業に向けて、楽しかった思い出や未来への希望を「卒業文集」にまとめる時期がやってきました。 でも、「何を書けばいいかわからない」「どうやって書いたらいいの?」と、原稿用紙を前に悩んでしまう人も多いのではないでしょうか。
卒業文集は、小学校生活で学んだことの集大成であり、未来の自分や友達、家族に向けた大切なメッセージです。 上手に書くことよりも、あなた自身の言葉で、素直な気持ちを表現することが何よりも大切です。この記事では、テーマの決め方から、読みやすい構成の作り方、そして具体的な例文まで、小学生の皆さんが卒業文集をスムーズに書けるようになるための書き方のコツを、やさしくわかりやすく解説します。
この記事を読めば、あなたもきっと、自分らしい素敵な卒業文集が書けるようになります。さあ、一緒に6年間の宝物のような思い出を、未来に残る言葉にしていきましょう。
小学生の卒業文集、何を書けばいい?~テーマを見つけよう~

卒業文集を書くにあたって、まずはじめに決めるのが「テーマ」です。 テーマとは、文章の中心となる話題のこと。テーマが決まれば、何について書けばよいかがはっきりして、ぐっと書きやすくなります。 難しく考えすぎず、あなたの心が一番動いた出来事を選んでみましょう。
一番心に残っている思い出を振り返る
6年間の小学校生活には、たくさんの思い出があふれています。 入学式、運動会、音楽会、修学旅行など、楽しかった学校行事を思い返してみましょう。 クラスのみんなと協力して何かを成し遂げたこと、友達と笑い合った休み時間、時にはケンカしてしまったことなど、一つ一つの出来事があなたを成長させてくれたはずです。
「どの思い出が一番心に残っているかな?」「そのとき、どんな気持ちだったかな?」と自分に問いかけてみてください。楽しかった、うれしかった、悔しかった、感動した…そんな素直な気持ちを思い出してみることが、あなたらしい文章を書く第一歩になります。特に印象に残っているエピソードを3〜5つほど選んで書き出すと、文章の材料が集めやすくなりますよ。
将来の夢や目標について考える
「将来、どんな大人になりたいかな?」と考えてみるのも、卒業文集の素敵なテーマの一つです。 プロ野球選手やケーキ屋さん、ゲームクリエイター、先生など、具体的な職業を思い浮かべるのも良いでしょう。 その夢を持つようになったきっかけや、その夢を叶えるためにこれからどんなことを頑張りたいかを書くと、より内容の濃い文章になります。
まだ具体的な夢が決まっていなくても大丈夫です。 「人を笑顔にできる人になりたい」「困っている人を助けたい」といった、どんな人になりたいかという視点で考えてみるのもおすすめです。 中学生になったら挑戦してみたいことや、部活動への期待などを書くのも良いでしょう。 未来に目を向けることで、希望に満ちた前向きな文章になります。
感謝の気持ちを伝えたい人へ
この6年間、あなたを支えてくれた人たちのことを思い出してみましょう。いつも一緒に笑ったり、励まし合ったりした友達。 優しく勉強を教えてくれたり、時には厳しく叱ってくれたりした先生。 そして、毎日おいしいご飯を作ってくれたり、一番近くで応援してくれたりしたお父さんやお母さん、家族。
たくさんの人に支えられて、今のあなたがいるはずです。 卒業という節目に、普段はなかなか言えない「ありがとう」の気持ちを文章で伝えてみませんか?「〇〇さんとの△△の出来事が心に残っています」「先生のあの言葉がうれしかったです」のように、具体的なエピソードを交えながら感謝の気持ちを綴ると、読んだ人の心に温かい気持ちが広がります。
好きなことや得意なことを深掘りする
あなたが夢中になっていることは何ですか? サッカーや野球などのスポーツ、ピアノや絵を描くこと、本を読むこと、ゲームをすることなど、自分の「好き」や「得意」をテーマにするのも、とてもあなたらしい文章になります。
いつからそれが好きなのか、どんなところに魅力を感じるのか、それを通して何を学んだのかなどを書いてみましょう。例えば、「サッカーを通して、仲間と協力することの大切さを学びました」のように、好きなことから学んだことを書くと、あなたの成長が伝わる素敵な文章になります。自分の好きなことについて書くのは、きっと楽しくて筆が進むはずです。難しく考えずに、あなたの「好き」という気持ちをストレートに表現してみましょう。
読みやすい!小学生卒業文集の基本的な書き方(構成)
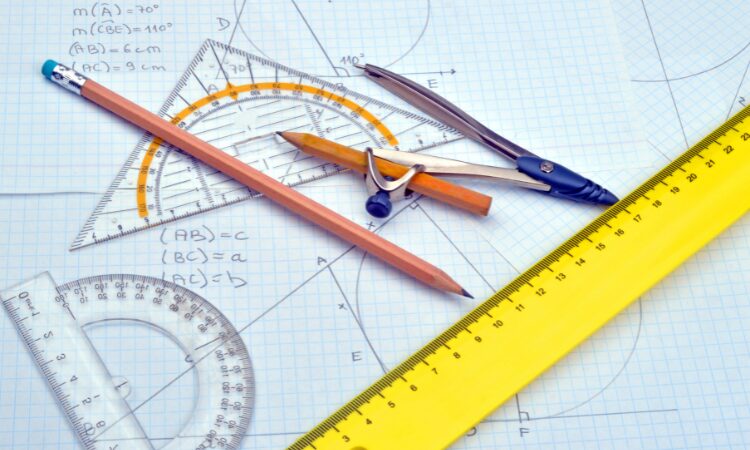
書きたいテーマが決まったら、次はどうやって文章を組み立てていくか、その「構成」を考えましょう。構成とは、文章の設計図のようなものです。 「はじめ」「なか」「おわり」の3つのブロックに分けて考えると、話の流れがスムーズになり、読んでいる人にも内容が伝わりやすくなります。
はじめ:書き出しで読者の心をつかむ
「はじめ」の部分は、文章の導入部分です。ここで、これから何について書くのかを読者に伝えます。 いきなり本題に入るのではなく、「6年間の小学校生活を振り返って、一番心に残っているのは〇〇です」や「私の将来の夢は〇〇になることです」のように、文章全体のテーマを簡潔に紹介すると良いでしょう。
例えば、「もうすぐ小学校を卒業すると思うと、たくさんの思い出がよみがえってきます」 といった、卒業を控えた今の気持ちから書き始めるのも一つの方法です。書き出しは、読者が「この先を読んでみたい」と思えるような、大切な部分です。あまり長くならず、2〜3行程度でまとめるのがポイントです。自分らしい言葉で、文章のスタートを切りましょう。
なか:具体的なエピソードで内容を豊かに
「なか」は、文章の中心となる最も大切な部分です。 「はじめ」で紹介したテーマについて、具体的なエピソードを交えながら詳しく書いていきます。 ここで大切なのは、「何があったか」という事実だけを書くのではなく、「その時どう感じたか」「何を考えたか」という自分の気持ちを詳しく書くことです。
例えば、運動会の思い出について書くなら、「リレーで一位になりました」という事実だけでなく、「練習ではうまくいかなかったけど、本番でみんなと心を一つにバトンをつなげた時、胸が熱くなりました。アンカーがゴールテープを切った瞬間は、今までで一番うれしかったです」のように、その時の情景や感情を生き生きと描くことで、読んでいる人もその場にいるかのような気持ちになります。一番伝えたいことを、この「なか」の部分でたっぷり表現しましょう。
おわり:感謝の言葉と未来への抱負で締めくくる
「おわり」は、文章のまとめの部分です。 これまで書いてきた内容を振り返り、文章全体を締めくくります。お世話になった先生や友達、家族への感謝の言葉を入れると、温かい気持ちが伝わる締めくくりになります。 「この6年間、支えてくれたすべての人に感謝しています」といった一文を加えてみましょう。
そして、中学校生活への期待や将来の夢に向けた決意表明で締めると、未来への希望を感じさせる前向きな印象になります。 「小学校で学んだことを忘れずに、中学校でも勉強や部活動を頑張りたいです」 や「夢を叶えるために、これからも努力を続けていきます」といった言葉で、力強く文章を終えましょう。最後の部分は長々と書かず、数行で簡潔にまとめるのがポイントです。
【テーマ別】小学生卒業文集の例文を見てみよう

ここでは、テーマ別に卒業文集の例文を紹介します。作文の文字数は、学校によって400字詰め原稿用紙1枚から4枚程度と様々です。 これから紹介する例文を参考に、自分らしいエピソードや言葉に置き換えて、オリジナルの文章を考えてみましょう。
例文①:運動会や修学旅行など学校行事の思い出
タイトル:最高の思い出、最後の運動会
六年間で一番心に残っているのは、小学校最後の運動会です。特に、クラス全員で心を一つにした組体操は、忘れられない思い出です。
練習が始まった頃、僕たちのクラスはなかなか技を成功させることができませんでした。何度も崩れてしまい、悔しい思いをしました。でも、休み時間もみんなで集まって、「こうすればうまくいくんじゃない?」「もう少しタイミングを合わせよう」と声をかけ合い、練習を重ねました。先生も、僕たちの自主練習に最後まで付き合ってくれました。
そして迎えた本番。たくさんの人の前で技が一つひとつ決まるたびに、大きな拍手が聞こえてきました。最後の大きなピラミッドが完成した瞬間、僕は感動で胸がいっぱいになりました。みんなで支え合い、一つの目標に向かって努力することの素晴らしさを、この組体操を通して学びました。
この経験は、僕にとって大きな宝物です。支えてくれた先生、そして最高の仲間たちに「ありがとう」と伝えたいです。中学校でも、この経験を忘れずに、仲間と協力することを大切にしていきたいです。
例文②:クラブ活動や委員会活動で頑張ったこと
タイトル:放送委員として学んだこと
私は五年生と六年生の二年間、放送委員として活動しました。お昼の放送を担当し、みんなが給食の時間を楽しめるように、音楽を流したり、クイズを出したりしました。
最初は人前で話すのが苦手で、マイクの前に立つと声が震えてしまいました。しかし、委員会の仲間が「大丈夫だよ」「一緒に練習しよう」と励ましてくれたおかげで、少しずつ自信を持って話せるようになりました。どうすればみんなが聞きやすい放送になるかを考え、話すスピードを工夫したり、はっきりとした声で話す練習をしたりしました。
六年生の時には、運動会の放送も担当しました。各種目の紹介や結果発表など、責任のある仕事でとても緊張しましたが、無事にやり遂げた時には大きな達成感を感じました。放送を聞いた友達から「今日の放送、良かったよ」と言ってもらえた時が、一番うれしかったです。
この二年間、放送委員の活動を通して、責任感と仲間と協力することの大切さを学びました。この経験を活かして、中学校でも積極的にいろいろなことに挑戦していきたいです。
例文③:将来の夢について
タイトル:笑顔を届けるパン屋さん
私の将来の夢は、パン屋さんになることです。この夢を持ったきっかけは、小さい頃にお母さんと一緒に作ったパンが、とてもおいしくできたことです。自分が作ったパンを家族がおいしそうに食べてくれた時の、うれしい気持ちが今でも忘れられません。
私が作りたいのは、ただおいしいだけでなく、食べた人が笑顔になれるようなパンです。そのためには、パン作りの技術はもちろん、お客さんがどんなパンを求めているのかを考える気持ちも大切だと思います。小学校の家庭科の授業で調理実習をした時、みんなで協力して料理を完成させる楽しさを知りました。将来は、仲間と一緒に新しいパンを開発したり、お客さんの声を聞いたりして、たくさんの人に喜んでもらえるお店を作りたいです。
夢を叶えるために、これからもっとたくさんのパンを作って練習したり、いろいろなお店のパンを食べて研究したりしたいです。そして、中学校では技術・家庭科の授業を特に頑張りたいです。人を笑顔にするという夢に向かって、一歩一歩努力を続けていきます。
例文④:友達や先生、家族への感謝の気持ち
タイトル:たくさんの「ありがとう」を込めて
六年間、私の小学校生活はたくさんの人に支えられていました。まず、いつも一緒にいてくれた友達。休み時間にくだらない話で笑い合ったり、分からない問題を教え合ったり、時にはケンカもしたけど、どんな時も隣にはみんながいてくれました。みんなと過ごした毎日は、私の宝物です。
そして、私たちを温かく見守ってくださった先生方。私が失敗して落ち込んでいる時、優しく声をかけて励ましてくれました。先生の「大丈夫、次があるよ」という言葉に、何度も助けられました。勉強だけでなく、人として大切なことをたくさん教えていただき、本当にありがとうございました。
最後に、一番近くで支えてくれた家族へ。毎朝早く起きてお弁当を作ってくれたり、どんな時も私の味方でいてくれたり、感謝の気持ちでいっぱいです。なかなか素直に言えないけど、いつも本当にありがとう。
たくさんの人に支えられて、私はこの小学校を卒業することができます。ここで出会ったすべての人への感謝の気持ちを忘れずに、中学生になっても自分らしく頑張ります。
もっと素敵になる!卒業文集の書き方のコツ

基本的な書き方をマスターしたら、次はあなたの文章をもっと魅力的にするためのコツを紹介します。ちょっとした工夫で、読んだ人の心に深く残る文章になりますよ。
具体的なエピソードを盛り込む
文章をより面白く、説得力のあるものにするためには、具体的なエピソードを入れることがとても重要です。 例えば、「友達と仲良くしました」と書くだけでなく、「私が転んでケガをした時、友達の〇〇さんがすぐに保健室に連れて行ってくれて、ずっとそばにいてくれました。その優しさがとてもうれしかったです」のように、実際にあった出来事を書くことで、情景が目に浮かび、あなたの気持ちがより深く伝わります。
楽しかったこと、悔しかったこと、感動したことなど、あなたの感情が大きく動いた場面を思い出してみてください。その時に「誰が」「どこで」「何をして」「どう思ったか」を詳しく書くことで、文章にリアリティが生まれます。
自分の気持ちや考えを素直に表現する
卒業文集は、上手に書くことよりも、あなたの本当の気持ちを伝えることが大切です。 「こんなことを書いたら変に思われるかな?」などと心配せず、思ったことや感じたことを素直に言葉にしてみましょう。
例えば、失敗した経験について書く場合でも、「悔しかったけれど、その失敗からあきらめないことの大切さを学びました」のように、その経験を通して自分がどう成長できたかを書くことで、前向きなメッセージになります。 飾らない、あなた自身の言葉で綴られた文章は、きっと読む人の心に響くはずです。
五感を使った表現を取り入れる
文章をより生き生きとさせるために、「五感」を使った表現を取り入れてみましょう。五感とは、見る(視覚)、聞く(聴覚)、味わう(味覚)、嗅ぐ(嗅覚)、触る(触覚)のことです。
例えば、運動会の場面で「大きな歓声がグラウンドに響き渡り、火薬のにおいがした」と書けば、その場の臨場感が伝わります。修学旅行の食事の場面で「みんなで食べたカレーは、いつもよりずっとおいしく感じた」と書けば、楽しかった気持ちが伝わります。このように、五感を使った表現を入れることで、読者はあなたが体験したことをより鮮明にイメージすることができます。
書く前に構成メモを作ろう
いきなり原稿用紙に書き始めるのではなく、まずは構成メモを作ることをおすすめします。 これは、文章の設計図を簡単にかたちにする作業です。
まず、中心となるテーマを決めます。次に、「はじめ」「なか」「おわり」のそれぞれのブロックに、どんな内容(特にどんなエピソード)を入れたいかを箇条書きで書き出してみましょう。 例えば、テーマが「修学旅行」なら、「はじめ:修学旅行が一番の思い出」「なか:①友達と見た夜景の美しさ ②班行動で道に迷ったハプニング ③そこで感じた友情」「おわり:感謝と中学への抱負」といった具合です。このメモに沿って書いていくことで、話が脱線することなく、まとまりのある文章をスムーズに書くことができます。
保護者の方へ:お子さんの卒業文集のサポート方法

お子さんが卒業文集に取り組む姿を、保護者としてどうサポートすれば良いか悩むこともあるかと思います。 主役はあくまでもお子さん自身ですが、少しのきっかけ作りで、お子さんが本来の力を発揮できるよう手助けすることができます。
無理に書かせず、まずは話を聞く
「早く書きなさい」と急かすのではなく、まずはお子さんの気持ちに寄り添ってあげてください。 「何を書こうか悩んでいるの?」と優しく声をかけ、小学校生活の思い出について一緒に話す時間を持つのも良いでしょう。
保護者の方が「運動会の時、リレーの選手に選ばれて頑張っていたね」「一年生の時、こんなことがあったよね」と具体的な出来事を話してあげることで、お子さん自身も忘れていた記憶がよみがえり、書く内容のヒントが見つかることがあります。楽しかった思い出を語り合う中で、お子さんの表情が輝いた瞬間が、まさに文集に書くべきテーマかもしれません。
アイデアを引き出す質問をしてみる
お子さんが何を書くか決めかねている時は、ヒントになるような質問を投げかけてみましょう。 例えば、「6年間で一番楽しかったことは何?」「一番頑張ったなと思うことは?」「誰に一番『ありがとう』って伝えたい?」といった質問です。
また、「中学校に入ったら、どんなことをしてみたい?」と未来に目を向けさせる質問も、将来の夢や目標について考えるきっかけになります。 保護者の方が聞き役になることで、お子さんの頭の中にある漠然とした思いが整理され、文章にしたい内容が明確になっていきます。答えを教えるのではなく、あくまでお子さんの中から答えを引き出す手助けをしてあげることが大切です。
誤字脱字のチェックは一緒に
お子さんが文章を書き終えたら、誤字脱字や文章のねじれがないか、一緒に確認してあげましょう。 ただし、内容について「こうした方が良い」と大きく手を入れるのは避けましょう。卒業文集は、お子さん自身の言葉で書かれていることに価値があります。
文章を声に出して読んでみるのも良い方法です。読んでいてつっかえる部分や、意味が分かりにくい部分があれば、「ここは、どういうことを伝えたかったの?」と聞いてみましょう。お子さんの意図を確認しながら、より伝わりやすい表現を一緒に考えることで、国語の学習にもつながります。あくまでサポート役に徹し、お子さんの「書きたい」という気持ちを尊重してあげてください。
まとめ:小学生の卒業文集の書き方で、最高の思い出を未来へ

この記事では、小学生の卒業文集の書き方について、テーマの決め方から構成の作り方、具体的な例文、そして文章をより良くするコツまで詳しく解説してきました。
卒業文集を書く上で最も大切なのは、あなた自身の思い出や気持ちを、素直な言葉で表現することです。 6年間の小学校生活を振り返り、一番心に残っている出来事や、将来の夢、そしてお世話になった人への感謝の気持ちなどを思い浮かべてみましょう。
文章を書くのが苦手だと感じていても、心配はいりません。「はじめ・なか・おわり」という基本的な構成に沿って、まずは構成メモを作ってみることで、考えが整理されて書きやすくなります。 もし悩んだ時は、この記事で紹介した例文を参考に、自分らしいエピソードに置き換えてみてください。
卒業文集は、数年後、数十年後に読み返した時に、今のあなたの気持ちを思い出させてくれるタイムカプセルのような存在です。 この記事を参考に、あなたの6年間の輝かしい思い出を、未来に残る素敵な言葉で綴ってください。




コメント