生徒会選挙の立候補、おめでとうございます!「学校をより良くしたい」というその気持ち、とても素晴らしいです。しかし、全校生徒の前で話す「演説」に、不安や緊張を感じている人も多いのではないでしょうか。「何を話せばいいかわからない…」「どうすればみんなの心に響くんだろう?」そんな悩みを抱えるあなたのために、この記事では生徒会演説を成功させるためのコツを、中学生にも分かりやすく徹底解説します。
演説は、あなたの考えや学校への熱い思いをみんなに伝える絶好のチャンスです。 原稿の作り方から、自信を持って話すためのテクニックまで、具体的な例文も交えながら紹介していくので、ぜひ参考にして、あなたらしい最高の演説を準備してくださいね。
生徒会演説で心を掴む!中学生が知るべき基本のコツ

まずは、生徒会演説に臨む上での心構えと、基本となるポイントを押さえましょう。なぜ演説が重要なのか、そして聞き手の心に響く演説とはどんなものなのかを理解することが、成功への第一歩です。
なぜ生徒会演説が重要なのか?
生徒会演説は、ただ自分の意見を発表するだけの場ではありません。これは、全校生徒に自分という人間を知ってもらい、信頼してもらうための大切な機会です。 多くの生徒にとって、投票先を決める最も大きな判断材料がこの演説になります。あなたがどんな人物で、どんな学校にしたいと考えているのかを直接伝えられるのは、この演説の場だけです。だからこそ、ここでどれだけ自分の魅力や熱意を伝えられるかが、選挙の結果を大きく左右します。しっかりと準備をして、あなたの人柄や考えが伝わる演説を目指しましょう。
聞き手の心に響く演説の3つの要素
聞き手の心に響く演説には、共通する3つの要素があります。それは「共感」「信頼」「期待」です。
- 共感:「わかる!」「自分もそう思う!」と聞き手に感じてもらうことです。例えば、「もっと行事が盛り上がったら楽しいのに、と思ったことはありませんか?」のように、多くの生徒が日頃感じているであろう悩みや願いに触れることで、共感を呼ぶことができます。
- 信頼:「この人なら任せられる」と思ってもらうことです。そのためには、具体的で実現可能な公約(マニフェスト)を掲げることが重要です。 また、ハキハキとした話し方や堂々とした態度は、自信の表れとして信頼につながります。
- 期待:「この人が生徒会に入ったら、学校がもっと良くなりそう」と未来を想像してもらうことです。「皆さんの意見を聞くために目安箱を設置します!」といった具体的な行動計画を示すことで、生徒たちはあなたが活躍する姿をイメージし、学校の未来に期待を寄せてくれるでしょう。
これらの3つの要素を意識して演説を組み立てることが、多くの票を集めることにつながります。
まずは自分を知ろう!自己分析のすすめ
魅力的な演説をするためには、まず自分自身を深く知ることが不可欠です。自分が「なぜ生徒会に入りたいのか」「生徒会で何を成し遂げたいのか」を明確にしましょう。
- 立候補の動機を掘り下げる:「学校を良くしたい」という漠然とした思いだけでなく、「なぜそう思うようになったのか」という具体的なきっかけやエピソードを思い出してみましょう。 例えば、「昨年の文化祭で、クラス企画の準備が大変だった。だから、もっと全校生徒が協力し合えるような仕組みを作りたい」といった個人的な体験は、他の誰にも真似できない、あなただけの強い動機になります。
- 自分の強みと弱みを理解する:自分の長所は何か、短所は何かを客観的に分析してみましょう。例えば、「誰とでもすぐに打ち解けられるのが長所」であれば、「そのコミュニケーション能力を活かして、全校生徒の意見を吸い上げます」とアピールできます。 逆に「人前で話すのは少し苦手」という弱みがあったとしても、「だからこそ、一人ひとりの小さな声に耳を傾けたい」と誠実に伝えることで、かえって好感を持たれることもあります。
このように自己分析を深めることで、演説の内容に説得力とあなたらしさが生まれます。
【中学生向け】当選に近づく!生徒会演説の原稿作成のコツ
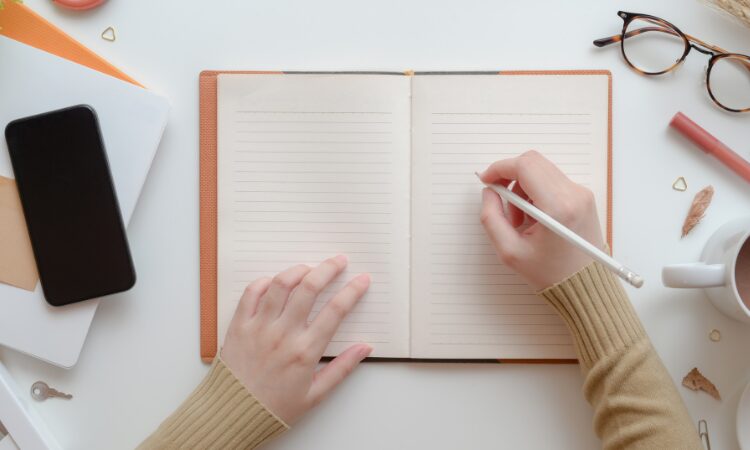
演説の成功は、しっかりとした原稿作成から始まります。ここでは、聞いている生徒たちを引きつけ、あなたの思いがしっかりと伝わる原稿の作り方を、構成から具体的な表現まで詳しく解説します。
印象に残る!演説原稿の基本構成
演説原稿は、聞き手が内容を理解しやすいように、「①はじめ(自己紹介と問題提起)」「②なか(具体的な公約)」「③おわり(決意表明とお願い)」という3つのパートで構成するのが基本です。
- ①はじめ(自己紹介と問題提起):
まずは、学年・クラス・名前を大きな声でハキハキと伝え、自分を覚えてもらいましょう。 「この度、生徒会〇〇に立候補しました、〇年〇組の〇〇です」と、役職名も明確に伝えます。 その後、「皆さん、今の学校生活に満足していますか?」のように、聞き手に問いかける形で問題提起をすると、演説に引き込みやすくなります。 キャッチフレーズを使って「〇〇で学校を笑顔に!」のように、自分が目指すものを最初に簡潔に示すのも効果的です。 - ②なか(具体的な公約):
演説の最も重要な部分です。 あなたが「生徒会に入って何をしたいのか」を具体的に述べます。 ここで大切なのは、「学校を楽しくします」といった抽象的な言葉で終わらせず、「全校生徒が参加できる球技大会を企画します」「目安箱を設置し、寄せられた意見は毎月生徒会だよりで回答します」のように、誰が聞いても活動内容がイメージできるような具体的な公約を掲げることです。 なぜその公約を実現したいのか、その背景にあるあなたの思いや経験談を交えると、より共感を得やすくなります。 - ③おわり(決意表明とお願い):
最後に、改めて生徒会活動にかける熱意を伝え、力強く締めくくります。 「私は、皆さんの声を聞き、全力で行動することをお約束します」といった決意表明で、あなたの本気度をアピールしましょう。 そして、「皆で一緒に、この学校をさらに素晴らしい場所にしていきましょう。 清き一票を、どうぞよろしくお願いします!」と、投票を明確にお願いして演説を終えます。感謝の言葉「ご清聴ありがとうございました」も忘れないようにしましょう。
具体的な公約(マニフェスト)の作り方
公約は、あなたの演説の「核」となる部分です。他の候補者との違いを明確にし、有権者である生徒たちに「この人に投票したい」と思わせるための重要な要素となります。
- みんなの「あったらいいな」を考える:まずは、自分だけでなく、周りの友達やクラスメイトが学校に対してどんな不満や要望を持っているかリサーチしてみましょう。「昼休みに体育館が使えたらいいのに」「もっと面白い行事がほしい」など、たくさんの意見が出てくるはずです。それらが公約のヒントになります。
- 「具体性」と「実現可能性」を意識する:集めた意見の中から、具体的で、かつ実現可能なものを公約として選びましょう。例えば、「あいさつ運動を活発にする」という公約なら、「毎朝、生徒会役員が校門に立ち、あいさつ当番を設置します」と具体的にすることで、本気度が伝わります。また、「校則をすべてなくす」といった非現実的な公約は、かえって信頼を失う可能性があるので注意が必要です。先生方とも相談しながら、実現できる範囲の公約を考えましょう。
- 公約は2~3個に絞る:あまり多くの公約を並べすぎると、一つひとつの印象が薄れてしまいます。 本当に実現したい、最も重要な公約を2つか3つに絞って、それぞれを丁寧に説明する方が、聞き手の記憶に残りやすくなります。 例えば、「学校行事の活性化」と「生徒の意見を取り入れる仕組み作り」のように、テーマを絞って話すと良いでしょう。
他の候補者と差がつく!オリジナリティの出し方
他の候補者と同じような内容では、なかなか印象に残りません。あなた自身の言葉で、あなたならではの演説にすることが大切です。
- 自分の「体験談」を語る:公約を述べるときは、必ずあなた自身の具体的なエピソードを交えて話しましょう。 例えば、「私はバスケットボール部に所属していますが、雨の日に練習する場所に困ることがよくあります。だから、体育館の利用ルールを見直して、もっと多くの部活動が快適に活動できる環境を作りたいです」のように話すと、その公約に込められたあなたの真剣な思いが伝わり、聞き手の心を動かします。
- 自分らしい「言葉」で語る:難しい言葉を使う必要はありません。 いつものあなたが友達と話すような、自然で分かりやすい言葉を選びましょう。 少しユーモアを交えてみたり、好きな言葉を引用してみたりするのも良いでしょう。大切なのは、借り物の言葉ではなく、あなた自身の心から出てきた言葉で語りかけることです。そうすることで、あなたの人柄が伝わり、親近感を持ってもらえます。
- 学校全体への「愛」を伝える:あなたがどれだけこの学校を好きで、大切に思っているかを伝えることも、共感を呼ぶポイントです。「私は、みんなが『この学校に通っていて良かった』と心から思えるような学校にしたいです」というメッセージは、きっと多くの生徒の心に響くはずです。 自分のためではなく、学校に通うみんなのために頑張りたいという姿勢を伝えましょう。
使ってはいけないNGワードと表現
演説で聴衆の心を掴むためには、避けるべき言葉や表現があります。無意識に使ってしまうと、かえってマイナスの印象を与えかねないので注意しましょう。
- 「~だと思います」といった曖昧な表現:「~だと思います」「~のつもりです」といった自信のなさそうな表現は避けましょう。生徒会役員にはリーダーシップが求められます。「~します」「~をお約束します」と、断定的な言葉を使うことで、頼りがいのある印象を与えることができます。
- 他の候補者を批判する言葉:たとえ選挙戦であっても、他の候補者の悪口を言ったり、批判したりするのは絶対にやめましょう。他人を貶めるような発言は、聞いている人に不快な印象を与えるだけでなく、あなた自身の品位を下げてしまいます。正々堂々と、自分の政策や学校への思いを語ることに集中してください。
- 上から目線の言葉遣い:「皆さんのために、私が~してあげます」のような、上から目線の表現もNGです。「皆さんと一緒に~していきたいです」「皆さんの力を貸してください」のように、全校生徒と同じ目線に立ち、協力をお願いする謙虚な姿勢が大切です。 生徒会はみんなの代表であることを忘れずに、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
聞き手を惹きつける!生徒会演説の話し方のコツ

素晴らしい原稿が完成しても、それが聞き手に伝わらなければ意味がありません。ここでは、あなたの思いを全校生徒の心に届けるための「話し方」のコツを紹介します。本番で力を発揮するために、しっかり練習しましょう。
自信が伝わる!声の出し方と話し方
自信があるように見える話し方は、内容の説得力を何倍にも高めてくれます。
- 明るく、ハキハキと話す:演説で最も大切なことの一つは、明るく、はっきりとした声で話すことです。 小さな声やモゴモゴとした話し方では、自信がないように見えてしまい、内容も聞き取ってもらえません。体育館の後ろの席まで届けるつもりで、お腹から声を出すことを意識しましょう。口を大きく開けて、一語一語を丁寧に発音する練習をしてみてください。
- 「間」を効果的に使う:ずっと同じペースで話し続けると、聞いている方は疲れてしまい、内容が頭に入りにくくなります。そこで重要になるのが「間」です。伝えたいキーワードの前や、問いかけの後で一呼吸置くことで、聞き手の注意を引きつけ、言葉の重みを増すことができます。「私たちの学校に必要なもの。それは…(間)…生徒一人ひとりの笑顔です」のように、間を意識的に使ってみましょう。
- 抑揚をつけて話す:一本調子の話し方は、聞き手を退屈させてしまいます。 大事なところは声を大きくしたり、少しゆっくり話したりと、声に強弱や高低の変化(抑揚)をつけましょう。 特に、自分の名前や公約など、一番伝えたい部分は感情を込めて力強く話すと、熱意が伝わりやすくなります。
全校生徒に思いを届ける!目線の配り方
どこを見て話すか(目線)も、聞き手に与える印象を大きく左右します。原稿ばかりを見つめるのではなく、しっかりと顔を上げて、全校生徒に語りかけましょう。
- 原稿の棒読みは絶対にしない:演説で最も避けたいのが、手元の原稿を下を向いて読み続けることです。 これでは、あなたの熱意は全く伝わりません。原稿はあくまで話す内容を確認するためのもので、完璧に暗記する必要はありませんが、キーワードや話の流れは頭に入れておきましょう。そして、できるだけ顔を上げて話すことを心がけてください。
- 会場全体をゆっくりと見渡す:演説が始まったら、まずは会場全体をゆっくりと見渡してみましょう。前の席の人だけでなく、右側、左側、そして後ろの席の人たちにも、順番に視線を送るようにします。こうすることで、「自分たちにも語りかけてくれているんだ」と、多くの生徒が感じることができます。特定の人だけを見つめ続けるのは避け、広く浅く視線を配るのがコツです。
- うなずいてくれる人を見つける:大勢の前で話すのが緊張する場合は、優しそうな表情で聞いてくれている人や、うなずきながら聞いてくれている友達を見つけて、その人に向かって話しかけるようにするのも一つの方法です。知っている顔を見つけると、少し気持ちが落ち着いて、自然な表情で話しやすくなります。ただし、その人ばかりを見ないように、時々視線を動かすことを忘れないでください。
説得力を倍増させる!ジェスチャーの使い方
言葉だけでなく、身振り手振り(ジェスチャー)を加えることで、演説はより表現豊かになり、説得力が増します。
- 強調したい場面で自然に使う:ジェスチャーは、演説中ずっと大げさに動かす必要はありません。特に伝えたい公約や、決意を述べるときなど、ここぞという場面で効果的に使いましょう。例えば、「私は3つのことを約束します」と言うときに指を3本立てたり、「皆で力を合わせましょう」と呼びかけるときに両手を広げたりすると、言葉の意味が視覚的にも伝わりやすくなります。
- 胸の前で手を組むのは避ける:腕を組んだり、体の前で手を固く組んだりする姿勢は、自信がなさそうに見えたり、聞き手を拒絶しているような印象を与えたりすることがあります。できるだけ体はオープンな状態を保ち、リラックスして話すことを心がけましょう。手持ち無沙汰に感じる場合は、片方の手を軽くもう片方の手に添える程度が良いでしょう。
- 練習で身につける:いきなり本番でジェスチャーをしようとしても、ぎこちなくなってしまいます。鏡の前で練習したり、家族や友達に見てもらったりして、どのタイミングでどんなジェスチャーをするのが効果的かを研究しましょう。 自分の言葉と動きが自然に連動するように、何度も繰り返し練習することが大切です。
緊張を味方につける!本番で力を発揮する方法
全校生徒の前に立つのは、誰でも緊張するものです。しかし、その緊張を完全に消そうとするのではなく、うまく付き合っていくことが大切です。
- 「完璧」を目指さない:緊張の大きな原因は、「うまくやらなきゃ」「失敗したくない」というプレッシャーです。しかし、少しぐらい言葉に詰まったり、言い間違えたりしても大丈夫です。大切なのは、完璧な演説をすることではなく、あなたの「学校を良くしたい」という熱意を伝えることです。誠実な気持ちが伝われば、多少の失敗は気にされません。
- 本番前の深呼吸:自分の番が近づいてきたら、ゆっくりと深い呼吸を繰り返しましょう。鼻から大きく息を吸って、口からゆっくりと吐き出す。これを数回行うだけでも、心拍数が落ち着き、リラックスする効果があります。また、「自分ならできる」と心の中でポジティブな言葉を唱えるのも、自信を持つために有効です。
- 練習量こそが最大の自信:最終的に、緊張を和らげてくれるのは「これだけやったんだから大丈夫」という練習量です。声に出して何度も原稿を読み、家族や友達の前で発表する練習を重ねましょう。練習をすればするほど、内容が体に染み込み、本番でも自信を持って話せるようになります。本番は、練習の成果を発表する場だと考え、楽しむくらいの気持ちで臨みましょう。
【シーン別】すぐに使える!生徒会演説の例文

ここでは、立候補する役職別に、演説の例文を紹介します。これを参考に、ぜひあなた自身の言葉やエピソードを加えて、オリジナルの演説原稿を完成させてください。
会長に立候補する場合の演説例文
生徒会長は、学校のリーダーとして強いリーダーシップとビジョンが求められます。学校全体をどう変えていきたいかを明確に伝えましょう。
皆さん、こんにちは。
この度、生徒会長に立候補しました、2年1組の〇〇 〇〇です。
皆さんは、今の〇〇中学校が「最高の学校」だと胸を張って言えますか? 私は、この学校が大好きです。しかし、もっと一人ひとりが輝ける、もっと笑顔があふれる学校にできるはずだと信じています。
私が生徒会長になったら、実現したいことが2つあります。
一つ目は、「目安箱NEXT」の設置です。従来の目安箱に加えて、月に一度、全校生徒が参加できるオンラインアンケートを実施します。スマートフォンから匿名で気軽に意見を送れるようにすることで、今まで届かなかった小さな声も拾い上げ、生徒会活動に反映させていきます。
二つ目は、「学年を超えた交流イベント」の開催です。現在は体育祭や文化祭など、決まった行事でしか他学年と交流する機会がありません。昼休みを利用したeスポーツ大会や、有志による特技発表会など、誰もが気軽に参加できるイベントを企画し、先輩・後輩のつながりを深め、学校全体の一体感を高めたいです。
私は、全校生徒の皆さんと対話し、皆さんと一緒にこの学校を作っていきたいです。私に、その先頭に立つチャンスをください。この〇〇中学校を、日本一の学校にしましょう!
皆さんの大切な一票を、〇〇 〇〇に、どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
副会長・書記などに立候補する場合の演説例文
副会長や書記などの役職は、会長を支え、生徒会を円滑に運営する「縁の下の力持ち」としての役割が重要です。サポート力や実務能力をアピールしましょう。
皆さん、こんにちは。
この度、生徒会副会長に立候補しました、1年3組の〇〇 〇〇です。
私が副会長に立候補した理由は、リーダーを支え、みんなのために働くことに大きなやりがいを感じるからです。小学校では放送委員長として、運動会のアナウンスや機材の準備を担当し、行事を裏から支えることの楽しさを学びました。
私が副会長になったら、会長の最高のサポーターとして、公約の実現を全力でサポートします。会長がリーダーシップを発揮できるよう、私は議事録の作成や各委員会との連絡調整など、地道な仕事を正確かつ丁寧に行うことをお約束します。
さらに、私は「生徒会活動の見える化」を進めたいです。生徒会が今どんな活動をしているのか、廊下の掲示板や生徒会だよりを通じて、こまめに皆さんにお知らせします。そうすることで、生徒会をより身近に感じてもらい、皆さんの意見や協力を得やすくしたいと考えています。
目立つことは苦手かもしれませんが、誰かのためにコツコツと努力することには自信があります。この力を、ぜひ〇〇中学校のために役立たせたいです。会長、そして役員の皆さんをしっかりと支え、より良い生徒会を作っていきます。
どうぞ、〇〇 〇〇をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ユーモアを交えた演説例文
真面目な演説も大切ですが、時にはユーモアを交えることで、聞き手の心を掴み、強い印象を残すことができます。 あなたのキャラクターに合っているなら、挑戦してみる価値はあります。
皆さん、こんにちは!
(少し間を置いて)…あれ、拍手が聞こえませんね?未来の生徒会長、2年4組の〇〇 〇〇の登場です!
さて、突然ですが、皆さんに質問です。この学校のWi-Fi、少し弱くないですか? 私が調べたところ、体育館の隅っこが一番電波が強いようです。だからといって、みんなで体育館の隅っこに集まるわけにはいきませんよね。
私が生徒会長になったら、まず「校内Wi-Fi環境の改善」を学校に全力で交渉します!快適なネット環境で、調べ学習をもっと効率的に、そして休み時間をもっと楽しく過ごせるようにしたいです。
そしてもう一つ。我が校の七不思議、知っていますか? 「開かずの間にいるベートーベンの肖像画」…ではなく、「なぜかいつも長い、トイレの行列」です!これを解決するため、トイレットペーパーの補充状況をリアルタイムで知らせるシステム(という名の、クラスごとの当番チェック表)を導入し、休み時間を1秒たりとも無駄にしない学校を目指します!
もちろん、ふざけているだけではありません。私は、皆さんの「ちょっとした不満」に真剣に耳を傾け、それを「笑顔」に変えるために、全力で働きます。
この学校を、日本一笑いの絶えない、そして過ごしやすい学校にしてみせます!
面白そうだと思ったら、ぜひ一票!〇〇 〇〇をよろしくお願いします!ありがとうございました!
まとめ:生徒会演説のコツを掴んで、自信を持って本番へ!

この記事では、中学生の皆さんが生徒会演説で成功するためのコツを、原稿の書き方から話し方まで詳しく解説してきました。
演説で最も大切なのは、あなた自身の言葉で、学校をより良くしたいという熱い思いを誠実に伝えることです。 難しい言葉や格好つけた表現は必要ありません。具体的な公約を掲げ、自信を持ってハキハキと話すことが、聞き手の信頼を得ることにつながります。
紹介した構成や例文を参考に、あなたならではのエピソードを盛り込んだ原稿を作成し、何度も声に出して練習してみてください。練習量が増えるほど、自信がつき、本番での緊張も和らぎます。
あなたの素晴らしい挑戦を心から応援しています!


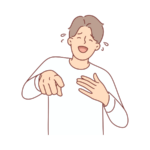

コメント