応援演説とは、生徒会選挙などで立候補した友人の良さを伝え、多くの人に「この人に投票したい!」と思ってもらうためのスピーチです。 応援演説を頼まれたあなたは、候補者にとって非常に重要な役割を担っています。 あなたの言葉一つで、選挙の結果が大きく変わることもあるのです。
しかし、いざ書こうと思っても「何から始めたらいいの?」「どうすれば魅力が伝わるの?」と悩んでしまいますよね。大丈夫です。この記事では、応援演説の基本的な構成から、心に響く言葉の選び方、そして聞いている人を引きつける話し方のコツまで、中学生の皆さんに分かりやすく解説していきます。応援演説の書き方をマスターして、あなたの大切な候補者を全力で応援しましょう!
応援演説って何?目的を理解しよう
まず、応援演説の目的をしっかり理解することが大切です。応援演説の一番の目的は、立候補した人がどれだけ生徒会役員にふさわしい人物であるかを、第三者の視点から伝えることです。 候補者本人が自分のことをアピールするのとは別に、友人であるあなたが語ることで、その言葉に客観性と信頼性が生まれます。
具体的には、候補者の人柄や普段の学校生活での素晴らしい行動、そして役員になったら何をしてくれそうか、といった期待を語ります。ただ長所を並べるだけでなく、具体的なエピソードを交えて話すことで、聞いている人は候補者の姿をより鮮明にイメージできるようになります。 この演説を通じて、聞いている生徒たちに「〇〇さんなら、私たちの学校をきっと良くしてくれる!」と共感してもらい、最終的に投票につなげることがゴールです。
誰に何を伝える?ターゲットとメッセージを明確に
次に考えるべきなのは、「誰に(ターゲット)」、「何を(メッセージ)」伝えるかです。応援演説を聞くのは、全校生徒ですよね。ですから、一部の人にしか分からないような内輪ネタは避け、誰にでも分かりやすい言葉で話す必要があります。
そして、最も重要なのが「メッセージ」です。候補者の魅力はたくさんあると思いますが、全てを話そうとすると、かえって印象が薄くなってしまいます。 時間も限られているため、「これだけは絶対に伝えたい!」という中心的なメッセージを一つか二つに絞りましょう。 例えば、「〇〇さんは、誰にでも優しいリーダーです」や「〇〇さんは、決めたことを必ず実行する行動力があります」といった具体的な強みです。このメッセージを軸にして、それを裏付けるエピソードなどを組み立てていくと、まとまりのある説得力のある演説になります。
応援演説の基本的な構成「序論・本論・結論」
応援演説の原稿は、大きく分けて「序論・本論・結論」の3つのパートで構成するのが基本です。 この流れを意識するだけで、格段に分かりやすく、聞きやすいスピーチになります。
- 序論(始まり): まずは、自分のクラスと名前を名乗り、誰の応援に来たのかを明確に伝えます。 ここで、候補者との関係性(「〇〇さんとは同じクラスで、いつも助けてもらっています」など)を少し加えると、聞いている人が話に入り込みやすくなります。
- 本論(中身): ここが演説の中心部分です。なぜその候補者を応援するのか、その理由を具体的なエピソードを交えて語ります。 例えば、「責任感が強い」という長所を伝えたいなら、「昨年の文化祭で、誰もやりたがらない難しい役職を自ら引き受け、毎日遅くまで準備を頑張ってくれた」といった事実を話します。 このエピソードによって、あなたの言葉に説得力が生まれます。
- 結論(締め): 最後に、もう一度候補者の名前を出し、「〇〇さんなら、この学校をより良くしてくれると信じています」といった力強い言葉で、投票を呼びかけます。 そして、「ご清聴ありがとうございました」という感謝の言葉で締めくくりましょう。
【場面別】中学生向け応援演説の例文集

応援演説の基本的な構成が分かったところで、次に具体的な例文を見ていきましょう。ここでは、中学生が応援演説を頼まれることが多い「生徒会選挙」と「体育祭や部活動」の場面に分けて、すぐに使える例文を紹介します。もちろん、候補者の人柄や役職に合わせて、言葉やエピソードをアレンジして使ってくださいね。自分自身の言葉を加えることで、より心のこもったスピーチになります。
生徒会選挙(会長候補)の応援演説 例文
生徒会長は学校のリーダーです。そのため、演説ではリーダーシップ、責任感、そして全校生徒のことを考える広い視野を持っていることをアピールするのが効果的です。
皆さん、こんにちは。
〇年〇組の〇〇です。私が本日ここでお話しさせていただくのは、生徒会長に立候補した、〇〇さんの応援のためです。
皆さんは、〇〇さんにどのようなイメージを持っていますか?いつも明るく、誰にでも分け隔てなく接してくれる、そんなイメージではないでしょうか。もちろん、それも〇〇さんの大きな魅力です。しかし、私が伝えたい〇〇さんの本当のすごさは、その強いリーダーシップと責任感です。
去年の合唱コンクールで、私たちのクラスはなかなかまとまらず、練習も思うように進みませんでした。そんな時、中心になってクラスを引っ張ってくれたのが〇〇さんでした。彼は、ただ「頑張ろう」と言うだけではありません。一人ひとりの意見に耳を傾け、時には朝早くから練習に付き合い、どうすればみんなが楽しく歌えるかを真剣に考えてくれました。その姿を見て、私たちのクラスは一つになり、本番では最高の合唱を披露することができました。
〇〇さんは、周りの人を巻き込み、同じ目標に向かって導く力を持っています。そして、一度引き受けたことは、決して投げ出しません。この力は、必ず生徒会長という立場で活かされるはずです。皆さん一人ひとりの声を聞き、この学校をより楽しく、より過ごしやすい場所にするために、全力で行動してくれると私は確信しています。
どうか、未来の生徒会長、〇〇さんに、皆さんの貴重な一票をよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。
生徒会選挙(書記・会計候補)の応援演説 例文
書記や会計といった役職は、リーダーシップもさることながら、真面目さ、正確さ、そして縁の下の力持ちとして組織を支える責任感が求められます。 演説では、そうした実務能力や誠実な人柄が伝わるエピソードを盛り込みましょう。
皆さん、こんにちは。
〇年〇組の〇〇です。今回は、生徒会書記に立候補した〇〇さんの応援にまいりました。
私が〇〇さんを推薦する理由は、彼女の誰にも真似できないほどの真面目さと、丁寧な仕事ぶりです。
〇〇さんとは、文化祭の実行委員で一緒に活動しました。その中で、彼女は会議の議事録(話し合った内容の記録)を担当してくれたのですが、その内容が本当に素晴らしかったのです。誰がどんな意見を言ったのか、何が決まったのかが、後から誰が読んでも分かるように、とても分かりやすくまとめられていました。彼女のおかげで、私たちの準備はとてもスムーズに進みました。
また、〇〇さんは、目立つ仕事ではありませんが、みんなが見ていないところでも、コツコツと努力を続けられる人です。大変な作業でも決して手を抜かず、最後まで責任を持ってやり遂げます。
生徒会の書記という仕事は、まさに彼女のような誠実さと丁寧さが求められる役職だと思います。〇〇さんなら、生徒会の活動をしっかりと記録し、全校生徒の皆さんに分かりやすく伝えてくれるはずです。そして、生徒会を陰から力強く支えてくれる存在になると信じています。
どうか、生徒会書記には〇〇さんを、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
体育祭や部活動の応援演説 例文
体育祭や部活動の場面での応援演説は、選挙とは少し目的が異なります。ここでは、特定の誰かを応援するというよりは、チーム全体の士気を高め、団結力を強めることが重要です。選手のこれまでの努力を称え、聞いている仲間たちが「よし、やるぞ!」と思えるような、熱いメッセージを届けましょう。
〇〇組の皆さん!いよいよ体育祭当日を迎えました。
今日まで、私たちはこの日のために、朝早くから、そして放課後遅くまで、練習を重ねてきました。
うまくいかなくて悔しい思いをした日もあったと思います。意見がぶつかり合ったこともありました。
しかし、私たちはその度に話し合い、励まし合い、そしてお互いを高め合ってきました。その時間は、決して無駄ではありません。私たちの絆を、どこよりも強くしてくれたはずです。
グラウンドを見てください。今日まで一緒に汗を流してきた仲間がいます。
スタンドを見てください。大きな声で応援してくれる友達がいます。
私たちは一人ではありません。この最高の仲間たちと共に戦えることを、誇りに思いましょう。
結果はもちろん大切です。でも、それ以上に大切なのは、これまで努力してきた自分たちを信じ、最後まで諦めずに全力を出し切ることです。
今日、この場所で、私たちの最高の力を見せつけてやりましょう!
頑張るぞ!オー!
魅力的な応援演説にするための書き方のコツ

基本的な構成と例文が分かったら、次はあなたの演説をさらにレベルアップさせるための「書き方のコツ」を見ていきましょう。同じ内容でも、少し表現を工夫するだけで、聞いている人の心に響く度合いが大きく変わります。ここでは、誰でもすぐに実践できる4つのテクニックを紹介します。これらのコツを意識して、あなただけのオリジナルの応援演説を完成させてください。
具体的なエピソードで候補者の人柄を伝えよう
応援演説で最も大切なのは、候補者の魅力を具体的に伝えることです。 ただ「〇〇さんは優しいです」「リーダーシップがあります」と言うだけでは、聞いている人はあまりイメージが湧きません。 なぜそう言えるのか、その根拠となる具体的なエピソードを必ず入れましょう。
例えば、「優しい」ことを伝えたいなら、「私がクラスで孤立してしまった時、真っ先に『大丈夫?』と声をかけてくれ、休み時間にずっと隣で話を聞いてくれた」というように、実際にあった出来事を話します。 このような個人的な体験談は、聞いている人に「そんなことがあったんだ」と情景を思い浮かばせ、候補者の人柄にリアリティを持たせることができます。 聞いている人の共感を呼び、候補者の魅力を何倍にも強く印象づけることができるのです。
短く分かりやすい言葉を選ぼう
応援演説は、全校生徒という多くの人に向けて話すものです。そのため、一部の人にしか伝わらない難しい言葉や専門用語は避け、誰が聞いてもすぐに理解できる、シンプルで分かりやすい言葉を選びましょう。
原稿を書くときは、一文が長くなりすぎないように気をつけるのもポイントです。だらだらと長い文章は、聞いている人が途中で集中力を失ってしまう原因になります。 「~ですが、~なので、~でした」のように接続詞で長くつなげるのではなく、「~です。なぜなら、~だからです。」というように、一度文を区切ることを意識してみてください。声に出して読んでみて、息が苦しくなるようなら、その文は長すぎるサインです。短く、リズミカルな文章を心がけることで、内容が聞き手の頭にすっと入ってきやすくなります。
聞き手の共感を呼ぶ言葉を使おう
優れたスピーチは、話し手が一方的に話すのではなく、聞き手との間に一体感を生み出します。 そのために有効なのが、聞き手の共感を呼ぶ言葉を取り入れることです。例えば、「皆さんも、学校生活の中で『もっとこうだったらいいのに』と感じたことはありませんか?」のように、問いかけるフレーズを入れてみましょう。 こうすることで、聞き手は「確かにそうだな」と、演説を自分事として捉え始めます。
また、「私だけでなく、ここにいる多くの人が、〇〇さんの頑張りを見てきたはずです」といったように、「私」という一人称だけでなく、「皆さん」「私たち」といった言葉を使うのも効果的です。これにより、話し手と聞き手の間に「同じ学校の仲間」という連帯感が生まれ、演説全体がより心に響くものになります。候補者を応援する気持ちが、あなた一人のものではなく、みんなの気持ちであるかのように伝えることができるのです。
ポジティブな言葉で未来を語ろう
応援演説は、候補者の当選やチームの勝利といった、明るい未来のために行うものです。ですから、演説全体をポジティブで前向きな言葉で満たすことがとても重要です。誰かの批判をしたり、ネガティブな言葉を使ったりするのは絶対に避けましょう。
原稿を書く際には、「〇〇さんが生徒会長になれば、私たちの学校はもっと楽しくなります!」「〇-〇さんの力で、今よりもっと活気のある生徒会が生まれるはずです!」というように、候補者がもたらしてくれるであろう明るい未来を具体的に示してあげましょう。 このような希望に満ちた言葉は、聞いている人をワクワクさせ、「この人に任せてみたい!」という気持ちにさせます。候補者の魅力を伝えるだけでなく、その先にある素晴らしい未来を一緒に見せてあげることで、あなたの応援演説はより説得力を持つものになるでしょう。
聞き手の心をつかむ!応援演説の話し方とパフォーマンス

素晴らしい原稿が書けても、それが聞き手に伝わらなければ意味がありません。応援演説の成功は、話の内容だけでなく、話し方や態度といったパフォーマンスにも大きく左右されます。 人前で話すのは誰でも緊張するものですが、いくつかのポイントを意識するだけで、あなたの熱意や思いは格段に伝わりやすくなります。ここでは、自信を持って堂々と話すための具体的なコツを紹介します。練習して本番に臨みましょう。
自信を持って、大きな声でハキハキと話す
まず基本となるのが、聞き取りやすい声で話すことです。 体育館のような広い場所では、小さな声は後ろまで届きません。少し大げさかな、と思うくらい大きな声で、お腹から声を出すことを意識しましょう。
そして、一つ一つの言葉をハキハキと発音することも大切です。緊張すると早口になりがちですが、あえて少しゆっくりめに話すことで、言葉が明瞭になり、聞き手も内容を理解しやすくなります。 自信がないと声は小さくなり、語尾も消え入りがちになってしまいます。「応援したい」という強い気持ちを声に乗せるつもりで、堂々と話すことを心がけてください。それだけで、聞き手に与える印象は全く変わってきます。
姿勢とジェスチャーで熱意を伝える
人が話を聞くとき、言葉そのものの内容だけでなく、話し手の見た目からも多くの情報を受け取っています。これを非言語コミュニケーションと呼びます。応援演説においても、この非言語的な表現が非常に重要です。
まずは姿勢です。背筋をピンと伸ばし、胸を張って立つだけで、「自信がある」「堂々としている」という印象を与えることができます。うつむかずに、しっかりと前を向き、聞き手である全校生徒の顔をゆっくりと見渡しながら話しましょう。
さらに、ジェスチャーを効果的に使うことで、言葉に込められた熱意をより強く伝えることができます。 例えば、「〇〇さんなら、この学校をより良くしてくれます!」と一番伝えたい部分で、ぐっと拳を握ったり、手を広げたりするだけで、その言葉に力がこもります。ずっと同じ姿勢で話すのではなく、伝えたい気持ちに合わせて自然に体を動かすことを意識してみてください。
「間」を効果的に使って聞き手を引き込む
スピーチが上手な人は、話すことと同じくらい、話さない時間、つまり「間(ま)」を上手に使っています。ずっと同じペースで話し続けると、聞いている方は疲れてしまい、内容が頭に入ってきにくくなります。
そこで、大切なことを言う前や、話の区切りで、あえて一瞬黙る「間」を作ってみましょう。例えば、「私が〇〇さんを推薦する理由は…(少し間をあけて)…彼の圧倒的な行動力です」というように話すと、聞き手は「何だろう?」と次の言葉に自然と注目します。この「間」があることで、その後に続く言葉がより強調され、聞き手の印象に強く残るのです。また、演説の冒頭、話し始める前に少しだけ間を取るのも、会場の注目を集めるのに効果的です。怖がらずに、意識して「間」を使ってみましょう。
これで完璧!応援演説の原稿をチェックするときの注意点

素晴らしい応援演説にするためには、原稿を書き上げた後の最終チェックが欠かせません。自分では完璧だと思っていても、客観的に見直したり、声に出して読んでみたりすることで、改善点が見つかることはよくあります。本番で最高のパフォーマンスを発揮するために、ここで紹介する3つのポイントを必ず確認しておきましょう。少しの手間をかけるだけで、演説の完成度はぐっと高まります。
時間内に収まるか声に出して読んでみよう
応援演説には、多くの場合、制限時間が設けられています。 一般的に、人が集中して話を聞ける時間はそれほど長くありません。指定された時間をオーバーしてしまうと、聞いている人の集中力が切れてしまうだけでなく、運営の迷惑にもなってしまいます。
原稿が完成したら、必ずストップウォッチなどを使って、実際に声に出して読んでみましょう。 このとき、本番を想定して、少しゆっくりめに、ハキハキと話すのがポイントです。もし時間がオーバーしてしまう場合は、内容を削る必要があります。一番伝えたいメッセージは何かを再確認し、それ以外の部分や、重複している表現を整理していきましょう。 逆に、時間が余りすぎる場合は、エピソードを少し詳しく説明するなどして調整します。時間内にぴったり収まるように、何度も練習して調整することが成功への近道です。
候補者のイメージと合っているか確認しよう
応援演説は、あくまで主役である候補者のために行うものです。演説の内容が、応援する候補者の実際の人柄やイメージとずれていないかを、冷静な視点で確認することが非常に重要です。例えば、普段は物静かで真面目なタイプの候補者なのに、演説で「彼はいつもクラスのムードメーカーで、面白いことばかり言っています!」と紹介してしまうと、聞いている人は「本当にそうなの?」と違和感を抱いてしまいます。
これを防ぐために最も効果的なのは、原稿ができた段階で、一度候補者本人に読んでもらうことです。「このエピソードを使おうと思うんだけど、大丈夫?」「こういう言い方で、君の魅力は伝わるかな?」と相談してみましょう。候補者自身の意見を聞くことで、より正確で、心のこもった演説内容になります。二人三脚で最高の演説を作り上げるという意識を持つことが大切です。
誤字脱字や不適切な表現はないか
最後に、基本的なことですが、原稿に誤字脱字がないか、誰かを傷つけるような不適切な表現が含まれていないかを徹底的にチェックしましょう。特に、候補者の名前やクラスなどを間違えるのは、非常に失礼にあたりますので、細心の注意を払ってください。
また、候補者の魅力を伝えたいあまり、他の候補者を比較して悪く言ったり、誰かをからかうような表現を使ったりするのは絶対にNGです。応援演説は、ポジティブな言葉で、候補者の素晴らしさを伝える場です。
自分一人でチェックするだけでなく、友人や先生、家族など、第三者の目で見てもらうのも良い方法です。自分では気づかなかった間違いや、より良い表現が見つかるかもしれません。最後の最後まで丁寧に推敲(すいこう・文章を練り直すこと)を行い、完璧な原稿で本番に臨みましょう。
まとめ:【中学生向け】応援演説の書き方をマスターして、最高の応援を届けよう!

この記事では、中学生の皆さんが応援演説を頼まれた際に役立つ、書き方の基本から具体的な例文、そして話し方のコツまでを詳しく解説してきました。
応援演説で最も大切なのは、「この人を応援したい!」というあなたの純粋な気持ちです。 上手な言葉やテクニックも重要ですが、それ以上に、候補者の魅力を自分の言葉で、心を込めて伝えることが聞き手の心に響きます。
演説の構成は「序論・本論・結論」を基本とし、本論では具体的なエピソードを盛り込むことで、言葉に説得力を持たせましょう。 そして、原稿が完成したら、必ず声に出して時間を計り、候補者本人にも内容を確認してもらうことが大切です。
人前で話すのは緊張すると思いますが、しっかり準備と練習を重ねれば、自信を持って本番に臨むことができます。この記事で紹介した書き方やコツを参考に、あなたらしい最高の応援演説で、大切な友人にエールを送ってください。あなたの言葉が、きっと大きな力になるはずです。

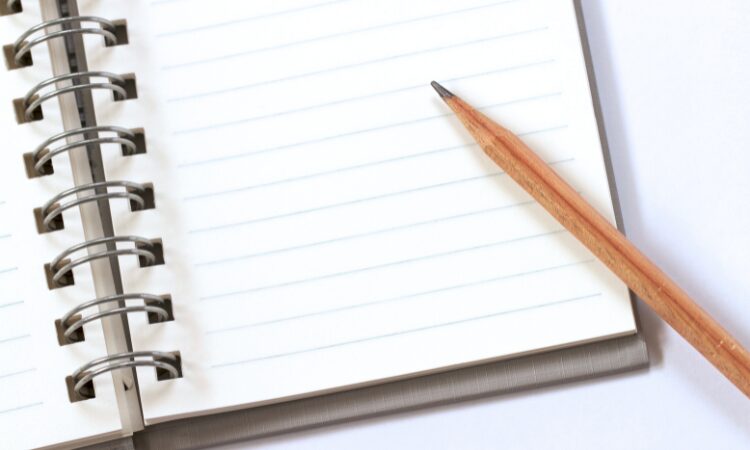


コメント