学級委員に立候補したものの、「みんなの前でどんな意気込みを話せばいいんだろう…」と悩んでいませんか?あるいは、推薦されてどうしようかと考えている人もいるかもしれません。
学級委員の意気込みを語るスピーチは、クラスのみんなに自分のことを知ってもらい、「この人になら任せられる!」と思ってもらうための大切な第一歩です。
この記事では、小学生から高校生まで、それぞれの学年に合わせた学級委員の意気込み例文を豊富にご紹介します。さらに、ただ例文を真似するだけでなく、自分の言葉でクラスメイトの心に響くスピーチを作るための具体的なステップや、聞いている人への印象を良くする話し方のコツまで、分かりやすく解説していきます。
この記事を読めば、あなたも自信を持って学級委員としての意気込みを語れるようになり、新しい学期、新しいクラスでの第一歩を力強く踏み出せるはずです。
学級委員の意気込みを考える前に知っておきたいこと

意気込みの例文を見る前に、まずは学級委員の役割やスピーチの目的について理解を深めておきましょう。これらを知ることで、より自分らしく、説得力のある意気込みを考えることができます。
学級委員の役割とは?
学級委員は、クラスのまとめ役であり、先生とクラスメイトの架け橋となる重要な存在です。 学校によって細かい仕事内容は異なりますが、主に以下のような役割を担います。
- クラスの意見をまとめる: みんなの意見を聞き、クラスとしての考えをまとめる。
- 学級会の進行: 話し合いがスムーズに進むように司会進行を務める。
- 先生との連携: 先生からの連絡事項をクラスに伝えたり、クラスの状況を先生に報告したりする。
- 行事の運営: 体育祭や文化祭などの学校行事で、クラスの中心となって企画や準備を進める。
- クラスの雰囲気作り: 明るく過ごしやすいクラスになるように、声かけなどを行う。
このように、学級委員の仕事は多岐にわたります。大変なこともありますが、クラスをより良くしていくという大きなやりがいのある役割です。
どんな人が学級委員に向いている?
「自分はリーダータイプじゃないから…」と不安に思う必要はありません。学級委員に求められる資質は、リーダーシップだけではありません。以下のような気持ちや特徴を持っている人なら、誰でも学級委員として活躍できる可能性があります。
- クラスを良くしたいという気持ちがある人: 「もっと楽しいクラスにしたい」「みんなが安心して過ごせるクラスにしたい」という思いが一番大切です。
- 責任感がある人: 引き受けた仕事を最後までやり遂げようとする真面目さ。
- 周りの意見をしっかり聞ける人: 自分の意見だけでなく、いろいろな人の考えを尊重できる。
- みんなのために行動できる人: 縁の下の力持ちとして、クラスのために動くことをいとわない。
- 新しいことに挑戦してみたい人: 学級委員の経験を通して、自分を成長させたいという意欲がある。
最初から完璧な人はいません。学級委員の活動を通して、リーダーシップや責任感は自然と育まれていきます。 「やってみたい」という気持ちを大切に、自信を持って挑戦してみましょう。
意気込みスピーチの目的と重要性
意気込みを語るスピーチは、単なる自己紹介ではありません。これは、クラスのみんなに対するあなたの「所信表明」であり、信頼を得るための非常に重要な機会です。スピーチの目的は、主に以下の2つです。
- 自分のやる気と人柄を伝える: 「このクラスをこんな風に良くしていきたい」というあなたの熱意や、「みんなと協力していきたい」という誠実な姿勢を伝えます。
- 「この人なら任せられる」と信頼してもらう: 具体的な目標や行動計画を示すことで、聞いている人に安心感と期待感を持ってもらいます。
どんなに素晴らしい考えを持っていても、それが伝わらなければ意味がありません。スピーチでは、自分の言葉で、分かりやすく、そして自信を持って話すことが大切です。そうすることで、あなたの思いがクラスメイトの心に響き、応援してくれる人が増えるはずです。
【学年別】学級委員の意気込み例文集

ここでは、小学生、中学生、高校生それぞれの学年に合わせた意気込みの例文を紹介します。これらの例文はあくまで参考です。 自分自身の言葉やクラスの状況に合わせて、アレンジして使ってみてください。
小学生向けの元気で分かりやすい例文
小学生のスピーチでは、明るく、元気に、分かりやすい言葉で話すことがポイントです。「みんなとなかよく」「楽しいクラス」といった、シンプルで前向きな言葉が心に響きます。
例文1:あいさつで元気なクラスに!
みなさん、こんにちは。この度、学級委員に立候補した〇〇です。
ぼく(わたし)は、このクラスが、みんなが毎日「おはよう!」と元気にあいさつできる、明るいクラスになったらいいなと思っています。
もし学級委員になったら、朝の会で元気にあいさつの見本を見せたり、あいさつ運動を企画したりしたいです。
みんなで元気にあいさつをして、一日を気持ちよくスタートできるクラスを一緒につくりましょう!よろしくお願いします。
例文2:みんなの笑顔があふれるクラスに!
わたしが学級委員になったら、笑顔があふれる楽しいクラスにしたいです。
そのために、クラスでやる遊びを決めるときなど、みんなの意見をたくさん聞きたいです。そして、みんなが「楽しい!」と思えるようなイベントを企画したいです。
困っている子がいたら、すぐに声をかけて助け合えるような、やさしい気持ちでいっぱいのクラスを目指します。
全力でがんばるので、応援よろしくお願いします。
例文3:忘れ物をなくすクラス!
ぼく(わたし)は、このクラスの忘れ物をゼロにしたいです!
みんなが授業の準備をしっかりできるように、前の日の帰りの会で、次の日の持ち物について声をかけるようにします。
もし学級委員になったら、先生と相談して、教室に「明日のもちもの」を書くコーナーを作りたいです。
みんなで協力して、忘れ物のない、勉強に集中できるクラスにしていきましょう!よろしくお願いします。
中学生向けの具体的で頼もしい例文
中学生になると、学校生活もより複雑になります。スピーチでは、小学生の時よりも具体的で、少し踏み込んだ内容を盛り込むと、「この人はしっかり考えているな」と信頼感が増します。勉強や部活動、学校行事など、具体的なテーマに触れるのがおすすめです。
例文1:メリハリのあるクラスを目指す!
この度、学級委員に立候補しました〇〇です。
私は、このクラスを「やるときはやる、楽しむときは楽しむ」というメリハリのあるクラスにしたいと考えています。
授業中は誰もが集中して学習に取り組める雰囲気を作り、休み時間や行事の時には、クラス全員で思いきり楽しめるような企画を提案していきたいです。
そのために、まずは授業開始のチャイムを守る「2分前着席」を徹底できるよう、積極的に声かけをしていきます。 皆さんの意見を大切にしながら、より良いクラス運営を目指しますので、ご協力よろしくお願いします。
例文2:学校行事を成功させたい!
皆さん、こんにちは。学級委員に立候補した〇〇です。
私は、体育祭や合唱コンクールといった学校行事を通して、このクラスの団結力を高めたいと思っています。
学級委員として、皆がそれぞれの得意なことを活かして活躍できるような役割分担を考えたり、練習がスムーズに進むように計画を立てたりと、皆をサポートしていきたいです。
行事の成功という一つの目標に向かって、クラス全員で協力し合う経験は、きっと私たちを大きく成長させてくれるはずです。最高の思い出を一緒に作りましょう。よろしくお願いします。
例文3:誰もが意見を言いやすい環境を作りたい!
私が学級委員になったら、クラスの誰もが安心して自分の意見を言える、風通しの良い環境を作りたいです。
「こんなことを言ったら笑われるかな」と不安に思うことなく、誰もが自由に発言できる雰囲気は、クラスの問題を解決したり、新しいアイデアを生み出したりするために不可欠だと思います。
その第一歩として、皆さんの意見を匿名で集められる「目安箱」を設置することを提案します。
皆さん一人ひとりの声を大切にし、それをクラス運営に活かしていきます。どうぞよろしくお願いします。
高校生向けの実現可能で説得力のある例文
高校生のスピーチでは、情熱だけでなく、実現可能性や論理性も大切になります。クラスが抱える課題を分析し、それに対する具体的な解決策を提示できると、説得力が高まります。大学受験など、将来を見据えた視点を入れるのも良いでしょう。
例文1:主体性を高め、団結力のあるクラスへ
この度、学級委員を務めさせていただくことになりました〇〇です。
私たちのクラスの目標は、一人ひとりが主体性を持ち、互いに高め合える集団になることだと考えています。
その実現のため、文化祭などの行事運営においては、企画段階から皆の意見を広く募り、全員が何らかの形で関われるよう役割を分担していきます。また、日々の学習においては、分からない問題を教え合えるような学習会を定期的に開くことを提案したいです。
学級委員として、皆の自主的な活動を全力でサポートし、クラス全体の団結力を高めていきたいと思います。一年間、よろしくお願いします。
例文2:進路実現に向けて協力できるクラス
学級委員に立候補しました〇〇です。
高校生活も後半に差し掛かり、多くの人が進路について真剣に考え始めていると思います。そこで私は、このクラスを、皆で進路実現に向けて協力し合えるクラスにしたいと考えています。
具体的には、クラス内でオープンキャンパスの情報や効果的な勉強法などを共有できる掲示板を設置したり、分野別に分かれて進路について語り合う機会を設けたりしたいです。
一人で悩むのではなく、クラスというチームで受験という大きな目標に立ち向かっていけるような雰囲気を作りたいです。皆さんの力を貸してください。よろしくお願いします。
例文3:効率的なクラス運営と情報共有
私が学級委員として取り組みたいことは、クラス運営の効率化です。
日々の連絡事項や提出物の管理などをよりスムーズに行うため、クラス用のSNSグループや共有カレンダーアプリの活用を提案します。これにより、情報の伝達ミスを防ぎ、皆がより重要な活動に時間を使えるようになると考えます。
また、学級会では、事前に議題を共有し、短い時間で結論が出せるよう工夫していきます。
学級委員として、皆が快適で充実した学校生活を送れるよう、縁の下の力持ちとしてクラスを支えていきたいです。ご支援よろしくお願いします。
自分らしい学級委員の意気込みを作る3つのステップ
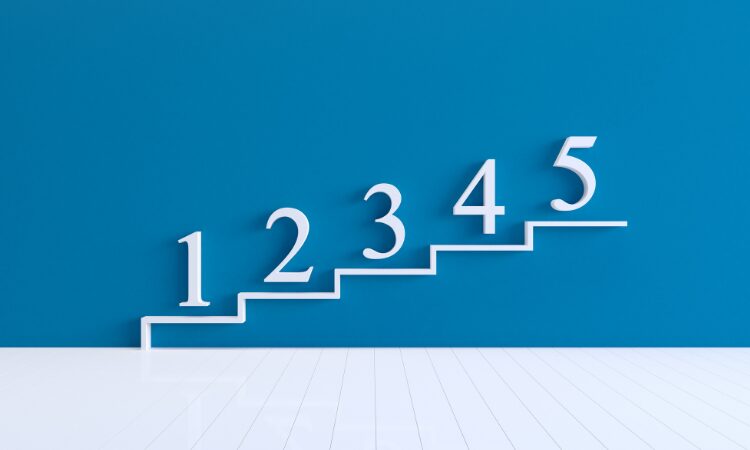
例文を参考にしつつ、さらに自分らしさを加えることで、スピーチはより魅力的になります。ここでは、オリジナルの意気込みスピーチを作成するための3つのステップを紹介します。
ステップ1:自分の「やりたいこと」を明確にする
まずは、「なぜ自分は学級委員になりたいのか」「学級委員になって、このクラスをどうしたいのか」を自分自身に問いかけてみましょう。 紙に書き出してみるのがおすすめです。難しく考える必要はありません。
- どんなクラスが理想?
- 「みんなが笑顔でいられるクラス」
- 「いじめや仲間外れのない、安心して過ごせるクラス」
- 「お互いに助け合える、温かい雰囲気のクラス」
- 「何事にもみんなで協力して取り組めるクラス」
- 自分の強みは?
- 「人の話を丁寧に聞くのが得意」
- 「みんなを盛り上げるのが好き」
- 「細かい作業をコツコツやるのが得意」
- 「責任感が強い」
これらの問いに答えていくことで、自分の核となる「思い」が見えてきます。この「思い」が、あなたのスピーチの土台となり、聞いている人の心に響くメッセージの源になります。
ステップ2:具体的な公約(マニフェスト)を考える
「やりたいこと」という理想を、具体的な行動計画、つまり公約(マニフェスト)に落とし込みましょう。 「楽しいクラスにしたい」というだけでは、聞いている人は具体的に何をするのか分かりません。
- 理想:「みんなが笑顔のクラス」
- 公約の例: 「月に一度、クラス全員が楽しめるレクリエーション大会を企画します!」
- 理想:「協力できるクラス」
- 公約の例: 「体育祭の応援グッズを、みんなでアイデアを出し合って手作りすることを提案します!」
- 理想:「意見を言いやすいクラス」
- 公約の例: 「クラスの問題について話し合うための学級会を、毎週金曜日のホームルームで定期的に開催します!」
公約を考える際のポイントは、実現可能であることです。 あまりに大きすぎる目標や、現実離れした計画は、かえって信頼を失うことにつながりかねません。 自分一人でできることだけでなく、「みんなで協力すればできそうなこと」を提案すると、クラスメイトも当事者意識を持ちやすくなります。
ステップ3:聞いている人に伝わる言葉で構成する
自分の「思い」と「公約」が決まったら、それらをスピーチの形に組み立てていきます。基本的な構成は以下の通りです。
- 始めの挨拶と自己紹介: 「皆さん、こんにちは。この度、学級委員に立候補しました、〇年〇組の〇〇です。」
- 学級委員になりたい理由(思い): 「私が学級委員になりたいと思った理由は、このクラスをもっと〇〇なクラスにしたいと思ったからです。」
- 具体的な公約: 「そのために、私は〇〇と〇〇の2つのことに取り組みたいと考えています。まず一つ目は…」
- 協力のお願いと結びの挨拶: 「もちろん、私一人の力では実現できません。ぜひ皆さんの力を貸してください。精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。」
この構成に沿って、ステップ1と2で考えた内容を、自分の言葉で当てはめていきましょう。難しい言葉を使う必要はありません。 むしろ、シンプルで分かりやすい言葉の方が、気持ちは伝わりやすいものです。完成したら、一度声に出して読んでみましょう。不自然な部分や、言いにくい部分を修正していくことで、より洗練されたスピーチになります。
印象アップ!学級委員の意気込みスピーチのコツ
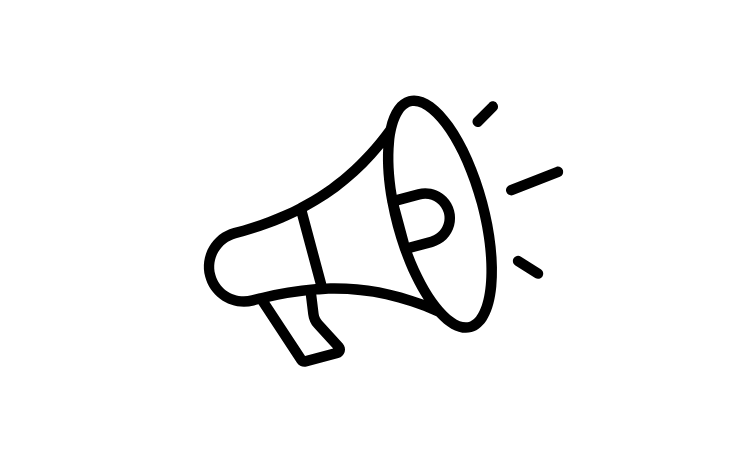
スピーチの内容と同じくらい、話し方や態度も重要です。少し意識するだけで、聞いている人に与える印象は大きく変わります。自信を持って堂々と話すためのコツをいくつかご紹介します。
話し方のポイント(声の大きさ、速さ、目線)
- 声の大きさ: 緊張すると声が小さくなりがちですが、意識して少し大きめの声で話しましょう。教室の後ろの人まで届けるつもりで、お腹から声を出すのがポイントです。
- 話す速さ: 早口になると、内容が伝わりにくく、焦っているような印象を与えてしまいます。少しゆっくりめを意識して、一語一語はっきりと話すように心がけましょう。適度な「間」を空けることも、聞き手が内容を理解する助けになります。
- 目線: 下を向いて原稿を読み続けるのではなく、できるだけ顔を上げて、クラス全体を見渡すように話しましょう。 特定の人だけを見るのではなく、いろいろな人と順番に目を合わせるようにすると、「みんなに語りかけている」というメッセージが伝わります。
姿勢や態度のポイント
- 姿勢: 猫背にならず、背筋をまっすぐ伸ばして立ちましょう。堂々とした姿勢は、自信があるように見え、話の説得力を高めます。
- 手: 手のやり場に困るかもしれませんが、ポケットに入れたり、後ろで組んだりするのは避けましょう。体の前で軽く組むか、自然に横に下ろしておくのが基本です。身振り手振りを少し加えると、表現が豊かになります。
- 表情: 緊張で顔がこわばってしまうかもしれませんが、できるだけ明るい表情を心がけましょう。スピーチの最初に少し微笑むだけでも、親しみやすい印象を与えることができます。
聞いている人の心をつかむテクニック
スピーチに少し工夫を加えることで、より聞いている人の心をつかむことができます。
- 最初に問いかける: 「皆さん、このクラスでどんな思い出を作りたいですか?」のように、最初に質問を投げかけると、聞き手はスピーチに引き込まれやすくなります。
- 自分の経験を話す: 「去年の体育祭で、みんなで協力した時にとても感動しました。今年はもっと大きな感動を味わいたいです」のように、自分の体験談を少し加えると、話に具体性とリアリティが生まれます。
- ユーモアを交える: 少しだけ笑えるような自己紹介やエピソードを入れると、場の雰囲気が和み、親近感を持ってもらえます。ただし、ふざけすぎると逆効果なので、バランスが大切です。
- 最後は力強く!: スピーチの最後は、感謝の気持ちとやる気を込めて、「精一杯頑張りますので、よろしくお願いします!」と力強く締めくくりましょう。丁寧にお辞儀をすることも忘れないでください。
まとめ:学級委員の意気込み例文を参考に、自分らしいスピーチを完成させよう

この記事では、学級委員の意気込みを伝えるための例文や、スピーチを作成するステップ、そして印象を良くするためのコツについて解説しました。
学級委員の意気込みを考えることは、「どんなクラスにしたいか」を真剣に考える素晴らしい機会です。今回紹介した例文はあくまで一つの例です。一番大切なのは、例文を参考にしつつも、自分の言葉で、自分の思いを正直に伝えることです。
あなたの「このクラスを良くしたい」という純粋な気持ちは、きっとクラスメイトの心に響くはずです。事前準備をしっかり行い、自信を持ってスピーチに臨んでください。あなたの挑戦を応援しています。




コメント