新学期が始まり、子どもたちと「どんなクラスにしたいか」を話し合う大切な時間。その中心となるのが「学級目標」です。この記事では、小学校の学級目標の例を、低学年・中学年・高学年といった学年別に豊富なアイデアでご紹介します。
さらに、子どもたちの主体性を引き出す決め方のステップや、一年間みんなが意識し続けられるような浸透させる工夫、四字熟語や担任の名前を使ったユニークな例まで、分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、あなたのクラスにぴったりの、心に残る学級目標づくりのヒントがきっと見つかるはずです。
小学校の学級目標とは?その役割と重要性

小学校における学級目標は、単に教室に掲示されるスローガンではありません。それは、子どもたちと担任の先生が一年間を共に過ごす上で、共通の指針となる大切な言葉です。 学級目標があることで、クラス全体が同じ方向を向き、一体感が生まれます。ここでは、学級目標が持つ役割と、その重要性について詳しく見ていきましょう。
クラスの一体感を高める「旗印」
学級目標は、いわばクラスの「旗印」のようなものです。みんなで話し合って決めた目標は、「自分たちのクラスの目標」という意識を育みます。 この共通認識があることで、子どもたち一人ひとりがクラスの一員であるという自覚を持ちやすくなります。運動会や合唱コンクールなどの行事の際には、この旗印のもとに団結し、目標達成に向けて力を合わせることができます。また、日々の学校生活の中で何か問題が起きたときも、「私たちのクラス目標はこうだよね」と立ち返る場所があることで、子どもたち自身で解決に向かう力を育むことにもつながるのです。
子どもたちの行動の「指針」
学級目標は、子どもたちが日々の学校生活を送る上での具体的な行動の「指針」となります。 例えば、「えがおで あいさつ みんななかよし」という目標があれば、子どもたちは「笑顔であいさつをしよう」「友達と仲良くしよう」と具体的な行動を意識しやすくなります。 この指針があることで、子どもたちは善悪の判断や望ましい行動について、自分たちで考える習慣を身につけることができます。抽象的な言葉だけでなく、「ありがとうを大切にするクラス」のように具体的な行動に結びつきやすい言葉を選ぶことで、目標はより生活に根付いたものになるでしょう。
学級経営の「羅針盤」
担任の先生にとって、学級目標は一年間の学級経営における「羅針盤」の役割を果たします。 学級目標は、学習指導要領や学校の教育目標に基づいて設定され、先生と子どもたちが目指すべき方向を共有するためのものです。 どのようなクラスにしたいかという先生の願いと、子どもたちの思いをすり合わせて作ることで、指導に一貫性が生まれます。 例えば、子どもたち同士のトラブルが起きた際に、「私たちのクラスの目標を思い出してみよう」と声をかけることで、目標が指導の根拠となり、子どもたちの納得感も得やすくなるのです。
【学年別】小学校の学級目標の例を紹介

小学校の子どもたちは、6年間で心も体も大きく成長します。そのため、学級目標もそれぞれの発達段階に合わせた言葉選びが大切です。 ここでは、低学年・中学年・高学年それぞれの特徴に合わせた学級目標の例を、具体的なキーワードと共に紹介します。
低学年(1・2年生)向けの例:ひらがなで分かりやすく
小学校に入学したばかりの低学年の子どもたちには、シンプルで覚えやすく、具体的な行動をイメージしやすい言葉が適しています。 難しい言葉は避け、ひらがなを中心にした、親しみやすい表現を心がけましょう。
キーワード例:
- やさしさ・なかよし: 「みんな なかよし たすけあう」「じぶんにも ともだちにも やさしく」
- げんき・えがお: 「にこにこ げんきで がんばる クラス」「あいさつで ひろがる えがおのわ」
- チャレンジ・がんばる: 「なんでも いっしょうけんめい やってみよう」「さいごまで あきらめない こころ」
学級目標の例:
- えがおで あいさつ みんななかよし
- おはなしは みみをすまして きこう
- にこにこ げんき 1ねんせい
- なんでもチャレンジ やればできる
- ありがとうのごあいさつ
中学年(3・4年生)向けの例:少しステップアップ
中学年になると、少しずつ自分たちで考えて行動できるようになり、仲間意識も芽生えてきます。 そのため、協力することや、自立、責任といった要素を少し加えた目標が効果的です。 子どもたち同士で話し合い、協働して目標を決めるプロセスも大切にしましょう。
キーワード例:
- 協力・助け合い: 「力を合わせて 前へ進もう」「おもいやりの心で 助け合うなかま」
- 挑戦・チャレンジ: 「チャレンジ精神で さい後までやりぬこう」「できることをふやして、夢に近づこう」
- 考える・伝える: 「考えよう つたえよう」「友だちの話をよく聞こう」
学級目標の例:
- みんなで協力 輝くクラス
- メリハリ・集中・思いやり
- 挑戦!全力!仲間を信じて!
- 一人一人が主人公!力を合わせる〇〇組
- 認め合い 高め合い 助け合う仲間
高学年(5・6年生)向けの例:自分たちで考える力を
高学年は、最高学年としての自覚が芽生え、より主体的な活動が期待される時期です。 抽象的な言葉の意味も理解できるようになるため、自分たちの将来や社会との関わりを意識した、少し背伸びした目標も良いでしょう。 目標を決める過程そのものが、子どもたちの成長につながります。
キーワード例:
- 自主性・責任: 「自分で考え 判断し 責任をもって行動しよう」
- 個性・尊重: 「一人ひとりの個性をみとめ合い 高め合える仲間たち」
- 未来・夢: 「自分を信じ 仲間を大切に 夢に向かってチャレンジしよう」
- 感謝・伝統: 「最高の思い出をつくろう」「ありがとうを忘れずに、みんなでがんばろう」
学級目標の例:
- One for all, All for one.(一人はみんなのために、みんなは一人のために)
- 凡事徹底(当たり前のことを徹底して行う)
- 考動(考えて動く)・協働(協力して働く)・幸動(幸せを呼ぶ行動)
- 最高の仲間と最高の思い出を
- 未来へはばたけ!夢に向かって全力ジャンプ!
心に残る!ユニークな学級目標の例とアイデア
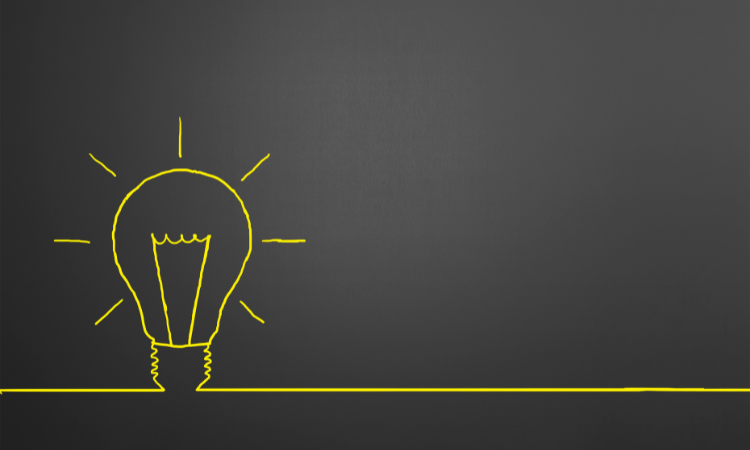
毎年同じような学級目標になりがち…と感じる先生もいるかもしれません。少し視点を変えるだけで、子どもたちの心に残り、一年間楽しく意識できるユニークな学級目標を作ることができます。ここでは、四字熟語やことわざを取り入れた例や、オリジナルの造語、あいうえお作文など、ユニークな学級目標のアイデアを紹介します。
四字熟語やことわざを取り入れた例
中学年や高学年になると、国語の授業で四字熟語やことわざを学び始めます。 それらを学級目標に取り入れると、言葉の意味を深く考えるきっかけになり、知的な雰囲気を出すことができます。 受験を控えた高学年には、自然と学習にもつながるというメリットもあります。
- 一期一会(いちごいちえ): このクラスの出会いを大切にしよう、という思いを込めて。
- 七転び八起き(ななころびやおき): 失敗を恐れずに何度も挑戦しよう、というメッセージ。
- 十人十色(じゅうにんといろ): 一人ひとりの個性を尊重し合えるクラスに。
- 一致団結(いっちだんけつ): クラスみんなで一つの目標に向かって力を合わせる。
- 切磋琢磨(せっさたくま): 仲間とお互いに励まし合い、高め合っていこう。
造語やスローガン形式の例
既存の言葉だけでなく、子どもたちとオリジナルの言葉やキャッチーなスローガンを考えるのも楽しい方法です。 クラスの特徴や目指す姿を短い言葉にギュッと凝縮することで、より愛着のわく目標になります。
- 造語の例:
- 笑倍(しょうばい): 笑顔が倍になるクラス。
- 楽級(がっきゅう): 楽しい学級。
- 進火(しんか): 目標に向かって燃えながら進む。
- スローガン形式の例:
- 全員主役、脇役なし。
- 心を燃やせ!
- ひとりじゃない、だから最強。
- みんなで作る、“世界一のクラス”ストーリー。
担任の名前やクラス名を使った例
あいうえお作文は、低学年から高学年まで楽しめるアイデアです。 特に、担任の先生の名前や「1年2組」といったクラス名を使うと、オリジナリティあふれる目標になります。 子どもたちもゲーム感覚で楽しく考えることができ、先生やクラスへの親近感も高まります。
- 担任の名前が「やまだ」先生の場合:
- やさしい心で
- まいにち笑顔
- だれとでも仲良く
- 「3年1組」の場合:
- さいごまで
- んーと力を合わせて
- ねばり強く
- ん~と伸びよう
- 一致団結
- くじけずチャレンジ
- みんなが主役
学級目標の決め方のポイント【小学校編】

学級目標は、ただ掲げるだけでは意味がありません。子どもたちが「自分たちの目標」として主体的に捉え、一年間意識し続けるためには、その決め方のプロセスが非常に重要です。 ここでは、子どもたちの思いを引き出し、クラスみんなが納得できる学級目標を決めるためのポイントを解説します。
子どもたちの意見を引き出す話し合い
何よりも大切なのは、子どもたちが主体となって話し合うことです。 先生が一方的に決めてしまうと、子どもたちは「先生の目標」と捉えてしまいがちです。 まずは、「どんなクラスにしたい?」「どんな自分になりたい?」といった問いかけから始め、子どもたちの願いや思いを自由に出し合う時間を作りましょう。 個人で考えたり、グループで話し合ったりする時間を設けることで、自分の意見を言うのが苦手な子も参加しやすくなります。 出てきた意見を黒板に書き出し、似ているものをまとめたり、キーワードを絞り込んだりしながら、クラス全体の思いを集約していきます。
ポジティブで具体的な言葉を選ぶ
学級目標の言葉を選ぶ際には、ポジティブな表現を心がけましょう。「〇〇しない」といった否定的な言葉よりも、「〇〇しよう」という肯定的な言葉の方が、前向きな気持ちで行動に移しやすくなります。 また、「頑張る」といった抽象的な言葉だけでなく、「最後まであきらめない」「友達の話をしっかり聞く」のように、具体的な行動につながる言葉を選ぶことも大切です。 子どもたちが目標を達成したかどうかを自分たちで判断しやすく、日々の生活の中で意識しやすくなります。
教室に掲示することを意識する
学級目標は、完成したら教室に掲示します。そのため、視覚的に分かりやすく、魅力的なデザインにすることも重要なポイントです。 目標の言葉だけでなく、その言葉をイメージしたイラストや、クラス全員の顔写真、手形などを取り入れると、より子どもたちの愛着が深まります。 掲示物を作る作業も、子どもたちと協力して行うと良いでしょう。自分たちが作ったものだと思うと、自然と目標に目が向き、意識する機会が増えます。 デザインや言葉の響きも考慮し、みんなが覚えやすく、口ずさみたくなるような目標を目指しましょう。
決めただけでは終わらない!学級目標を浸透させる工夫

素晴らしい学級目標が決まっても、それが教室の飾りになってしまっては意味がありません。 大切なのは、一年間を通して子どもたちと先生がその目標を意識し、行動に移していくことです。ここでは、決めた学級目標を形骸化させず、クラス全体に浸透させるための具体的な工夫を紹介します。
教室の目立つ場所に掲示する
まず基本となるのが、教室のいつでも目に入る場所に掲示することです。 子どもたちが自分たちで作成した目標を、イラストや写真と共に飾ることで、自然と目に留まり、意識するきっかけになります。 黒板の上や教室の後方など、子どもたちの視線が集まりやすい場所を選びましょう。 ただ掲示するだけでなく、「今日のめあて」として学級目標の一部を書き出したり、行事ごとに目標との関連を意識させたりするのも効果的です。
定期的に振り返りの時間を持つ
学級目標を浸透させるためには、定期的に振り返る機会を設けることが不可欠です。 例えば、毎週金曜日の帰りの会や、学期の終わりなどに、「今週、学級目標の〇〇が達成できたかな?」「次の学期は、〇〇をもっと頑張ろう」といった形で話し合う時間を持ちます。 目標が達成できた具体的なエピソードを子どもたちに発表してもらったり、良かった行動をみんなで認め合ったりすることで、目標への意識が高まります。 この振り返りを通じて、目標が達成できていなければその原因を考え、次への具体的な行動につなげていくことが大切です。
行事や活動と結びつける
運動会や学習発表会、日々の係活動など、学校生活の様々な場面で学級目標と結びつけて指導することも有効な方法です。 例えば、運動会の練習が始まる前に「『一致団結』の目標を達成するチャンスだね」と声をかけたり、係活動で「『責任』という目標のために、自分の役割をしっかり果たそう」と促したりします。このように、具体的な活動の中で目標を意識させることで、子どもたちは目標の意味をより深く理解し、自分たちの行動として定着させていくことができます。
【まとめ】学級目標の例を参考に、小学校生活を豊かにしよう

この記事では、小学校の学級目標について、学年別の豊富な例から、子どもたちの心に残るユニークなアイデア、そして目標を形骸化させないための決め方や浸透させる工夫まで、幅広く解説してきました。
学級目標は、単なる言葉ではなく、1年間を共に過ごすクラスの「旗印」であり、子どもたちの成長を促す「指針」です。 大切なのは、先生と子どもたちが一緒になって「こんなクラスにしたい」という願いを共有し、その思いを込めた言葉を紡ぎ出すプロセスです。低学年には分かりやすく具体的な言葉を、高学年には主体性を引き出すような言葉を選ぶなど、発達段階に合わせた配慮も重要になります。
そして、目標は決めて終わりではありません。 日々の声かけや定期的な振り返りを通じて、一年間意識し続けることで、学級目標は子どもたちの心に深く根付き、クラスの絆を深め、一人ひとりの豊かな成長へとつながっていきます。今回ご紹介したたくさんの例やアイデアをヒントに、ぜひあなたのクラスだけの素敵な学級目標を作り上げてください。




コメント