小学校3年生になると、学校の宿題で日記を書く機会が増えてきますね。「何を書けばいいかわからない」「毎日書くのが大変」とお子さんが悩んでいたり、どうやって教えたらいいか困っている保護者の方も多いのではないでしょうか。この記事では、小学校3年生に向けた日記の書き方のコツを、やさしくわかりやすく解説します。日記に何を書けばいいのかというネタ探しのヒントから、文章を組み立てる具体的なステップまで、豊富な例文を交えながらご紹介します。この記事を読めば、日記を書くのがきっと楽しくなるはずです。親子で一緒に読みながら、今日から楽しく日記を始めてみませんか?
小学校3年生向け!日記の書き方の基本

小学校3年生にとって、日記は自分を表現するとても良い練習になります。しかし、いざ書こうとすると何から手をつけていいか分からなくなってしまうこともありますよね。まずは、日記を書くことの楽しさや目的を知り、気軽に始められる準備をすることが大切です。ここでは、日記を書くことのメリットや、準備するもの、そして続けるためのちょっとしたコツといった、日記の書き方の基本的な部分から見ていきましょう。
なぜ日記を書くの?日記のすごい効果
「どうして日記なんて書かないといけないの?」と思っているお子さんもいるかもしれません。実は、日記にはたくさんの素晴らしい効果があるのです。第一に、文章を書く力(作文力)が自然と身につきます。 毎日自分の考えや出来事を文章にすることで、どうすれば相手に伝わるかを考える練習になります。 第二に、表現力や語彙力(たくさんの言葉を知っていること)が豊かになります。 「楽しかった」という気持ち一つでも、「わくわくした」「心がはずんだ」など、いろいろな言葉で表現する工夫ができるようになります。 第三に、一日を振り返ることで、考える力や記憶力が育ちます。 その日あったことを思い出し、何が一番心に残ったかを考えることは、頭の体操にもなります。そして最後に、日記は自分の成長の記録になります。後で読み返したときに、「こんなことがあったんだな」「こんなことを考えていたんだな」と、大切な思い出として残ります。
日記に必要なもの【ノートとえんぴつ】
日記を始めるのに、特別な道具は必要ありません。基本的にはノートと鉛筆(またはシャープペンシル)があれば十分です。ノートは、市販されている日記帳でなくても、大学ノートや好きなキャラクターのノートなど、お子さんが「これを使いたい!」と思うものを選ぶのがおすすめです。自分の好きなノートを使うことで、日記を書くことへのモチベーションが上がります。また、鉛筆だけでなく、消せるボールペンや色鉛筆を使ってみるのも楽しいでしょう。カラフルなペンで大切な部分を色分けしたり、イラストを描いたりすると、自分だけの特別な一冊になります。形から入るのも、楽しく続けるための一つの方法です。まずは、お気に入りの文房具を見つけるところから始めてみてはいかがでしょうか。
いつ書くのがいい?時間を決めて習慣にしよう
日記を続けるコツは、毎日書く時間を決めてしまうことです。例えば、「夜ご飯を食べた後」「お風呂から上がったら」「寝る前の10分間」など、生活のリズムの中に日記の時間を組み込んでしまうのです。時間を決めて習慣にすることで、歯磨きをするのと同じように、日記を書くことが当たり前になりやすくなります。もちろん、疲れている日や忙しい日に無理して書く必要はありません。書けない日があっても「まあ、いっか」と気楽に考えることも大切です。 もし書くのを忘れてしまっても、次の日に「昨日は書けなかったけど、こんなことがあった」と書いても大丈夫です。大切なのは、完璧に毎日書くことよりも、日記を書くことが嫌いにならないように、親子で楽しみながら続けることです。
【日記の書き方】小学校3年生がスラスラ書ける5つのステップ
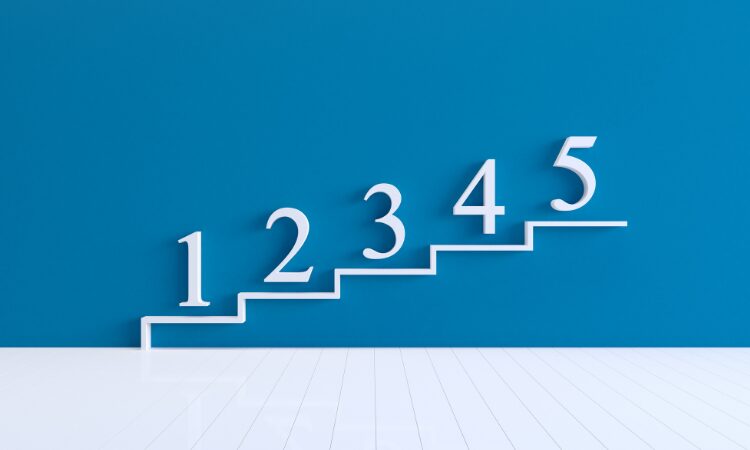
「日記を書こう!」と思っても、白いノートを前にすると何から書いていいか固まってしまうことがありますよね。そんな時は、順番にステップを踏んで考えていくと、驚くほど簡単に文章が作れるようになります。ここでは、小学校3年生のお子さんが一人でもスラスラ書けるようになるための、魔法の5つのステップをご紹介します。このステップに沿って進めれば、あなたも日記の名人になれるかもしれません。
ステップ1:今日の出来事を思い出す【何があったかな?】
まずは、今日一日、朝起きてから今までのことを順番に思い出してみましょう。難しく考えずに、どんな小さなことでもいいので、頭に浮かんだことをメモに書き出してみるのがおすすめです。
例えば、
- 朝ごはん、何を食べた?
- 学校へ行く途中で何を見た?
- 国語の授業で何を勉強した?
- 休み時間に誰と何をして遊んだ?
- 給食のメニューは何だった?
- 放課後はどこで過ごした?
- お家に帰ってから何をした?
- 家族とどんな話をした?
このように、一日の行動を振り返ることで、「あ、こんなことがあったな」と日記に書くネタがたくさん見つかります。全部を詳しく思い出す必要はありません。心に引っかかったことや、少しでも印象に残っていることをいくつかピックアップしてみましょう。
ステップ2:一番心に残ったことを選ぶ【主役を決めよう】
ステップ1で思い出したたくさんの出来事の中から、今日の日記の主役(テーマ)を一つだけ選びます。 全部のできごとを書こうとすると、話があちこちに飛んでしまい、何を伝えたいのか分かりにくい日記になってしまいます。 「楽しかったこと」「うれしかったこと」「くやしかったこと」「びっくりしたこと」など、自分の心が一番大きく動いた出来事を選ぶのがポイントです。 例えば、「休み時間に友達とドッジボールをしたこと」が一番楽しかったなら、それが今日の日記の主役です。主役が決まれば、日記の半分は完成したようなものです。何について書くかがはっきりすることで、この後の文章がとても書きやすくなりますよ。
ステップ3:5W1Hで詳しく書こう【いつ・どこで・だれが…】
日記の主役が決まったら、次はその出来事を詳しく書いていきましょう。ここで役に立つのが「5W1H」という合言葉です。 これは、文章を分かりやすくするための材料集めのようなものです。
- いつ(When): その出来事はいつありましたか?(例:2時間目の休み時間、放課後)
- どこで(Where): どこでありましたか?(例:学校の校庭で、教室で)
- だれが(Who): だれが登場しますか?(例:ぼくが、〇〇ちゃんと、クラスのみんなと)
- なにを(What): 何をしましたか?(例:ドッジボールをした、なわとびの練習をした)
- なぜ(Why): なぜそうなりましたか?(例:雨が上がったから、新記録を出したかったから)
- どのように(How): どんな様子でしたか?(例:みんなで力を合わせて、一生懸命に)
これら全てを無理に入れる必要はありませんが、いくつか意識して文章に入れるだけで、何があったのかがとても具体的に、読んでいる人に伝わるようになります。
ステップ4:思ったことや感じたことを書く【自分の気持ち】
日記で一番大切なのが、自分の気持ちを書くことです。 ただ出来事を報告するだけでなく、その時にあなたがどう感じたのかを言葉にすることで、日記はあなただけのかけがえのない記録になります。
「楽しかった」「うれしかった」だけでも十分ですが、もう少し詳しく書いてみると、より気持ちが伝わります。例えば、
- なぜそう感じたの?
- 例:「最後の最後にボールをキャッチできて、ヒーローみたいでうれしかった。」
- どんなふうに感じたの?
- 例:「心臓がドキドキするくらい、はらはらした。」
- 例:「みんなで勝てて、飛び上がるほどうれしかった。」
うれしいや楽しいといった気持ちだけでなく、くやしかったこと、悲しかったこと、不思議に思ったことなど、正直な気持ちを書くことが大切です。 日記はあなたの気持ちを整理するための場所でもあるのです。
ステップ5:明日したいことや目標を書く【未来への一言】
日記の最後は、明日への希望や次の目標を書いて締めくくると、とても前向きな気持ちで一日を終えることができます。 これは絶対に書かなければいけないものではありませんが、書くことで日記にまとまりが出ます。
例えば、
- 「今日は負けてくやしかったから、明日はもっと練習して勝ちたいな。」
- 「今日の鉄棒は楽しかったから、明日は新しい技にチャレンジしてみたい。」
- 「またみんなとドッジボールがしたいな。」
このように、未来に向けた一言を添えることで、明日が少し楽しみになるかもしれません。日記を単なる記録で終わらせず、未来の自分へのメッセージにするのも素敵な書き方の一つです。
【ネタ探し】日記の書き方に困らない!小学校3年生におすすめのテーマ

「毎日同じことのくり返しで、書くことがない…」そんな風に感じる日もありますよね。でも、アンテナを少し立ててみると、私たちの周りには日記のネタがたくさん隠れています。特別な出来事がなくても大丈夫。ここでは、小学校3年生のお子さんが日記のテーマを見つけるためのヒントをたくさんご紹介します。これを読めば、明日から「何を書こう?」と悩む時間がぐっと減るはずです。
学校での出来事を書こう
一日の大半を過ごす学校は、日記のネタの宝庫です。授業のこと、休み時間のこと、給食のことなど、少し視点を変えるだけでたくさんのテーマが見つかります。
例えば、
- 授業のこと: 算数の問題が解けてうれしかったこと、理科の実験でびっくりしたこと、図工で素敵な作品ができたこと、音楽で新しい歌を習ったこと、体育で新記録が出たことなど。
- 休み時間のこと: 友達とどんな遊びをしたか、どんな話で盛り上がったか、友達のすごいところを見つけたこと、少しケンカしてしまったけど仲直りしたこと。
- 給食のこと: 大好きなメニューが出てうれしかったこと、苦手なものを一口だけ頑張って食べたこと、おかわりができてラッキーだったこと。
- 係や当番の仕事: 黒板をきれいに消せて気持ちよかったこと、生き物のお世話で新しい発見があったこと。
何気ない学校生活の中にも、あなたの心が動いた瞬間がきっとあるはずです。
お家での出来事を書こう
お家での時間も、日記の素敵なテーマになります。家族との会話や、自分一人で過ごした時間の中にも、書き留めておきたい出来事はたくさんあります。
例えば、
- 家族との会話: お父さんやお母さんと話して面白かったこと、兄弟げんかをしてしまったこと、家族みんなでテレビを見て笑ったこと。
- お手伝い: お皿洗いを手伝って感謝されたこと、洗濯物をたたむのが上手になったこと。
- 晩ごはんのこと: 今日のメニューがどうして好き(または嫌い)なのか、作ってくれた人への感謝の気持ち。
- 自分の時間: 読んだ本やマンガの感想、見たアニメのあらすじと面白かったところ、ゲームで難しいステージをクリアしたこと、新しい絵を描いたこと。
お家でのリラックスした時間だからこそ、素直な気持ちを書きやすいかもしれません。
お出かけや特別な出来事を書こう
週末のお出かけや、季節の行事などは、日記の絶好のテーマになります。 こうした特別な日のことは、普段の日記よりも詳しく書きやすいかもしれません。五感をフル活用して、その時の様子を思い出してみましょう。
例えば、
- お出かけ: 公園で新しい遊具を見つけたこと、スーパーで珍しい野菜を見たこと、図書館で面白そうな本を借りたこと、おじいちゃん・おばあちゃんの家で過ごしたこと。
- 習い事: スイミングで級が上がったこと、ピアノで新しい曲が弾けるようになったこと、サッカーの試合でシュートを決めたこと。
- 旅行やイベント: 家族旅行で見た景色、遊園地で乗ったアトラクション、お祭りで食べたかき氷の味、キャンプで見た星空。
その時どんな音が聞こえたか、どんな匂いがしたか、何を見て、何を感じたかを詳しく書くと、読んだ人がその場にいるような生き生きとした日記になります。
自分の好きなことや考えたことを書こう
日記は、その日にあった出来事だけを書くものではありません。自分の頭の中で考えたことや、好きなものについてじっくり書くのも、とても面白いテーマになります。
例えば、
- 好きなものについて: 大好きなキャラクターの魅力、集めているカードやシールのこと、好きなアイドルのすごいところ。なぜそれが好きなのか理由を書くと、自分の気持ちが整理できます。
- もしも〇〇だったら: 「もしも空を飛べたらどこへ行きたいか」「もしも透明人間になったら何をするか」など、想像を膨らませて自由に書いてみましょう。
- 将来の夢: 今、将来何になりたいと思っているか、そのためにはどうすればいいかを考えてみる。
- ニュースを見て考えたこと: テレビのニュースや新聞で気になったことについて、自分はどう思ったかを書いてみる。
このように、自分の内面と向き合うテーマは、あなただけのオリジナルな日記を作るきっかけになります。
季節の行事や自然について書こう
私たちの周りの自然や季節の移り変わりも、日記の素晴らしいテーマです。毎日少しだけ周りに目を向けてみると、小さな変化に気づくことができます。
例えば、
- 天気のこと: 今日の空はどんな色だったか、雲はどんな形をしていたか、雨の音はどんな風に聞こえたか。
- 植物や生き物: 通学路に咲いていた花の名前、公園で見つけた虫の様子、家のペットの面白い行動。
- 季節の食べ物: 夏に食べたスイカの味、秋に拾ったどんぐり、冬に食べたお鍋の温かさ。
- 季節の行事: お正月のおもちつき、節分の豆まき、ひな祭り、七夕の短冊、クリスマス会のことなど。
季節を感じることで、日記の内容がより豊かになり、一年後に読み返したときに「この季節にはこんなことがあったな」と思い出す楽しみも増えます。
もっと上手になる!小学校3年生の日記の書き方レベルアップ術

日記を書き慣れてきたら、もう少しステップアップしてみませんか?ここでは、いつもの日記をさらに面白く、表現力豊かにするためのコツをご紹介します。ちょっとした工夫で、あなたの日記はもっと魅力的になります。難しいことではないので、できそうなものから一つずつ試してみてください。きっと、文章を書くのがもっと楽しくなりますよ。
いろいろな言葉を使ってみよう【表現力を豊かに】
いつも「楽しかったです」「すごかったです」だけで終わっていませんか?同じ気持ちでも、いろいろな言葉で表現することができます。 例えば、「楽しかった」という気持ちを表す言葉には、こんなものがあります。
- うれしかった
- わくわくした
- 気持ちがよかった
- 心がぽかぽかした
- おもしろかった
- 夢中になった
このように、自分の気持ちにぴったりの言葉を探してみるだけで、日記の表現がぐっと豊かになります。 最初は難しくても、国語の教科書や本に出てくる素敵な言葉を真似してみるのも良い練習になります。気持ちを表す言葉のリストを作っておいて、日記を書くときに見てみるのもおすすめです。
会話文を入れてみよう【「」を使ってみる】
日記の中に、友達や家族と話した言葉をそのまま入れてみると、その場の様子がもっと生き生きと伝わるようになります。 会話文を入れるときは、「」(かぎかっこ)を使いましょう。
【例文】
休み時間に、たろう君が「今日のドッジボール、ぼくたちのチームがぜったい勝つぞ!」と言いました。ぼくは「おう、まけないぞ!」と答えました。
このように会話を入れることで、ただ「ドッジボールをしました」と書くよりも、その時の楽しそうな雰囲気や、友達とのやり取りが目に浮かぶようになります。誰が何を言ったのかが分かるように書くのがポイントです。楽しかった会話や、びっくりした一言などを思い出して、ぜひ日記に取り入れてみてください。
絵やイラストを加えてみよう【絵日記も楽しい】
文章を書くのが少し苦手でも、絵を描くのが好きなら、絵日記に挑戦してみましょう。文章だけでは伝えきれない気持ちや、見たものをイラストで表現するのも素敵な方法です。例えば、その日の出来事を表す簡単なイラストを描いたり、自分の気持ちを顔の表情で描いてみたりするだけでも、日記が華やかで楽しい雰囲気になります。色鉛筆やカラーペンを使って色を塗ったり、お気に入りのシールを貼ったりするのも良いでしょう。文章と絵を組み合わせることで、世界に一つだけのあなたらしい日記帳が出来上がります。大切なのは、上手に描くことではなく、楽しく表現することです。
見直しをしてみよう【誤字脱字チェック】
日記を書き終わったら、最後に必ず一度読み返してみましょう。 これを「見直し」と言います。見直しをすることで、字の間違い(誤字)や、抜けている字(脱字)に気づくことができます。また、「ここの言い方は、こうした方が分かりやすいかな?」と、より良い表現を考えるきっかけにもなります。保護者の方に読んでもらって、分かりにくいところがないか聞くのも良い方法です。ただし、間違いを厳しく指摘しすぎると、書くのが嫌になってしまうこともあります。まずは、最後まで書き上げたことをたくさん褒めてあげることが大切です。見直しの習慣をつけることで、文章力が自然と向上していきます。
【保護者の方へ】小学校3年生のお子さんの日記の書き方をサポートするコツ

お子さんが日記の宿題で悩んでいるとき、保護者としてどのようにサポートすれば良いか迷うこともありますよね。ここでは、お子さんが楽しく日記を続けられるように、保護者の方ができるサポートのコツをいくつかご紹介します。大切なのは、お子さんの「書きたい」という気持ちを育むことです。
無理に書かせない【まずは楽しむことが大切】
日記が「やらなければいけない面倒なもの」になってしまうと、長続きしません。 まずは、日記を書くことの楽しさを感じてもらうことが何よりも大切です。疲れている日や、どうしても書く気分になれない日に、無理やり書かせるのは避けましょう。「今日は一行だけでも書いてみようか」「絵だけでも描いてみる?」など、ハードルを下げてあげる工夫も効果的です。「書けない日があってもいいんだ」とお子さんが思えることで、日記へのプレッシャーが軽くなります。書くことがないとお子さんが悩んでいたら、「今日、何か面白いことあった?」とインタビューのように質問して、一緒にネタ探しを手伝ってあげるのも良いでしょう。
たくさん褒めてあげよう【良いところを見つける】
お子さんが日記を書き上げたら、まずはたくさん褒めてあげてください。 文章のつたなさや漢字の間違いを指摘する前に、「毎日続けていてえらいね」「この表現、すごくいいね」「気持ちがよく伝わってくるよ」など、具体的な良いところを見つけて褒めることが、お子さんの自信とやる気につながります。特に、出来事だけでなく自分の気持ちが書けている部分や、新しく習った漢字を使おうとしている努力などに注目して褒めると、お子さんは「次も頑張ろう」と思えるようになります。日記は完璧な文章を書くためのものではなく、自分を表現するための練習の場だと捉え、温かく見守ってあげましょう。
親子で交換日記をしてみる【コミュニケーションのきっかけに】
お子さんだけが書くのではなく、親子で交換日記を始めるのも非常におすすめです。 親が楽しそうに日記を書いている姿を見せることで、お子さんにとって日記がより身近なものになります。また、交換日記は素晴らしいコミュニケーションのツールにもなります。普段はゆっくり話す時間がないことでも、日記を通して子どもの本音を知ることができたり、親の気持ちを伝えたりすることができます。 親が書く返事が、文章の書き方のお手本にもなります。子どもが書いた日記に対して、「お母さんもその時、こう思ったよ」と感想を返してあげることで、会話が広がり、書くことの楽しさを共有できるでしょう。
書いた内容を否定しない【安心できる場所に】
日記には、時に友達とのケンカや失敗談など、ネガティブな気持ちが書かれることもあります。そんな時、内容を頭ごなしに否定したり、叱ったりしないことが非常に重要です。日記は、お子さんにとって自分の本音を安心して吐き出せる場所であるべきです。たとえ「それはあなたが悪い」と思うような内容でも、まずは「そう思ったんだね」「くやしかったね」と、お子さんの気持ちに寄り添い、受け止めてあげる姿勢が大切です。日記を書いたことで叱られる経験をしてしまうと、子どもは正直な気持ちを書かなくなり、当たり障りのない内容しか書かなくなってしまいます。お子さんが安心して心の内をさらけ出せる場所として、日記を活用させてあげましょう。
まとめ:小学校3年生から始める日記の書き方で、書く力を育てよう

この記事では、小学校3年生のお子さんに向けた日記の書き方について、基本的なステップからネタ探しのヒント、さらに表現力を高めるコツまで、幅広くご紹介しました。
日記を書くことは、単に学校の宿題を終わらせるためだけのものではありません。 毎日の出来事や自分の気持ちを言葉にする練習を重ねることで、文章力や表現力、考える力が自然と育まれていきます。
はじめは「何を書けばいいかわからない」と戸惑うかもしれませんが、「一番心に残ったこと」を一つ選び、5W1Hを意識しながら、自分の「気持ち」を添えるというステップを踏めば、誰でも簡単に日記を書くことができます。特別な出来事がない日でも、学校や家での何気ない日常、自分の好きなことなど、身の回りにはたくさんのテーマが溢れています。
そして何より大切なのは、完璧を目指すのではなく、楽しんで続けることです。保護者の方は、お子さんの頑張りをたくさん褒め、書くことが好きになるようなサポートを心がけてあげてください。
日記という素晴らしい習慣を通して、お子さんの書く力を育て、親子のコミュニケーションを深めていきましょう。




コメント