「随筆を書きましょう」と聞いて、「何をどう書けばいいの?」と悩んでしまう小学生は多いかもしれません。作文や読書感想文とは少し違う「随筆」に、難しそうなイメージを持っている子もいるでしょう。しかし、随筆は自分の体験や考えを自由に表現できる、とても楽しい文章です。
この記事では、小学生のみなさんに向けて、随筆の書き方をやさしく、わかりやすく解説します。テーマの決め方から、文章を面白くするコツ、具体的な構成のステップまで、この記事を読めば「随筆って面白そう!」「自分でも書けそう!」と思えるはずです。さあ、一緒に随筆の世界をのぞいてみましょう。
小学生のための随筆入門!そもそも随筆ってどんな文章?

随筆の書き方を知る前に、まずは「随筆」がどんな文章なのかを知っておきましょう。作文や感想文との違いがわかると、もっと気軽に随筆に取り組めるようになりますよ。
そもそも随筆ってなあに?
随筆とは、作者が体験したことや、日々の生活の中で感じたり考えたりしたことを、自由な形式で書いた文章のことです。 エッセイと呼ばれることもあります。 大切なのは、筆者が「こう感じた」「こう思った」という気持ちや考えが書かれている点です。
例えば、「運動会でリレーの選手に選ばれてうれしかった」という体験(エピソード)に、「最後まであきらめないで走ることの大切さを学んだ」という自分の考えを加えると、それはもう立派な随筆になります。 難しいルールや決まりきった形式はないので、自分の心をのぞいて、思ったことや感じたことを素直に書き記すのが随筆の基本です。
作文や感想文との違いは?
「作文や感想文と何が違うの?」と疑問に思うかもしれませんね。大きな違いは、「体験」と「考え」の結びつきにあります。
- 作文:広い意味では随筆も作文の一種です。 しかし、学校で書くことが多い「できごとを説明する作文」は、体験したことを順番に書くことが中心になりがちです。一方、随筆は体験した事実だけでなく、そこから考えたことや感じたこと(意見・感想)に重点を置きます。
- 感想文:本を読んだり、映画を観たりした後に書くのが感想文です。きっかけとなる作品があり、それに対する自分の考えや感動を書きます。随筆は、きっかけが本や映画に限りません。日常のささいな出来事や、心に浮かんだことなど、あらゆるものがテーマになります。
つまり随筆は、自分の体験をきっかけにして、自分の考えや思いを自由に表現する文章だと言えるでしょう。
随筆を書くことの楽しさって?
随筆を書く一番の楽しさは、自分自身と向き合えることです。普段、何気なく過ごしていると忘れてしまいがちな「うれしかった気持ち」や「悔しかった思い」、「不思議に思ったこと」などを、文章にすることで改めて見つめ直すことができます。
また、自分の考えを整理して言葉にする練習にもなります。最初はうまく書けなくても、何度も挑戦するうちに、自分の気持ちを人に分かりやすく伝える力がついていくでしょう。何より、決まった書き方がないからこそ、自分らしい表現を見つける面白さがあります。まるで友達に話しかけるような気持ちで、楽しみながら書いてみてください。
小学生向け!随筆の書き方7つのステップ
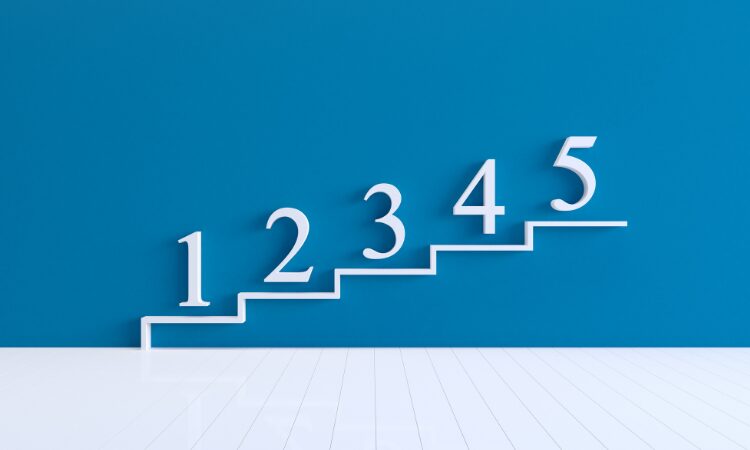
ここからは、実際に小学生が随筆を書くときの具体的な手順を7つのステップに分けて解説します。この順番で進めていけば、迷わずに書き進めることができますよ。
ステップ1:何を書くかテーマを決めよう
まず最初に、何について書くかテーマを決めます。 難しく考える必要はありません。「最近、心に残ったことは何かな?」と自分に問いかけてみましょう。
例えば、「新しく習い始めた逆上がり」「家族で行ったキャンプ」「友達とケンカして仲直りしたこと」など、自分の心が動いた出来事なら何でもテーマになります。 大きな出来事でなくても、「道ばたに咲いていたきれいな花を見て感動した」「給食のカレーがおいしくて幸せな気持ちになった」といった、ささいなことでも大丈夫です。大切なのは、自分が「書きたい!」と思えるテーマを選ぶことです。
ステップ2:構成メモで考えを整理しよう
テーマが決まったら、いきなり書き始めるのではなく、まず構成メモを作って、書きたいことを整理しましょう。 「はじめ・なか・おわり」の3つのパートに分けて、それぞれに何を書くか簡単なメモを作るのがおすすめです。
- はじめ:きっかけとなった出来事(いつ、どこで、何があったか)
- なか:その出来事の中で、特に心に残ったことや、その時の自分の気持ち(どうしてそう感じたのか)
- おわり:その体験を通して考えたこと、学んだこと、これからの自分について
例えば、「逆上がりができたこと」をテーマにするなら、「はじめ:公園で何度も練習したこと」「なか:悔しくて泣きそうになったけど、友達が応援してくれて頑張れたこと」「おわり:あきらめない気持ちが大切だと分かったこと」のように、箇条書きでメモしておくと、文章全体の話の流れがスムーズになります。
ステップ3:まずは自由に下書きをしてみよう
構成メモができたら、いよいよ文章を書いていきます。ここでは、誤字や表現などをあまり気にせず、まずは最後まで自由に書いてみることが大切です。ステップ2で作ったメモを見ながら、自分の言葉でどんどん書いていきましょう。
途中で言葉に詰まっても大丈夫です。思いつくままに、感じたままに書き進めてみてください。作文用紙に書く前に、ノートやプリントの裏などに下書きをするのがおすすめです。たくさん書いて、たくさん消して、自分らしい表現を探していきましょう。この段階では、完璧な文章を目指す必要はありません。
ステップ4:読者の心をつかむ「書き出し」を考えよう
下書きができたら、文章の顔となる「書き出し」を工夫してみましょう。最初の1文や2文で、読んだ人が「この先を読んでみたい!」と思えるような工夫ができると、随筆がぐっと面白くなります。
例えば、ただ「きのう、公園へ行きました」と始めるのではなく、「『もうやめたい』。僕の心の中で、弱虫な声がした」のように、その時の気持ちから書き始めると、読者は「何があったんだろう?」と興味を持ってくれます。ほかにも、印象的な会話文から始めたり、驚いたことから書き始めたりするのも良い方法です。色々な書き出しを試して、自分の文章に一番合うものを見つけてください。
ステップ5:体験や気持ちを「具体的に」書こう
文章の真ん中の部分(「なか」)では、体験したことや、その時に感じた気持ちを具体的に書くことを意識しましょう。 「楽しかった」「悲しかった」という言葉だけで終わらせずに、「なぜ、どのように」楽しかったのかを詳しく書くことがポイントです。
例えば、「キャンプが楽しかった」と書くだけでなく、「夜、みんなで見た星空が、まるで宝石箱をひっくり返したみたいにきれいで、息をするのも忘れるほどだった。隣にいたお父さんが『すごいなあ』とつぶやいた声が、なぜかうれしかった」のように書くと、読んだ人もその時の情景や気持ちを想像しやすくなります。
ステップ6:印象に残る「結び」で締めくくろう
物語の終わりが大切なように、随筆も「結び」の部分がとても重要です。ここで、体験を通して自分がどう変わったのか、何を学んだのかをまとめると、文章全体が引き締まります。
例えば、「逆上がりができた」という体験なら、「これからは、難しいことでもすぐに諦めないで挑戦していきたい」という決意で締めくくったり、「応援してくれた友達の大切さを改めて感じた」という感謝の気持ちで終わったりすることができます。書き出しと同じように、読者の心に響くような、印象的な言葉で締めくくることを目指しましょう。
ステップ7:声に出して読み返し、推敲(すいこう)しよう
文章が最後まで書けたら、必ず読み返しをしましょう。 この作業を「推敲(すいこう)」と言います。誤字や脱字がないかはもちろん、文章のリズムがおかしくないか、読みにくい部分はないかをチェックします。
おすすめなのは、声に出して読んでみることです。声に出すと、黙読では気づかなかった不自然な点や、読点(、)を打つべき場所が分かりやすくなります。「そして」を使いすぎていないか、同じ言葉を繰り返し使っていないかなども確認しましょう。 最後に、きれいな字で清書をすれば、あなたの随筆の完成です。
これで迷わない!小学生におすすめの随筆テーマ集

「何について書けばいいか、やっぱり思いつかない…」という人のために、小学生が書きやすい随筆のテーマをいくつか紹介します。ここからヒントを得て、自分だけのテーマを見つけてみてください。
学校生活のできごと
毎日通う学校は、随筆のテーマの宝庫です。普段は当たり前だと思っていることでも、じっくり考えてみると、面白い発見があるかもしれません。
- 授業中の発見:「理科の実験で驚いたこと」「図工の作品作りで工夫したこと」「苦手な算数が少しだけ分かった瞬間」など、授業の中で心が動いた瞬間をテーマにしてみましょう。
- 休み時間の思い出:「友達と夢中になって遊んだドッジボール」「係の仕事で協力したこと」「一人で本を読んでいて考えたこと」など、休み時間の何気ない一コマも立派なテーマになります。
- 行事の体験:「運動会で感じた悔しさと喜び」「遠足で見た景色」「音楽会で心を一つにして演奏したこと」など、特別な行事は、自分の成長や考えの変化を書きやすいテーマです。
家族や友達とのこと
一番身近な存在である家族や友達との出来事も、随筆の素晴らしいテーマになります。 その人との関係を通して、自分が何を感じ、考えたのかを掘り下げてみましょう。
- 家族との会話:「お母さんにしかられて反省したこと」「おじいちゃんから昔の話を聞いて思ったこと」「きょうだいとケンカしたけれど、やっぱり大切だと感じたこと」など、家族とのやり取りにはたくさんの気づきが隠されています。
- 友達との関わり:「友達のすごいところを見つけて尊敬したこと」「ささいなことで気まずくなったけど、勇気を出して謝れたこと」「新しい友達ができて世界が広がったこと」など、友情について考えてみるのも良いでしょう。
- ペットとのふれあい:犬や猫、小鳥などのペットを飼っているなら、その世話を通して感じた命の大切さや、ペットとの心温まるエピソードも素敵なテーマになります。
季節の行事や自然の観察
季節の移り変わりや、それに伴う行事、そして身の回りの自然に目を向けることも、随筆のテーマを見つけるきっかけになります。
- 季節の楽しみ:「夏休みの虫取りで学んだこと」「秋に見つけたきれいな落ち葉の色について」「冬の朝の空気の冷たさと気持ちよさ」など、季節ごとの変化を感じたままに書いてみましょう。
- 行事での体験:「お正月に親戚と集まって感じたこと」「クリスマスプレゼントをもらった時のわくわくした気持ち」「節分の豆まきで考えた鬼の気持ち」など、行事を通して考えたことを深めてみましょう。
- 自然のふしぎ:「雨上がりの虹を見て感動したこと」「道端の草花が力強く咲いているのを見て思ったこと」「夕焼け空の色の変化を観察して考えたこと」など、自然の美しさや不思議さをテーマにすると、豊かな表現が生まれやすくなります。
好きなこと・夢中になっていること
自分が「大好き!」と思えることや、時間を忘れるほど夢中になれることについて書くのは、とても楽しい作業です。自分の「好き」という気持ちを、読者にも伝わるように表現してみましょう。
- 趣味や習い事:「サッカーの練習でシュートが決まった時の快感」「ピアノの発表会で緊張したけど、弾き終えた時の達成感」「ゲームをクリアするために工夫したこと」など、自分の努力や成長の過程を書くことができます。
- 好きな本やアニメ:好きな物語の登場人物について、「自分だったらどうするだろう」と考えてみたり、作者が伝えたかったメッセージを自分なりに解釈してみたりするのも、面白い随筆になります。
- 将来の夢:「どうしてその職業に就きたいのか」「その夢をかなえるために、今がんばっていること」「夢を通してどんな人になりたいか」など、自分の未来について考えることも、自分自身を見つめる良い機会になります。
もっと面白くなる!小学生の随筆がレベルアップする書き方のコツ

基本的な書き方が分かったら、次は文章をさらに面白く、表現豊かにするためのコツを紹介します。少し意識するだけで、あなたの随筆がぐっと魅力的になりますよ。
五感をフル活用して表現しよう
文章を生き生きとさせるには、五感(見た・聞いた・におった・味わった・さわった)を使って書くことが効果的です。ただ「海へ行った」と書くのではなく、五感で感じたことを加えることで、読者はその場にいるような気持ちになれます。
- 見た(視覚):キラキラ光る波、どこまでも続く青い空、砂浜の貝殻の形
- 聞いた(聴覚):ザアザアという波の音、カモメの鳴き声、人々の楽しそうな笑い声
- におった(嗅覚):潮の香り、日焼け止めのにおい
- 味わった(味覚):しょっぱい海水、お昼に食べたすいかの甘さ
- さわった(触覚):熱い砂の感触、ひんやりした水の冷たさ
このように、五感で感じたことを具体的に描写することで、文章に臨場感が生まれます。
会話文や心の声を入れてみよう
文章の中に、登場人物の会話文や、自分の心の声(思ったこと・感じたこと)を入れると、文章に動きが出て読みやすくなります。
例えば、「友達が『がんばれ!』と応援してくれた。僕はうれしかった」と書く代わりに、「『あと少し!がんばれ!』友達の声が聞こえた。その声を聞いて、僕の心に温かい火がともったようだった。よし、絶対にあきらめないぞ」のように書くと、その時の状況や気持ちがより鮮明に伝わります。会話文は「」を使い、心の声は地の文に混ぜ込んだり、「()」を使ったりして工夫してみましょう。
いろいろな言葉を使ってみよう
いつも同じ言葉ばかり使っていると、文章が単調になってしまいます。特に、物事の様子を表す言葉を豊かにすると、表現の幅が広がります。
- 擬音語・擬態語(オノマトペ):「雨がしとしと降る」「心臓がドキドキする」「太陽がぎらぎら輝く」など、音や様子を表す言葉を使うと、文章がリズミカルで楽しくなります。
- 比喩(たとえ):「雪のように白い肌」「鬼のような形相」など、他のものにたとえる表現を使うと、読者がイメージしやすくなります。難しく考えずに、「〇〇みたい」「〇〇のようだ」という形から使ってみましょう。
国語辞典や類語辞典を使って、いろいろな言葉を探してみるのもおすすめです。
小学生が随筆の書き方で気をつけたい3つのポイント

最後に、随筆を書くときに少しだけ気をつけてほしいポイントを3つお伝えします。これらを守ることで、より良い随筆に仕上がります。
うそは書かず、正直な気持ちを書く
随筆は、自分の体験や考えを書く文章です。 そのため、うそや作り話を書くのはやめましょう。自分をよく見せようとしたり、面白い話にしようとして事実と違うことを書いたりすると、文章に心がこもらなくなり、読者にも伝わってしまいます。
たとえ、かっこ悪い経験や失敗談であっても、その時に感じた正直な気持ちを書くことが大切です。うまくいかなかった経験から何を学んだのか、どうして失敗してしまったのかを考えることで、随筆はより深みを増します。自分に正直であることが、良い随筆を書くための第一歩です。
できごとの「あらすじ」だけにならないようにする
随筆を書くときにありがちなのが、体験した出来事を最初から最後まで説明するだけの「あらすじ」のようになってしまうことです。例えば、「朝起きて、学校へ行って、勉強して、家に帰りました」というだけでは、ただの報告になってしまいます。
大切なのは、その出来事を通して「自分が何を感じ、何を考えたか」という部分です。 たくさんの出来事を書こうとせず、一番心が動いた場面にしぼって、その時の気持ちや考えを詳しく書くようにしましょう。「なぜそう感じたのか」「その経験から何を学んだのか」を掘り下げることが、随筆の面白さにつながります。
難しく考えすぎず、楽しんで書く
随筆には、こう書かなければいけないという厳密なルールはありません。 「上手に書かなきゃ」「良いことを書かなきゃ」と難しく考えすぎてしまうと、書くこと自体が楽しくなくなってしまいます。
まずは、楽しんで書くことを一番に考えましょう。自分の心の中を探検するような気持ちで、思いついたこと、感じたことを自由に書き出してみてください。友達におしゃべりするような感覚で、のびのびと表現することを楽しんでください。 あなたにしか書けない、あなただけの素敵な随筆がきっと生まれるはずです。
【まとめ】小学生のための随筆の書き方をマスターしよう

この記事では、小学生のみなさんが楽しく随筆を書けるように、その意味や書き方のステップ、テーマの見つけ方やレベルアップのコツなどを詳しく解説してきました。
随筆とは、自分の体験をもとに、感じたことや考えたことを自由に書く文章です。大切なのは、事実を報告するだけでなく、その出来事を通して自分の心がどう動いたのかを表現することです。
書き方に迷ったら、まずは「テーマ決め」「構成メモ」「下書き」というステップを踏んで、考えを整理することから始めましょう。そして、五感を使ったり、会話文を入れたりする工夫をすることで、あなたの文章はもっと生き生きとしてきます。
難しく考えすぎず、自分に正直に、書くことを楽しむ気持ちを忘れないでください。この記事を参考にして、あなただけの素敵な随筆を書いてみましょう。

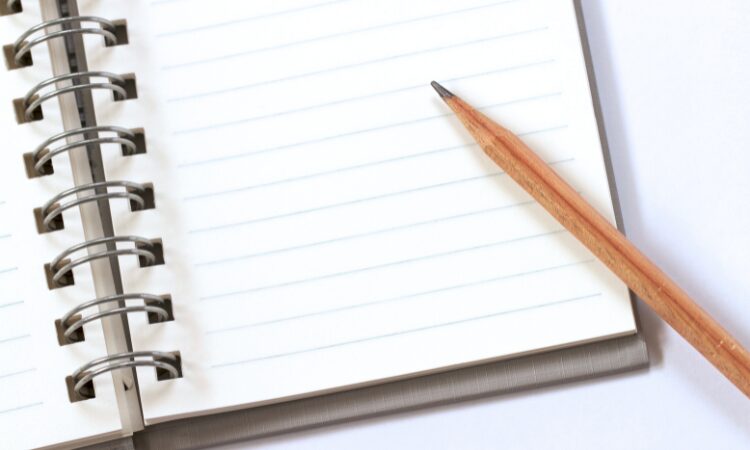
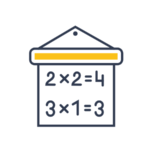

コメント