中学校の卒業文集や国語の課題で、「3年間の思い出」をテーマにした作文を書く機会は多いですよね。楽しかった体育祭、悔し涙を流した部活動の大会、友達と笑い合った何気ない日常。たくさんの思い出がよみがえってくるけれど、「いざ作文にしようとすると、何から書けばいいのか分からない」とペンが止まってしまう人もいるのではないでしょうか。
この記事では、そんな悩める中学生の皆さんのために、3年間の思い出を素敵な作文にするための具体的な方法を、やさしくわかりやすく解説していきます。まずは何を書くかを見つける準備から始め、読んだ人の心に残る構成の作り方、そして表現力をアップさせるコツまで、順番に見ていきましょう。部活動や学校行事など、テーマ別の例文も紹介するので、自分にぴったりの書き方がきっと見つかります。この記事を読めば、あなただけのかけがえのない3年間の思い出を、自信を持って言葉にできるようになりますよ。
3年間の思い出を作文にする前に!中学生がやるべき準備
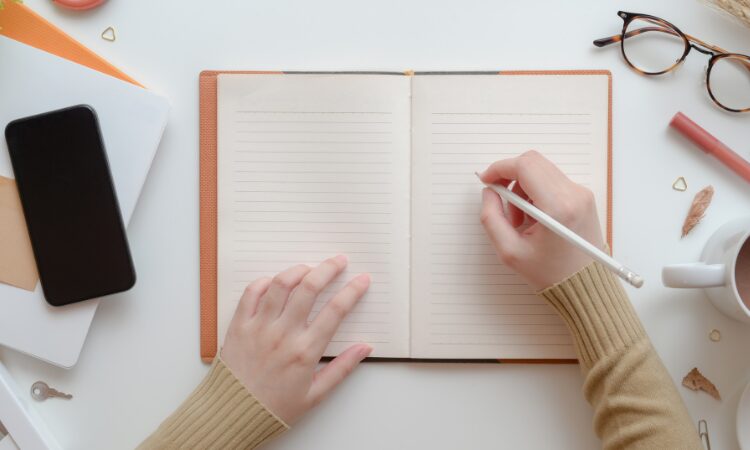
作文を書き始める前に少し準備をするだけで、驚くほどスムーズにペンが進むようになります。いきなり原稿用紙に向かうのではなく、まずは頭の中にあるたくさんの思い出を整理することから始めましょう。
まずは3年間の出来事を書き出してみよう
まずは、中学校生活3年間で経験したこと、心に残っていることを、思いつくままに紙やノートに書き出してみましょう。大きな出来事だけでなく、些細なことでも構いません。「楽しかった」「悔しかった」「嬉しかった」「悲しかった」など、感情が動いた瞬間を思い返してみるのがポイントです。
例えば、以下のような切り口で考えると、たくさんの思い出が浮かび上がってくるはずです。
・学校行事:体育祭、文化祭、合唱コンクール、修学旅行、遠足など
・部活動:練習、大会、先輩や後輩との関係、顧問の先生の言葉など
・勉強:苦手だった教科の克服、テストの成績、授業中の面白い出来事など
・友達とのこと:休み時間の会話、一緒に下校した道、喧嘩と仲直りなど
・委員会活動や生徒会活動:責任ある仕事、仲間との協力など
このように、まずは質より量を意識して、たくさんの思い出のかけらを集めてみてください。この作業が、あなたの作文の「材料」になります。
一番心に残っているエピソードを選ぶ
たくさんの思い出を書き出したら、次はその中から作文のメインとなるエピソードを一つか二つに絞り込みます。 すべての思い出を盛り込もうとすると、内容が浅く、何を伝えたいのかが分かりにくい作文になってしまうからです。
選ぶ基準は、「自分の心が最も大きく動いた出来事」です。例えば、「部活動最後の大会で負けて悔しかった」という思い出は、「なぜ悔しかったのか」「その時、仲間や先生とどんな言葉を交わしたのか」「その経験を通して何を学んだのか」など、深く掘り下げて書くことができます。
成功した体験だけでなく、失敗した体験や悔しかった思い出も、あなたの成長が伝わる良いテーマになります。 自分がその出来事を通してどう感じ、どう変わったのかを具体的に書けそうなエピソードを選んでみましょう。
作文のテーマ(伝えたいこと)を決める
メインのエピソードが決まったら、そのエピソードを通して読者に「何を一番伝えたいのか」というテーマを明確にします。 テーマとは、作文全体の背骨のようなものです。これがあることで、文章に一貫性が生まれ、読者の心に響く内容になります。
例えば、「部活動最後の大会」をエピソードに選んだ場合、テーマは以下のように様々考えられます。
・「仲間の大切さ」:チーム一丸となって戦った経験から学んだこと。
・「努力の重要性」:毎日続けた厳しい練習が自分をどう成長させたか。
・「感謝の気持ち」:支えてくれた仲間、先生、家族への感謝。
・「諦めない心」:試合には負けたけれど、最後まで全力を尽くしたことの価値。
「この作文を読み終えた人に、どんな気持ちになってほしいか」を考えると、テーマが見つけやすくなります。決めたテーマは、作文を書いている途中で何度も見返せるように、メモしておくと良いでしょう。
誰に読んでもらいたいかを意識する
最後に、この作文を「誰に読んでもらいたいか」を具体的にイメージしてみましょう。卒業文集であればクラスメイトや先生、後輩たちかもしれませんし、コンクールなら全く知らない人が読むことになります。
読む相手を意識することで、言葉遣いや説明の丁寧さが変わってきます。 例えば、クラスメイトが読むなら共通の思い出として省略できる部分も、知らない人が読む場合は、状況を詳しく説明する必要があります。
特に、お世話になった先生や、一緒に頑張ってきた友達、いつも支えてくれた家族など、特定の誰かに向けて書くことを意識すると、感謝の気持ちなどがより具体的に、そして素直に表現しやすくなります。手紙を書くような気持ちで、伝えたい相手の顔を思い浮かべながら構成を考えると、温かみのある作文になりますよ。
中学生必見!3年間の思い出が伝わる作文の構成
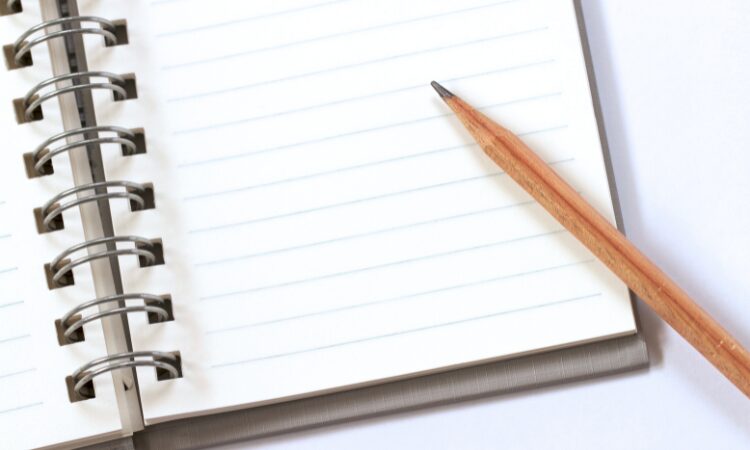
作文には、読みやすく、内容が伝わりやすい「型」があります。一般的に「序論・本論・結論」という三つの部分で構成するのが基本です。 この構成に沿って書くことで、話があちこちに飛ばず、まとまりのある文章になります。
読者を引き込む「書き出し」のコツ
「書き出し」は、作文の第一印象を決める非常に重要な部分です。ここで読者の興味を引くことができるかどうかで、最後まで読んでもらえるかが決まるといっても過言ではありません。
ありがちな「中学校の三年間で一番心に残っているのは、〇〇です。」という書き出しも悪くはありませんが、少し工夫するだけで、ぐっと魅力的な文章になります。例えば、次のような書き出し方を試してみてはいかがでしょうか。
・情景描写から始める:「じりじりと太陽が照りつけるグラウンドで、僕たちの声だけが響いていた。」
・印象的な会話から始める:「『最後まで諦めるな!』先生のその一言が、今でも耳に残っている。」
・問いかけから始める:「『努力は必ず報われる』という言葉を、皆さんは信じますか。」
・最も伝えたいいちばんの気持ちから始める:「悔しい。今思い出しても、あの時の気持ちはそれだけだ。」
このように、具体的な場面や感情から書き始めることで、読者は一気に物語の世界に引き込まれます。 何があったんだろう?と、続きが気になるような書き出しを考えてみましょう。
具体的なエピソードで膨らませる「中盤」
「中盤」は作文の心臓部であり、最も文字数を割く部分です。ここで、書き出しで提示したテーマについて、具体的なエピソードを交えながら詳しく説明していきます。
ただ出来事を順番に説明するだけでなく、その時々の「自分の行動」や「心の動き」を丁寧に描写することが大切です。
・行動の描写:ただ「練習を頑張った」と書くのではなく、「毎日誰よりも早く朝練に来て、日が暮れるまで自主練習を続けた」というように、具体的に何をしたのかを書きます。
・心の動きの描写:「嬉しかった」だけで終わらせず、「飛び上がるほど嬉しくて、思わず仲間と抱き合った。努力が報われた瞬間だった」のように、なぜそう感じたのか、その結果どうしたのかまで書くと、気持ちがより鮮明に伝わります。
また、自分だけでなく、周りの友達や先生の言動を描写することも効果的です。例えば、「『お前ならできる』と背中を押してくれた友人の言葉があったから、最後まで頑張れた」といったように、他者との関わりを入れることで、エピソードに深みと客観性が生まれます。
感動を誘う「締めくくり」の書き方
「締めくくり」は、作文全体のまとめの部分です。中盤で書いたエピソードを振り返り、そこから何を学び、今後どうしていきたいのかを述べて、文章を締めくくります。
書き出しと関連性を持たせると、文章全体にまとまりが生まれます。例えば、書き出しで「努力は必ず報われるという言葉を信じますか」と問いかけたなら、締めくくりで「大会では負けてしまったけれど、仲間と努力した日々は、優勝以上の価値があった。だから僕は、努力は必ず報われると、胸を張って言える」というように、自分なりの答えを示すことができます。
さらに、中学校生活での経験を、これからの高校生活や将来にどう活かしていきたいかという、未来への抱負を述べるのも良い締め方です。 「この3年間で学んだ〇〇を胸に、高校では△△に挑戦したい」といった前向きな言葉で終えることで、読者に明るい希望や感動を与えることができます。
【テーマ別】3年間の思い出を彩る中学生の作文例文

ここでは、中学生の皆さんが作文のテーマにしやすい「部活動」「学校行事」「勉強」「友達との日常」という4つのテーマで、具体的な例文と書く際のポイントを解説します。自分自身の経験と照らし合わせながら、作文作りの参考にしてください。
部活動の思い出
部活動は、喜びも悔しさも分かち合った仲間との思い出が詰まった、作文のテーマの宝庫です。ただ試合の結果を書くだけでなく、そこに至るまでの過程や、仲間との絆、自分自身の成長を中心に書くことがポイントです。
(例文)
「もうダメだ」。ラケットを握る手に力が入らなくなり、膝から崩れ落ちそうになった。地区大会決勝、スコアは0対2。あと1点で、僕たちの中学校最後の夏が終わる。その時、「顔を上げろ!」とキャプテンの声が飛んだ。見ると、仲間たちがまっすぐに僕を見つめている。「お前を信じてる」。その言葉に、体中の細胞が奮い立つような感覚がした。僕はもう一人じゃない。このチームで1秒でも長くプレーしたい。その一心で、再びラケットを強く握り直した。結果的に試合には敗れたが、僕の心には悔しさよりも、最高の仲間と最後まで戦い抜いた誇りが温かく残っている。この経験から学んだ「仲間を信じる心」は、僕の一生の宝物だ。高校でも、この気持ちを忘れずに新しい挑戦をしていきたい。
・ポイント解説:試合の勝敗という結果だけでなく、追い詰められた場面での心情の変化や、キャプテンの言葉という具体的な出来事に焦点を当てています。そして、その経験から「仲間を信じる心」という学びを得て、それを将来につなげようとする前向きな姿勢で締めくくっているのが特徴です。
学校行事(体育祭・文化祭)の思い出
体育祭や文化祭などの学校行事は、クラスが一丸となって一つの目標に向かう貴重な体験です。成功した喜びや、準備段階での苦労、クラスメイトとの協力などを具体的に描くことで、生き生きとした作文になります。
(例文)
文化祭のクラス劇で、主役を演じることになった。もともと人前に立つのが苦手な私にとって、それは大きな挑戦だった。セリフはうまく覚えられず、声も小さくて、練習では迷惑ばかりかけてしまった。「私じゃ無理かもしれない」。弱音を吐いた私に、クラスメイトのAさんが「大丈夫、私たちがついてるから」と励ましてくれた。それから毎日、Aさんは私の自主練習に付き合ってくれた。他のクラスメイトも、大道具や衣装作りを一生懸命進めてくれていた。みんなの期待に応えたい。その思いが、私の背中を押してくれた。本番、スポットライトを浴びた瞬間は足が震えたけれど、客席で応援してくれるみんなの顔が見えた時、すっと恐怖が消えた。劇が成功した時の、割れんばかりの拍手は今でも忘れられない。この経験を通して、仲間と協力することの素晴らしさと、一歩踏み出す勇気の大切さを学んだ。
・ポイント解説:単に「文化祭が楽しかった」で終わらせず、「人前に立つのが苦手」という自分の課題と、それをクラスメイトの支えによってどう乗り越えたか、という成長の過程を具体的に描いています。Aさんの言葉や行動を入れることで、文章にリアリティが生まれています。
勉強や苦手克服の思い出
勉強は、毎日の積み重ねが大切な活動です。すぐに結果が出ない苦しさや、目標を達成した時の達成感など、自分自身との戦いをテーマにすることで、読者の共感を呼ぶことができます。
(例文)
中学1年生の時、私の数学のテストはいつも平均点以下だった。複雑な公式や図形問題を見るだけで、頭が真っ白になってしまう。そんな私が、数学を「面白い」と感じるようになったのは、数学担当のT先生のおかげだ。先生は、私が質問に行くと、どんなに忙しくても丁寧に教えてくれた。「数学は、一つずつ順を追って考えれば、必ず答えにたどり着けるパズルみたいなものだよ」。先生のその言葉に、私は少しだけ勇気をもらった。それからは、毎日1時間、数学の勉強をすると決めた。最初は苦痛だったが、少しずつ問題が解けるようになると、パズルを解くような楽しさを感じるようになった。そして3年生の最後のテストで、初めて90点を取ることができた。答案用紙の「90」という数字を見た時、思わずガッツポーズをした。諦めずに続ければ、苦手なことでも克服できる。この自信は、これからの人生で困難にぶつかった時、きっと私を支えてくれるだろう。
・ポイント解説:苦手だった数学を、T先生の言葉をきっかけに克服していく過程が具体的に描かれています。「パズルみたいなもの」という比喩表現も効果的です。点数が上がったという結果だけでなく、数学に対する気持ちが「苦手」から「面白い」へと変化した内面の成長を丁寧に書くことが重要です。
友達との何気ない日常の思い出
大きな事件や行事だけでなく、友達と過ごした何気ない日常の中にも、かけがえのない思い出はたくさんあります。休み時間の会話や、一緒に帰った放課後の道など、具体的な場面を切り取ることで、温かい作文になります。
(例文)
私にとって中学校生活の思い出は、友達のBさんと過ごした放課後の図書室だ。これといった目的があるわけでもなく、ただお互いが好きな本を読み、時々顔を見合わせては、今日あった他愛もない出来事を報告し合う。テストの悩みを打ち明けたり、好きな音楽の話で盛り上がったり。静かな時間が流れる図書室は、私たちだけの特別な空間だった。ある日、進路のことで悩んでいた私に、Bさんは黙って一冊の本を差し出してくれた。その本の主人公が、困難を乗り越えて夢を叶える物語だった。「あなたなら大丈夫だよ」。言葉はなくても、Bさんの応援する気持ちが伝わってきて、胸が熱くなった。特別なイベントがあったわけではない。でも、私の3年間は、そんな穏やかで優しい時間に支えられていた。高校に進学して離れ離れになっても、この図書室での思い出は、きっと私を温め続けてくれるだろう。
・ポイント解説:図書室という具体的な場所を設定し、そこでの友達との静かな交流を描写することで、二人の関係性の深さが伝わってきます。Bさんが言葉ではなく本で励ますというシーンが、文章に深みを与えています。派手な出来事でなくても、自分にとってその時間がどれだけ大切だったかを丁寧に書くことで、読者の心に残る作文になります。
表現力アップ!中学生の作文で3年間の思い出をより魅力的に

同じエピソードでも、表現の仕方を少し工夫するだけで、作文はもっと生き生きと、読者の心に響くものになります。ここでは、あなたの作文をワンランクアップさせるための、具体的なテクニックをいくつか紹介します。
五感を使った表現を取り入れよう(情景描写)
出来事を説明するとき、「見る(視覚)」「聞く(聴覚)」「嗅ぐ(嗅覚)」「味わう(味覚)」「触れる(触覚)」といった五感を使った表現を入れると、読者はまるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができます。
例えば、「体育祭で応援した」と書く代わりに、
・視覚:「クラスカラーの青いハチマキが、青空に映えていた」
・聴覚:「グラウンドに響き渡る応援の声と、スタートを告げる乾いたピストルの音」
・嗅覚:「汗と土埃の匂いが混じり合った、グラウンドの独特な香り」
・触覚:「じりじりと肌を焼くような夏の太陽の光」
といった描写を加えるだけで、情景が目に浮かぶようになります。すべてを入れる必要はありませんが、特に印象に残っている感覚を一つでも加えることを意識してみてください。
会話文を効果的に使って臨場感を出す
作文の中に会話文を入れると、文章にリズムが生まれ、場面が活気づきます。 特に、その時の気持ちを象徴するような友達や先生の一言、仲間と交わした掛け声などを入れると非常に効果的です。
例えば、「先生に励まされた」と書くよりも、「『君なら絶対にできる』。先生は私の肩をぽんと叩いて、力強くそう言ってくれた」と書く方が、先生の温かさや、自分がどれだけ勇気づけられたかが具体的に伝わります。
ただし、会話文を多用しすぎると、かえって文章が散漫になってしまうこともあります。ここぞという場面で、最も印象的だった言葉を効果的に使うのがポイントです。会話文を入れる際は、改行して「」を使うなど、原稿用紙の正しい使い方にも注意しましょう。
自分の気持ちの変化を丁寧に描く
作文で一番伝えたいのは、出来事そのものよりも、その経験を通して「自分がどう感じ、どう成長したか」ということです。そのためには、心の動きを丁寧に描写することが欠かせません。
例えば、最初は「面倒だな」と思っていた行事が、練習を重ねるうちに「楽しくなってきた」、そして本番が終わった時には「最高の思い出になった」というように、気持ちが変化していく過程を具体的に書きましょう。
「なぜそう感じたのか」という理由も付け加えると、より説得力が増します。「最初は面倒だと思っていた。なぜなら、人前で何かをするのが苦手だったからだ。しかし、仲間が励ましてくれたことで、少しずつ自信がついていった」というように、心の動きを段階的に説明することで、読者はあなたの成長の物語に感情移入しやすくなります。
比喩や擬人法など表現技法を使ってみる
国語の授業で習うような表現技法を少し使ってみるのも、文章を豊かにする良い方法です。難しく考える必要はありません。身近なものに例える「比喩」を使ってみましょう。
・直喩(~のようだ、~みたいだ):「心臓が張り裂けそうなくらい、ドキドキした」→「まるで時計の秒針のように、心臓が大きく速く脈打っていた」
・隠喩(~は~だ):「時間はあっという間に過ぎた」→「3年間という時間は、まさに光の速さで駆け抜けていった」
また、人間でないものを人間に見立てる「擬人法」も、生き生きとした表現につながります。
・「校庭の桜が咲いた」→「校庭の桜が、僕たちの入学を優しく微笑んで迎えてくれた」
これらの表現を少し加えるだけで、ありきたりな文章が、あなただけのオリジナルな表現に変わります。辞書を引いたり、好きな本の表現を参考にしたりするのも良い勉強になりますよ。
まとめ:あなただけの中学生生活3年間の思い出を作文に

この記事では、中学生の皆さんが「3年間の思い出」をテーマにした作文を書くための、準備から構成、具体的な書き方、そして表現力を高めるコツまでを解説してきました。
作文を書く上で最も大切なのは、上手な文章を書こうと気負いすぎず、自分自身の素直な気持ちと向き合うことです。まずは3年間の出来事を一つひとつ思い出し、その中で最も心が動いたエピソードを選んでみましょう。そして、「序論・本論・結論」という基本的な構成に沿って、その経験から何を学び、どう成長できたのかを自分の言葉で綴っていくことが重要です。
部活動、学校行事、勉強、友達との日常、どんなテーマであっても、あなたにしか書けない貴重な体験がそこにはあります。この記事で紹介したポイントや例文を参考にしながら、あなただけのかけがえのない中学校生活3年間の思い出を、ぜひ素敵な作文にしてください。




コメント