6年間の長いようで短かった小学校生活も、もうすぐ終わり。卒業を前に「小学校6年間の思い出」をテーマにした作文や卒業文集を書く機会がやってきます。楽しかったこと、頑張ったこと、ちょっぴり悔しかったこと、たくさんの出来事があったはずです。しかし、いざペンを持つと「何から書けばいいんだろう?」「どうすれば気持ちが伝わる文章になるのかな?」と悩んでしまう人も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな皆さんのために、小学校6年間の思い出を素敵な作文にするためのヒントを、やさしくわかりやすく解説します。思い出の探し方から、読んだ人の心に残る構成の作り方、そして具体的な表現のコツまで、この記事を読めば、あなただけの特別な作文がきっと書けるはずです。さあ、一緒に6年間の宝物のような思い出を、言葉にしていきましょう。
小学校6年間の思い出を作文に!まずは準備から始めよう

いきなり原稿用紙に向かっても、なかなか筆は進まないものです。まずは、作文を書き始める前の準備が大切です。6年間のたくさんの思い出の中から、何を書くのか、誰に伝えたいのかをじっくり考える時間を取りましょう。この準備をしっかりすることで、作文の方向性が決まり、スムーズに書き進めることができます。
まずは思い出を全部書き出してみよう
頭の中だけで思い出そうとすると、忘れてしまっていることも多いものです。そこで、まずは紙とペンを用意して、小学校6年間であったことを、思いつくままに全部書き出してみましょう。「ブレインストーミング」という方法です。
例えば、「楽しかったこと」「頑張ったこと」「悔しかったこと」「友達とのこと」「先生とのこと」「家族とのこと」のように、テーマを分けて書き出すと、思い出しやすくなります。 低学年の頃のかわいらしい思い出から、高学年になって挑戦した難しいことまで、どんなに小さなことでも構いません。入学式、運動会、遠足、修学旅行などの大きな行事はもちろん、休み時間に友達と夢中になって遊んだこと、給食の時間のこと、係の仕事で大変だったことなど、日常の何気ない場面にも、あなただけの特別な思い出が隠れているはずです。
この作業をすることで、自分でも忘れていた大切な出来事や感情を思い出すきっかけになります。書き出したリストを眺めているうちに、作文のテーマにしたい「これだ!」というエピソードがきっと見つかるでしょう。
心に残ったエピソードを3つ選ぶ
たくさんの思い出を書き出したら、その中から特に心に残っているエピソードを3つほど選んでみましょう。 なぜなら、たくさんのことを少しずつ書こうとすると、一つひとつの内容が薄くなってしまい、読んだ人の印象に残りづらくなってしまうからです。
選ぶ基準は、「一番楽しかったこと」だけではありません。「一番悔しかったこと」「一番頑張ったこと」「一番感動したこと」など、自分の気持ちが大きく動いた出来事を選んでみてください。 例えば、リレーの練習を毎日頑張ったけれど負けてしまって悔し涙を流したこと、苦手な算数のテストで初めて100点を取れて飛び上がるほど嬉しかったことなど、具体的な感情が伴うエピソードは、作文に深みを与えてくれます。
この3つのエピソードが、あなたの作文の「柱」となります。それぞれの出来事で「何があったのか」「その時どう感じたのか」「その経験から何を学んだのか」を少し掘り下げてメモしておくと、後の作文作りがぐっと楽になります。
誰に一番伝えたいかを決める
作文は、誰かに読んでもらうために書くものです。そこで、「この作文を誰に一番読んでほしいか」を考えてみましょう。それは、いつもそばで支えてくれたお父さんやお母さんかもしれませんし、一緒に笑ったり泣いたりした親友かもしれません。あるいは、お世話になった先生や、6年後の未来の自分へ向けた手紙にするのも素敵です。
読む相手を決めることで、文章のトーンや伝えたいことがより明確になります。例えば、両親に伝えるのであれば感謝の気持ちを中心に、友達になら共有した楽しい時間のことを、先生になら教わったことへの感謝を、そして未来の自分になら今の決意や夢を伝える、といったように、自然と書きたい内容が定まってきます。
誰か一人の顔を思い浮かべながら書くことで、より気持ちのこもった、温かい文章になります。手紙を書くような気持ちで、その人に向かって語りかけるように書いてみましょう。
読みやすい!小学校6年間の思い出の作文構成
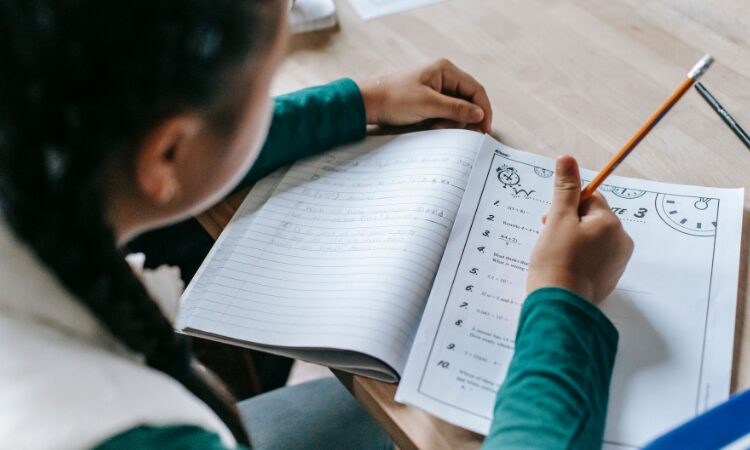
素晴らしいエピソードを見つけても、それをただ並べただけでは、読者に感動は伝わりません。読んだ人が「おもしろい!」「なるほど!」と感じるような作文にするためには、構成、つまり文章の組み立てが非常に重要です。ここでは、基本的な作文の構成である「はじめ・なか・おわり」の三部構成について、詳しく解説していきます。
「はじめ」で読者の心をつかむ
「はじめ」は、作文の顔とも言える部分です。ここで読者の興味を引くことができるかどうかで、最後まで読んでもらえるかが決まります。 まずは、これからどんなことを書くのかを簡潔に示しましょう。
例えば、「私の小学校6年間は、まるでジェットコースターのような毎日でした」のように、比喩を使ってみるのも一つの手です。また、「6年間で一番心に残っている思い出が三つあります」と、これから話すことの数を予告するのも分かりやすい書き方です。 他にも、「もうすぐこの学び舎を卒業すると思うと、胸にこみ上げてくるものがあります」と、卒業を控えた今の素直な気持ちから書き始めるのも良いでしょう。
ここで大切なのは、作文全体で一番伝えたいことは何かを意識することです。6年間の思い出を通して自分がどう成長したのか、誰に感謝を伝えたいのか、そのテーマを最初に示すことで、読者は安心して読み進めることができます。長く書きすぎず、数行でまとめるのがポイントです。
「なか」で具体的なエピソードを描写する
「なか」は、作文の中心となる最も大切な部分です。「はじめ」で選んだエピソードを、具体的に詳しく書いていきましょう。ただ「楽しかったです」「頑張りました」と書くだけでなく、その時の情景が目に浮かぶように描写するのがコツです。
そのためには、「五感」(見たもの・聞こえた音・におい・味・触った感じ)を意識して書くと効果的です。例えば運動会について書くなら、「ピストルの乾いた音がグラウンドに響き渡った」「汗と土のにおいが混じり合った」「ゴールテープを切った時の、ざらりとした感触」のように書くと、読者はまるでその場にいるかのような気持ちになります。
さらに、登場人物の会話や、自分の心の声をセリフとして入れると、文章が生き生きとします。 「『絶対勝つぞ!』と円陣を組んで叫んだ声は、少し震えていた」や、「(もうダメかもしれない)と諦めかけた時、友達の声が聞こえた」のように、その時の気持ちの変化を丁寧に書くことで、読者はあなたの体験に共感しやすくなります。一つのエピソードに絞って、その時の状況、自分の行動、そして気持ちの動きを詳しく書くことを心がけましょう。
「おわり」で自分の成長と感謝を伝える
「おわり」は、作文の締めくくりです。「なか」で書いた具体的なエピソードを通して、自分が何を学び、どのように成長できたのかをまとめます。
例えば、運動会で負けた悔しい経験を書いたなら、「この悔しさを通して、勝つことだけが大切なのではなく、仲間と力を合わせることの素晴らしさを学びました」とつなげることができます。苦手な勉強を克服した経験なら、「諦めずに努力すれば、必ず道は開けるということを知りました」という学びにつなげられるでしょう。
そして、6年間を振り返り、お世話になった人々への感謝の気持ちを伝えることも忘れないようにしましょう。 友達、先生、そして家族。具体的なエピソードを交えながら「〇〇ちゃんがいつも励ましてくれたから頑張れた。本当にありがとう」「先生のあの言葉が、今も私の支えです」「毎日お弁当を作って応援してくれたお母さん、ありがとう」といったように、感謝の気持ちを自分の言葉で表現します。最後に、中学生になったら頑張りたいことや、将来の夢について触れて、前向きな気持ちで作文を締めくくると、読後感がさわやかになります。
小学校6年間の思い出、みんなは何を書いている?作文テーマ例

「思い出はたくさんあるけれど、どれをテーマにすればいいか絞れない…」そんな人のために、多くの小学生が作文のテーマとして選んでいる人気のトピックをいくつかご紹介します。 もちろん、ここにないテーマを選んでも全く問題ありません。自分らしさを一番表現できると感じるものを選んでみてください。
運動会や修学旅行などの学校行事
運動会、学習発表会、合唱コンクール、そして修学旅行といった学校行事は、作文のテーマとして非常に人気があります。 なぜなら、クラスの仲間と一つの目標に向かって協力したり、普段とは違う特別な体験をしたりと、印象深い出来事がたくさん詰まっているからです。
運動会であれば、リレーの選手に選ばれて必死に練習したこと、応援団長として声をからしたこと、クラスが一致団結して大縄跳びに挑戦したことなどが考えられます。修学旅行なら、友達と夜遅くまで語り明かしたこと、初めて見る歴史的な建造物に感動したこと、班行動で道に迷ってしまったハプニングなど、書けることはたくさんあるでしょう。
これらの行事について書くときは、ただ「楽しかった」で終わらせずに、その経験を通して何を学び、感じたのかを深く掘り下げることが大切です。「仲間と協力することの大切さを知った」「計画通りにいかないことも、みんなで乗り越えれば良い思い出になると分かった」など、自分の成長につなげて書くと、より深みのある作文になります。
友達との何気ない日常や友情
大きな行事だけでなく、友達との何気ない日常の中にも、作文のテーマになる宝物が隠されています。 休み時間に一緒に遊んだこと、くだらないことで笑い合ったこと、時にはけんかをしてしまったけれど仲直りしたことなど、友達との思い出は6年間の学校生活を彩る大切な要素です。
例えば、「いつも一緒にいた親友との出会い」をテーマに、初めて話した日のことや、共通の趣味で盛り上がったことなどを振り返ってみるのも良いでしょう。また、けんかをして気まずい雰囲気になったけれど、勇気を出して「ごめんね」と謝り、前よりもっと強い絆で結ばれた経験は、友情の尊さを伝える感動的なエピソードになります。
「あの日、〇〇君がかけてくれた一言に、どれだけ救われたか分からない」といったように、友達からもらった優しさや励ましに焦点を当てるのも素敵です。読んでいる人も、自分の友達のことを思い浮かべ、温かい気持ちになれるような作文を目指しましょう。
苦手だった勉強や習い事を乗り越えた経験
誰にでも一つや二つ、苦手なことや好きになれないことがあるはずです。作文では、楽しかった思い出だけでなく、自分が困難を乗り越えた経験について書くことも、大きな感動を呼びます。 例えば、どうしても苦手だった算数の文章問題や、逆上がりができなくて悔しい思いをしたことなどです。
このテーマで書く際に重要なのは、「どのようにしてその苦手を乗り越えたのか」という過程を具体的に書くことです。「毎日放課後に先生に質問に行った」「友達にコツを教えてもらい、何度も練習した」「悔しくて泣きながらも、諦めずに鉄棒に向かった」など、自分の努力や工夫を詳しく描写しましょう。
そして、その経験を通じて得られた変化や成長をしっかりと書くことがポイントです。「最初は嫌で仕方がなかった算数が、問題が解けるようになるにつれて、だんだん楽しくなっていった」「逆上がりができた瞬間、世界が逆さまに見えて、自分にもやればできるんだという自信がついた」といった心の変化を表現することで、読者に勇気と感動を与えることができます。
先生や家族への感謝の気持ち
小学校6年間を無事に過ごすことができたのは、周りの人々の支えがあったからです。卒業という節目に、お世話になった先生や、いつも一番近くで応援してくれた家族への感謝の気持ちを作文にするのも、とても素晴らしいテーマです。
先生について書くのであれば、授業中に分かりやすく教えてくれたことへの感謝だけでなく、自分が悩んでいる時に親身に相談に乗ってくれたことや、失敗した時に温かい言葉で励ましてくれたことなど、具体的なエピソードを盛り込みましょう。「先生のあの一言がなければ、今の僕はいません」といったように、先生の言葉が自分の成長にどう影響したのかを書くと、気持ちがより深く伝わります。
家族への感謝を作文にする場合は、毎日当たり前のように感じていることに改めて目を向けてみましょう。「毎朝早く起きて美味しい朝ごはんを作ってくれること」「仕事で疲れているのに、宿題を見てくれること」「試合に負けて落ち込んでいる時に、黙ってそばにいてくれたこと」など、日常の中にこそ感謝の種はたくさんあります。普段は照れくさくて言えない「ありがとう」の気持ちを、作文を通して素直に伝えてみましょう。
もっと上手になる!小学校6年間の思い出の作文テクニック

構成を考え、テーマを決めたら、いよいよ文章を書いていきます。ここでは、あなたの作文をさらに魅力的で、読んだ人の心に響くものにするための、ちょっとしたテクニックを紹介します。少し意識するだけで、文章がぐっと生き生きとしてきますので、ぜひ試してみてください。
五感を使って情景を豊かに表現する
作文で出来事を伝えるとき、「楽しかった」「悲しかった」という言葉だけで終わらせてしまうと、読者にはその時の気持ちが具体的に伝わりません。そこで役立つのが「五感」です。五感とは、目で見たもの(視覚)、耳で聞いた音(聴覚)、鼻でかいだ匂い(嗅覚)、舌で感じた味(味覚)、肌で感じたこと(触覚)の五つの感覚のことです。
例えば、「運動会は楽しかったです」と書く代わりに、五感を使ってみましょう。「カンカン照りの太陽がまぶしくて(視覚)、友達を応援する声で耳がじんじんした(聴覚)。グラウンドの土ぼこりの匂いがして(嗅覚)、夢中で飲んだ麦茶は少ししょっぱい味がした(味覚)。ゴールテープを切った時の、ひんやりとした感触(触覚)は今でも忘れられない。」このように書くと、その場の情景が目に浮かぶように伝わり、読者はまるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができます。自分の体験を思い出しながら、どんなものが見え、どんな音が聞こえたか、細かく描写してみましょう。
会話文を入れて臨場感を出す
作文の中に登場人物の会話を入れると、文章にリズムが生まれて読みやすくなるだけでなく、その場の雰囲気や人物の気持ちがよりリアルに伝わります。 これを「会話文」といい、カギ括弧「 」を使って書きます。
例えば、「友達が励ましてくれました」と書くよりも、「『大丈夫だよ、君ならできる!』友達は私の肩をポンと叩いて、力強く言ってくれた」と書いた方が、友達の優しさやその時の情景がずっと鮮明に伝わります。また、自分自身の心の中のつぶやき、つまり「心の声」を入れるのも効果的です。「(もうダメかもしれない…)」と弱気になった気持ちや、「(絶対に成功させる!)」という強い決意などを書くことで、読者はあなたの気持ちの動きをより深く理解することができます。
会話文を入れるときは、誰が話しているのかが分かるように書くのがポイントです。また、会話文ばかりが続くと読みにくくなることもあるので、地の文(説明の文章)とのバランスを考えながら効果的に使いましょう。
気持ちの変化を詳しく書く
優れた作文は、出来事の報告書ではありません。その出来事を通して、あなたの心がどのように動き、変化していったのかを描くことが大切です。嬉しかった、悲しかった、悔しかったといった感情を、もっと具体的な言葉で表現してみましょう。
例えば「嬉しかった」という気持ちなら、「心臓がドキドキして、思わず飛び上がってしまった」「じわじわと胸が温かくなり、自然と笑みがこぼれた」のように表現できます。「悔しかった」なら、「唇をぎゅっと噛みしめた」「喉の奥が熱くなって、涙がこぼれそうになるのを必死でこらえた」のように書くと、その感情の強さが伝わります。
さらに、出来事が起こる前の気持ちと、起こった後の気持ちを比べることで、あなたの成長を表現することができます。「最初は『面倒だな』と思っていた係の仕事も、みんなに『ありがとう』と言われるうちに、だんだんやりがいを感じるようになった」といったように、気持ちの「ビフォー・アフター」を書くことで、作文に深みが出ます。自分の心の動きをじっくりと観察し、それを丁寧な言葉で描写することを心がけてみてください。
小学校6年間の思い出の作文で避けたい注意点

せっかく心を込めて書く作文ですから、読んだ人によく伝わるものにしたいですよね。ここでは、作文を書くときについやってしまいがちな、少しもったいない書き方とその改善方法について説明します。ちょっとした注意点を知っておくだけで、あなたの作文はもっと良くなります。
あったことの羅列になってしまう
小学校6年間には、本当にたくさんの思い出があります。 あれもこれも伝えたい、という気持ちから、運動会のこと、修学旅行のこと、友達とのこと、と色々なエピソードを少しずつ書いてしまうことがあります。しかし、これは「出来事の羅列」になってしまいがちです。たくさんの出来事が並んでいるだけで、一つひとつの印象が薄くなり、結局、読んだ人の心に何も残らないということになりかねません。
これを避けるためには、最初に決めたテーマや、特に心に残った1つか2つのエピソードに絞って、それを深く掘り下げて書くことが大切です。 例えば、テーマを「挑戦」と決めたなら、運動会のリレーでアンカーに挑戦したことだけに焦点を当てて、練習の様子、当日の緊張感、走り終えた後の気持ちなどを詳しく描写します。一つの出来事をじっくりと書くことで、あなたの気持ちの動きや成長が読者によく伝わり、共感を呼ぶ作文になります。
「楽しかったです」だけで終わらせない
作文の感想として、「楽しかったです」「嬉しかったです」という言葉はとても使いやすいですが、これだけで終わらせてしまうのは非常にもったいないです。 なぜ楽しかったのか、どのように嬉しかったのか、その理由や具体的な心の動きを書くことで、文章に説得力が生まれます。
例えば、「修学旅行は楽しかったです」で終わらせるのではなく、「修学旅行で一番心に残っているのは、友達と夜遅くまで語り合ったことです。普段は話せないような将来の夢や悩みを打ち明け合い、お互いのことをもっと深く知ることができました。あの時間があったから、私たちの絆はさらに強くなったのだと思います。だから、本当に楽しい思い出になりました」というように、具体的なエピソードとその時の気持ち、そしてその経験から得たことを付け加えてみましょう。
このように、感情の背景にあるストーリーを描写することで、読者は「なるほど、だから楽しかったんだな」と納得し、あなたの思い出を共有してくれたような気持ちになるのです。
嘘や大げさな表現は使わない
作文を面白くしようとして、実際にはなかったことを書いたり、話を大げさにしたりするのは避けましょう。例えば、本当はリレーで3位だったのに「1位になって優勝した」と書いたり、少し注意されただけなのに「先生にものすごく怒られた」と大げさに表現したりすることです。
読んでいる人は、その話が本当かどうかは分かりません。しかし、何よりも大切なのは、あなた自身の本当の気持ちや経験を、誠実に伝えることです。たとえ失敗した経験や、悔しかった思い出であっても、そこから何を学び、何を感じたのかを正直に書くことの方が、ずっと人の心を打ちます。
あなただけの、世界に一つしかない6年間の体験です。飾らない、ありのままの言葉で綴られた文章こそが、一番の魅力を持っています。自分自身の心と正直に向き合い、素直な言葉で表現することを心がけてください。
まとめ:あなただけの小学校6年間の思い出を作文で伝えよう

この記事では、小学校6年間の思い出を作文にするための方法を、準備から構成、テーマ選び、表現のテクニック、そして注意点まで、順を追って解説してきました。
まず大切なのは、いきなり書き始めるのではなく、6年間の出来事をじっくりと振り返り、どのエピソードを誰に伝えたいのかを考える準備の時間です。次に、読者が読みやすいように「はじめ・なか・おわり」の構成を意識し、中心となるエピソードを具体的に描写します。テーマは、学校行事や友達との友情、苦手なことを乗り越えた経験など、自分の心が一番動いたものを選びましょう。
さらに、五感や会話文を使って表現を豊かにし、気持ちの変化を丁寧に描くことで、あなたの作文はより生き生きとしたものになります。一方で、出来事を並べるだけになったり、「楽しかった」だけで終わらせたりしないように注意することも重要です。
作文を書くことは、6年間の自分の成長を確かめる素晴らしい機会です。あなただけの特別な思い出と素直な気持ちを、自信を持って言葉にしてください。この記事が、あなたの最高の作文作りを手助けできれば幸いです。




コメント